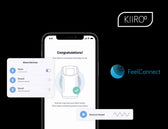パート1/12
私がセックスに関する最高傑作となる原稿を執筆中、郵送したサンプルがニューヨークの出版社の注目を集めた。
当時、自分の作品を出版することが私の人生の唯一の目的だったので、出版社の近くに住むためにニューヨークへ移住することを決意しました。自分の作品集だけでなく、ウィーンでゲルハルト・フォン・ボーデンシュタインから託された作品集もあったので、この試みに大きな期待を抱いていました。
物事は順調に進み、すぐにヴィレッジに素敵なアパートを見つけ、同時にトロント出身の可愛くて元気いっぱいなテスと婚約しました。ちょうど30歳になったばかりで、ようやく普通の責任ある大人としての生活を始められたと感じていました。
出版社から一流の編集者を紹介してもらえることになった。「ジュスティーヌ、フランス人だけど…英語は完璧だよ。二人でランチミーティングをセッティングするよ。ランチと会話を楽しんでくれ。でも、ちゃんと成果を出してくれよ」と彼は言った。
雨の降る春の日に、イーストリバーを見下ろす、素敵だけどどこか混沌としたバーにいた。誰と会うのか当ててみようと思い、少し早めに着いた。そして、当てられた。
難なく推測できた。店に入ってきた女性は洗練された雰囲気を漂わせていた。背が低く、黒髪で、黒くて鋭い目をした、40代半ばくらいの女性だった。ライトグレーのビジネススーツを着ており、スカートは膝上丈だった。黒いシルクストッキングが実にセクシーであることに、私は思わず目を留めた。しかし、すぐに我に返った。「私は、全く年齢の枠に合わない女性に興奮するためにここにいるんじゃない」と自分に言い聞かせ、そして「一体何を言っているんだ?! テスと婚約したばかりなのに!」と自問した。
私は席から立ち上がり、ジャスティンと心から握手しました。
打ち解けるために、彼女に編集の仕事に就いたきっかけを尋ねた。彼女はずっと文学に夢中だったと答えた。「でもフランス文学にはあまり興味がなくて、スウィフトやシェリー、バイロンといったイギリスの作家の方が好きだったんです。本当に好きなフランス作家はマルキ・ド・サドだけです。ご存知ですか?」と、彼女はパリらしい美しい英語で物憂げに尋ねた。
私は笑って言いました。「もちろんよ!彼は…うーん、とても興味深い作家よ」と私は言いながら、心の中では「なんて大胆な女性なの!私に言い寄ってきているのかしら?」と考えていました。
すぐに、私たちはお互いの会話を本当に楽しんでいることが明らかになりました。実際、話が止まらなくなってしまいました。午後はまるで数時間が数分のように過ぎていきました。最近私が見つけたイタリアンレストランで一緒に食事をすることにしました。ジャスティンのアパートはレストランからそう遠くなかったので、私は彼女を家まで送ってあげることにしました。
彼女の家の玄関に続く階段を上っていると、彼女は寝酒に私を招き入れた。
「これは絶対に間違っている。今すぐここを離れなければならない!」と私は心の中で言いましたが、私の声は「もちろん、いいよ」と言っているのが聞こえました。

数時間後、私たちはシャトーヌフ・デュ・パプを2本飲み干した。私は深い葛藤を感じていた。この魅惑的な女性とベッドに飛び込みたい一心だった。しかし、そんなことは考えられないと感じていた。そもそも、そんなことを考える理由があるだろうか?普段、45歳の女性を口説こうとするだろうか?もちろん、そんなことはない!そこで、私はすっかり定着しつつあったエロティックな魔法を破ろうと決意した。ジャスティンにテスとの婚約を告げたのだ。
彼女が失望と苛立ちに等しく葛藤しているのが分かりましたが、それでも彼女は平静を装っていました。私の言葉が哀れな女性に与えている影響に気づき、発した後に感じるはずだった安堵感は全く感じられませんでした。それどころか、罪悪感を感じるべきだと考えた時には感じなかったのに、正しいと思っていたことをしている今、罪悪感はますます強くなっていました。私は、すべての疑念に終止符を打つため、ジャスティンにテスの写真、そしてテスと私の写真もいくつか見せました。
それで終わりだったはずだった。私たちは最後のグラスを黙って飲み干し、ぎこちなくお互いを見ないようにした。するとジャスティンは顔面蒼白になり、ソファに深く沈み込みながら意識を失ったようだった。言うまでもなく、私はかなり驚いた。
「お願いですから、水をください」と彼女は弱々しくつぶやいた。
私は彼女の頼み通りにしました。すると彼女は私にベッドに行くのを手伝ってほしいと頼んできました。
数分後、彼女はベッドの中でまっすぐに座り、水をすすっていました。
「私は普段そんなにお酒を飲まないんです」と彼女は言った。
「大丈夫だよ。気分はどう?」
「少し良くなったわ。もう帰りたいなら、大丈夫よ。自分のことは自分でできるから。」
「いやいや、今急いで帰るつもりはない。もう少しここにいて、君の気分を伺うよ。」
「それはとても親切ですね」と彼女は言い、かすかな微笑みを見せた。
靴を脱いで、彼女の隣のベッドに座った。キングサイズのベッドはとても快適だった。すぐにうとうとし始めたが、ジャスティーンが服を脱いでいたので目が覚めた。
「気にしないでください。ただ寝る準備をしているだけなんです」と彼女は言った。
「私ももう寝たいわ」私はあくびをした。
「まあ、そのままでいいよ。もうすっかり親しい友達になったし…」
「そうね。この枕を一つ、あなたのソファに持って行ってもいいかしら?」
「私のソファ?そこで寝なくてもいいよ。あまりにも寝心地が悪いから。ここで寝なさい。」
「あら!本当にありがとうございます。感謝します。」
シャツとズボンを脱ぎ、毛布の中に潜り込んだ。ナイトガウン越しにくっきりと見える彼女の体を、つい見入ってしまった。彼女は明らかにジム通いの常習犯ではない…お腹は柔らかそうで、胸も柔らかそうだったが、ふっくらと丸みを帯びていた。眠気はたちまち消え、私はすっかり興奮し始めた。
「おやすみのキスを拒否するのは失礼だと思うよ」と私はささやいた。
「実際、フランスではそれは受け入れられないでしょう」と彼女は言い、それを「アクセプタブルー」と発音した。
キスが次々と続くのは、それほど驚くことではないかもしれない。そしてすぐに、私たちは春休み中の18歳の二人のようにキスをしていた。20分ほどキスをしていた。それから彼女は言った。
「君は本当にいたずらっ子だね。」
「それは断言できますよ」と私は笑顔で答えた。
「テスはどうなったの?」と彼女は尋ねた。
「ええ...わかっています」と私はささやきました。
「もう行った方がいいかもしれない」
「そうしてほしいですか?」
'いいえ...'
「じゃあ、私も残ります。二人ともそうしたいと思うと思います。」

「そうするわ」と彼女は言った。「でも、他の女性と婚約している男性とセックスするのは本当に申し訳ないと思うの」
「私たちはすでに一線を越えてしまった」
「あのセリフじゃないよ…」
「わかった」と私は言った。そして、もう一度彼女にキスをした。
私は指で彼女の体を愛撫した。
「それでいいんですか?」と私はささやいた。
'はい'
私は彼女の胸の間に手を滑り込ませた。
「それでいいですか?」
'はい'
私の指は彼女のガウンの下に滑り込み、彼女の左の乳首に触れました。
「それでいいですか?」
'いいえ'
「欲しくないから?」
「いいえ、それは一線を越えてしまったからです。」
「あなたのセリフじゃないよ…」
「いいえ、テスに対する礼儀の線です。」
「あなたはテスのことを知らないのね...」
「あなたは彼女を私の人生に引き入れたのです。」
彼女が私にさりげなく復讐していることに気づいた。私は愚か者で、彼女はそれが何を意味するのかを私に教えてくれた。彼女のアパートに足を踏み入れた瞬間に一線を越えてしまった。テスに関する告白は、ただの不器用な自己欺瞞だったのだ。
今や彼女は、私の欲望が耐え難いものになりつつあることを知っていた。もちろん、私たちがキスをし、愛撫し、私たちの体が互いに近づき、つま先からつま先まで触れずにはいられないほどだったとき、彼女は私の勃起を感じていた。
少し経って、私は彼女の胸をめぐる戦いに勝利した。彼女は触らせてくれたが、それ以上は許してくれなかった。私が切望していた安らぎは与えてくれなかった。こうして私は戦いに敗れた。キスと戯れ、愛撫と戯れの数時間後、彼女は「おやすみ」と言った。耳からは湯気が立ち上り、ペニスの周りの下着はまるで女の子のように濡れていた。
バスルームへ向かった。シンプルながらも豪華なバスルーム。プラクシスやホームデポでいつも何気なく通り過ぎてしまうグレイシャーベイスタイルの家具を彷彿とさせる。心臓の高鳴りが止まらなかった。自分の体を触ると、まるで私のペニスが春の香油であるかのように、彼女の人工大理石の化粧台の上に射精した。
執筆者
バジリオ・ヴァレンティーノ
イラスト:
フロリス・ピータース
フロリスはアムステルダムを拠点とするオランダのイラストレーター、ストーリーボード作家、漫画家です。
Instagramでフォローしてください @florispieterse
他の章を読む: