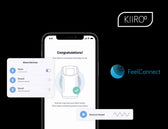パート9/12
ジャスティンとの情事はもう十分だ、と自分に言い聞かせた。彼女は私を嘲り、彼女の奇妙な世界に引きずり込み、ますます不可解な物語を織り交ぜ、半分真実の網に私を閉じ込めていた。
そして全くのナンセンス。
私は彼女を口説こうとして何週間も無駄にし、彼女の話を聞いてイライラする夜を何晩も過ごした。
物語を書いても、それでも――それでも、彼女は私にオーガズムの安らぎを与えてくれなかった。おまけに、私の執筆もほとんど進んでいなかった。突然、私の人生は停滞し、無意味に思えた。
アムステルダム通りを歩きながら考え事をしていると、突然、通りの向こう側の歩道を軽快な足取りで歩いてくる、とても素敵な若い女性の姿が見えました。世界は素晴らしい美しさに満ちていて、無数の魅力的なものや、
美しい人々を発見する日々が始まったとき、私の目を引いた若い女性が、他でもない私のガールフレンドのテスであることに気付きました。
どうして私は彼女をないがしろにしてしまったのでしょう? 私の何が悪かったのでしょう? こんなに素敵な女の子と一緒にいるために、どんな男でも殺さないでしょう? 私はうっとりと彼女を見つめました。あの長く美しい脚、あの金色の髪、あの力強い歩幅、軽やかに揺れる胸… 彼女を見つめる通りの男たちは、あの胸がブラジャーなしでもあんなにまっすぐ立っているなんて信じてくれるでしょうか?
ああ、すごい!
交通渋滞の中を駆け抜け、奇跡的にランドローバーに轢かれるのを免れ、彼女へと駆け寄った。近づくにつれ、なぜ彼女だと分かるまで数秒かかったのかが分かり始めた。彼女は全く普段とは違う服装をしていたのだ。スティレットヒールも、赤い革のミニスカートも、ましてやシースルーのブラウスも、今まで見たことがなかった。一体何が起こっているのだろう?
「やあ、ベイビー!」私は彼女に近づくと、そう言った。
「あら、やあ…」私の到着は彼女にあまり喜ばれていないようだった。
「テス、、」私は言いました。「会えて嬉しいけど…」
'しかし?'
「どうしてこんな格好をしているんですか?」
「なぜダメなの?効果があるでしょ?」
'どういう意味ですか?'
「まあ、突然、私に会うために自殺しそうになったんだね... やっと私にまた会えて嬉しいってわけか。」
「ああ、おいおい、そんなこと言わないで…私が君を愛してるって知ってるでしょ。」
「そう?最近は全然気にしてないけど」と彼女は小声で言った。
「その通り…私はあなたのそばにいてあげられなかった。ずっとよそよそしくして…自分の話に浸って、人生で一番大切なことを忘れていた。バカだったわ…ベイビー、一緒に来なよ。素敵なレストランに行って、酔っ払おう。一緒に過ごそう。」

彼女はためらいがちではあったが、私と一緒に来た。私たちはとても居心地の悪い食事をしたが、その間テスはほとんど一言も発しなかった。ウイスキーバーでラフロイグ(精液でむせる音に最も近い発音表記だとテスが言った言葉と、この銘柄は永遠に結びつくだろう)を何杯か飲んだ後、ようやく彼女はリラックスし始めた。
彼女は仕事についていくつか話してくれたし、冗談もいくつか言った。ようやく少し落ち着いたと思った矢先、突然彼女の目に涙が浮かんだ。そして、かすれた声でこう話し始めた。
「私はあなたに不公平なことを言っています。全部あなたのせいじゃないわ、バジリオ…あなたは最近私たちの関係をないがしろにしていたけど、今日の私の態度…あなたを見た時、どうしたらいいのか分からなかった…私の服装についてはあなたの言う通りだった…つまり…あなたは悪い人じゃない…私は…私は…」
彼女のすすり泣きはひどくなり、とりとめのない独白を続けることは不可能になった。
彼女が一体何を狙っているのか推測し始めると、冷や汗が毛穴から噴き出した。確かに悪いことだ…彼女が他の女と寝たのは間違いない…でも、どれほど悪いことなのだろうか?なぜ彼女は娼婦のような格好で街に出ているのだろう?彼女が何をしたにせよ、私は彼女に不誠実だった。だから、彼女を裁く権利などない。
「教えて、ベイビー、ただ教えて、何であれ、私はあなたを愛しているわ」と私は優しく話しました。
彼女は涙に濡れた目で私を見上げていた。顔にはマスカラが滲んでいた。
「そうね」と彼女はささやいた。「とても奇妙なことが私に起こったの...とても奇妙な女性とね。」
「女性と一緒にいたんですか?」と私は言った。
'はい'
「あなたは私を女性と浮気したのですか?」
「はい…本当にごめんなさい」
笑いたくなった。「それだけ?」と言いたかった。彼女が言った言葉の中で、これほどひどい言葉はなかった。頭の中で繰り広げられていた恐ろしいシナリオに比べれば、はるかにましだった。性差別主義者だ、古風だ、と言われるかもしれない。確かにそうかもしれないが、それでも私はホッとした。
他の男が私の彼女にペニスを入れるのは、あまり好きじゃない。私が今までやってきたことを考えると、それは不公平かもしれないけれど。お酒がさらに入ると、彼女の唇が緩み、物語が溢れ出した。
リサーチのために外出していた長い日々のある日、テスはブロードウェイ近くのバーにいた。普段は昼間にお酒を飲むようなタイプではなく、ましてや一人で飲むなんて! だが、退屈とフラストレーションが彼女を変え始めた。テスがそこに座っていると、きちんとした身なりをしたビジネスウーマンが近づいてきて、右隣の席は空いているか尋ねた。「全部空いていますよ」とテスは冷淡に答えた。
すると女性はテスに飲み物を勧めた。「本当に彼女?!」って思ったのよ。ウイスキーグラスの氷をぐるぐる回しながら、テスは言った。「彼女は少なくとも20歳は年上で、こんなに露骨に私に言い寄ってきたの。こんなの見たことなかった。それから、何が起こったのかわからなかった。すべてがあっという間にぼやけていくようだった。きっとお酒のせいもあったんだろう。知っての通り、私は昼間にお酒を飲む習慣がないの。でも、それでも本当に変だった。この女性と話している間、えーっと、ベイビー?」って感じだったの。

'はい'
「これをどう表現したらいいのか分からないのですが...」
「心配しないでください。私が対処します。」
「ええ、まるで彼女が私に魔法をかけたようでした。私は魅了され始めたのです。」
「彼女はあなたの飲み物に何か薬を混ぜたのですか?」
「そうは思いません。運動機能は失われていなかったし、何が起こったのかははっきり覚えています。」
「よかった…ちょっと心配させちゃったけど。」
「ええ、そうですね、私は心配しています、なぜならこの女性は... 怖いんです、バジリオ、怖いんです!」
「何を恐れているのですか?」
「彼女の!彼女は私に何かをしたんです…説明するのは難しいです。」
「話を続けてください。あなたはバーで、あの女性の隣にいました。彼女があなたに何かを頼んでいると確信したのはいつですか?」
「さっき言ったでしょ、バジリオ、彼女が現れた瞬間からそれは明らかだった」
「彼女は君に言い寄っていたんだ」
「露骨に!些細なことを話しただけなのに、彼女は私の目をまっすぐ見つめて、いたずらっぽく笑って唇を舐めたんです。威圧的でしたよ」
「脅迫されたと感じたなら、なぜ立ち去らなかったのですか?」
「そうですね、正直に言うと、私も魅了され、好奇心が湧き、興奮しました。」
「これまでに女性からそんな風に感じたことはありましたか?」
「いえいえ、全然。これは全く新しいことでした。」
「じゃあ、あなたは去らなかったのですね」と私は笑った。
実のところ、私も興奮し始めていた。テスにこの謎めいたビジネスウーマンについてもっと詳しく教えてほしかった。どんな容姿で、どんな匂いがするのか…どんな些細なことでも知りたかった。でも、今そんな質問をするのは不適切で、疑惑を招きかねないと思ったので、我慢しなければならなかった。
「だから、もうこの話をするしかないのね。もう後戻りはできないのよ」テスはため息をついた(「お願い!全部話して!」と私は思った)。「ある時点で、その女性は」
「邪魔して申し訳ないのですが」と私は言いました。「この女性には名前がありますか?」
「はい、彼女の名前はジュリエットです。」
「フランス語風に発音しますよ」と私は優しく言いました。
「はい、彼女はフランス人だと思います。」
「それは奇妙だ...」私はどもりながら言った。
「なぜその事実が、私がこれまでに話してきた他の話よりも奇妙なのでしょうか?」テスは尋ねた。
「ああ、いや、本当に奇妙で、何もかもが本当に奇妙。話も…」私は息を呑んだ。
ありがたいことに、テスは自分の窮状を心配しすぎていて、私の失態に気づかなかった。
「ええと、わかりました。長い話を短くすると、ある時点で、ジュリエットが右手を私の太ももに置いて、前にかがみ込み、彼女の鋭い緑色の目で私の目をまっすぐに見つめながら、「私と一緒に女性用トイレへ行きましょう」とささやきました。
「それで、あなたはそうしたのですか?」
'はい...'
「悪い子!」
「本当にごめんなさい!」
「実は、かなり興奮していることを認めざるを得ません。」
'あなたは?'
'はい...'
「でも私はあなたを騙したのよ!」
「ええ、そうでしたね。でも、すごくセクシーな話なんです。もっと詳しく聞かせてください」
「あなたは恥知らずだ!」
「あなたも…」
テスは顔を赤らめた。「その通りよ」と彼女は言った。「わかったわ。もっと話すわ。この汚い男め」
「ただ教えてください。」
「女性用トイレは広くて清潔で、鏡がたくさんありました。私が入ると、ジュリエットはバーとトイレの間の場所から持ってきた椅子でドアを閉めました。そして、裸になるように言いました。」
「え?まだキスもしてないのに、何もしてないのに…」
「いいえ、そうしていませんでした。」
「でも、あなたは裸になったんです...裸になったんです。」
「そうよ。私は無防備で不安で…完全に彼女の言いなりになっていました。ものすごく強烈で…心臓がドキドキして、すごく…濡れてた。ジュリエットは服を着たまま、私のところにやって来てキスをしたの。彼女はキスがすごく上手で、彼女の舌使いに私はすっかりイカされてしまったわ。彼女は私の脚の間に手を入れて、私をイカせてくれたの」
「それで彼女はまだ服を着ていたの?」
「ええ…イッた時、気を失いそうになって、しばらく彼女の腕の中で休んでいました。もう少しキスをした後、私は言いました。『ずるいわね。あなたの体を見ていないのに』」
ジュリエットは私に名刺をくれてこう言いました。「そうするでしょう。電話してください。」
それから彼女はトイレから出て行った。私が服を着てバーに戻ると、勘定は済んでいて、ジュリエットはもういなかった。
執筆者
バジリオ・ヴァレンティーノ
イラスト:
フロリス・ピータース
フロリスはアムステルダムを拠点とするオランダのイラストレーター、ストーリーボード作家、漫画家です。
Instagramでフォローしてください @florispieterse
他の章を読む:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Basilio からの詳細: