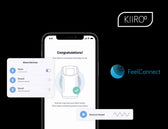恋愛に前向きな気持ちなら、このエロティックな暗号物語をぜひ読んでみてください。
ジョン・コンドルの作品は桁外れだ。緑のキャンドルに火を灯してみて。きっと、その情熱的な投資に見合う情熱的なリターンが得られるはずだ!もしかしたら、トップを吹き飛ばすかもしれない。
パート1
「あのエメラルドグリーンの瞳が、彼女について私が最初に気づいたものだった。その瞳は私を惹きつけた。私は逃げることができなかった…逃げたいと思っても、どんな手段を使っても。あの瞳の中には、緑の牧草地、古の森、緑の銀河が広がっていた…」
「大丈夫ですか?」と、紛れもなくドイツ訛りの彼女が言った。ズームアウトすると、完璧な楕円形の顔に、やや上向きの可愛らしい鼻が目に入った。身長は約160センチで、すらりとした体つきは上品な緑のドレスにすっきりと収まっていた。金色のブロンドの髪が肩から背中に流れる様子は、ボッティチェリの「ヴィーナスの誕生」を彷彿とさせた。
「大丈夫です、そうです」私はどもりながら答えた。
「何かに驚いたようでしたよ」と彼女は言った。
「はい、えーと、この絵のことです」私はぎこちなく嘘をつきました。
彼女は、私たちが出会ったばかりの隣の絵画の方を向いた。その絵はロンドン国立博物館のルネッサンス翼に掛けられていた。金の刺繍が施された絹のローブをまとった中年男性の肖像画で、絹で包まれた漏斗のような、かなり変わった帽子をかぶっていた。
「素晴らしい絵です」と彼女はため息をつきました。「こんなに好きなのは私だけだと思っていました。」
彼女は私が真実を話していないことに気づかなかったのだろうか?私をからかっていたのだろうか?それとも、私のぎこちなさを認めるにはあまりにも礼儀正しかったのだろうか?最後の可能性の方が高そうだったので、私はそれに従うことにし、嘘をつき続けるしかなかった。
「ええ」と私は言った。「ただ変な服を着た男性の肖像画だと言う人もいるかもしれないけど、私はそれ以上だと思っている。あの色彩の対比、洗練された眼差し、ルネサンス期特有の自信に満ちた楽観主義、すべてがとても上品で感動的だ。ああ、最高!」
自分が勝手に納得してしまっただけではないことを願いながら、少女の方を振り返った。彼女は輝くような笑顔でこう言った。「あなたもそう思ってくれて嬉しいわ。本当に素敵!」
「ただ芸術的な価値に感心しているだけです」と私は言った。「私たちが見ている人物についてはあまりよく知らないんです。ドージ・ロレダンの文字は読めるけど、私にはあまり意味がないんです。もっと詳しく教えていただけますか?」
「ええ」と彼女は熱心に言った。「ええ、そう思います。ロレダン元帥は1500年頃のヴェネツィア共和国の指導者でした。彼は重要で賢明な元帥、いや指導者でした。彼の治世下では、ジョヴァンニ・ベリーニを筆頭とするヴェネツィア派の画家たちが栄えました。」
「……誰がこれを描いたんだ?」
"はい..."
「本当にありがとうございます!どうしてそんなことを知っているんですか?」
「あ、私は何もかもを人に話すわけではないんです、そういうことじゃなくて…」
「そんなことは言ってないよ」私はそう言って彼女に友好的な微笑みを向けた。
「いや、違うよ。あはは、私も時々ちょっと混乱することがあるから…まあ、まあ、それが仕事だからよく分かってるんだけどね。」
「あなたは美術史家ですか?」
「はい、デュッセルドルフのK20近代美術館でキュレーターとして働いています。」
「とても印象的ですね」と私は言った。「でも、私の記憶違いでなければ、この絵は現代美術とは程遠いですね。あなたは古代美術にもご専門ですか?」
「はい、私もクリスティーズのオークションハウスで働いています。色々なスタイルや時代について知っておく必要があります。」
「とても興味深いですね。お会いできて嬉しいです。本当に光栄です!ジョンです」と私は言いました。
「私はヒルダです。」
この話をした酒飲みの常連客も頷いた。「それで、ええと、それで、芸術家気取りのドイツ人野郎を手に入れたんですね」
「そういうことだったの」とため息をつき、バーテンダーの方を向いてビールを2杯注文した。この男に心の内を打ち明けることにした理由は…いや、たまたま彼がそこにいて、どうしようもなかったから。以前にも、他の店でも、自分の話をしたことがあった。するといつも少しは心が楽になった…まるでモルヒネを飲んだみたいに。
最初の日は、本当に特別で、最高に刺激的で、ワイルドで、エロティックだった…美術館を出てからたった3時間後、私たちは酔っ払ったティーンエイジャーのように路地裏でキスをしていた。私は思い切って彼女にホテルの部屋に一緒に行こうと誘い、彼女は「いいよ」と答えた。
私たちはベッドに横たわり、何時間もキスをし、手探りで愛撫し、愛撫し合った。その間ずっと、私はあの緑の牧草地、太古の森、そして緑の銀河を思い浮かべていた…まるでこの新しい世界へと旅しているようだった。そして、服を脱いで、彼女の半月型の胸を愛でた後、それは文字通り現実になった。彼女の乳首が鼻のように上向きに反り返っているのが、まるで彼女の顔を思い出させた。
彼女の脚の間には、金色のブロンドの髪が小さな三角形を描いていた…絹のように柔らかいその脚は、すぐに私のために開き、彼女の秘密の宝物を露わにした。初めてあの完璧なピンクの膣を見た時。飛び込んだ瞬間、私はすっかり勃起していた。それでも、私は長い間耐えることができた。彼女の瞳を通して放たれる魂がエメラルドの海の波に乗ることができたからだ。
「おい、大丈夫か?」と飲み仲間がぶつぶつ言った。
「ええ…すみません、気が散ってました。」
「ああ、この汚らしい老いぼれ野郎、きっとあの女とヤっていた時のこと考えてたんだろうな?」
「はい、確かにその通りだと認めざるを得ません。」
「彼女はよかった?」
「最高。彼女のような人を想像したこともなかった。」
「彼女はいいチンコをしゃぶったか?」
「ああ、ああ、人生で一度もそんなことは…言っておくけど…あなたにはわからないわ」
「ああ、そう言ってるんだ。でも、君はここにいるのに、彼女はいない。きっと大失敗したんだね。」
「そうしました...。バーテンダーさん、ヘイニをあと2杯とジャックをあと2杯ください。」
隣の男に目をやった。典型的なラストベルトの廃人、まるで漂流物のようにバーからバーへと渡り歩いているような男だった。バーの奥にある「アルコール蒸留所」のネオン文字が、彼の顔を赤や緑の光で染めていた。
真っ暗闇が消防車の青いライトで時折明るく照らされる、極寒の夜だった。家でじっと座り込み、何をすればいいのか分からず悶々としていた私は、ついに赤いホンダのバイクに飛び乗り、この呪われた街デトロイトの果てしない工業地帯を走り抜けることにした。そして、偶然アルコホイン蒸留所に辿り着き、残りの夜を酒で過ごすことにした。

つづく
著者:
ジョン・コンドル
イラストレーター:
フロリス・ピータース
フロリスはアムステルダムを拠点とするオランダのイラストレーター、ストーリーボード作家、漫画家です。
Instagramでフォローしてください @florispieterse