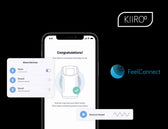パート3
アルトコインへの執着は日に日に深まり、エイダへの執着も深まっていきました。ヒルダは私がどれほど集中力に欠けているかに気づき始めました。私は、これは全て彼女のためにやっているのだと自分に言い聞かせ続けました。彼女は、これまで誰も贈ってくれたことのないほど素晴らしい贈り物を受け取ることになるのですから…感謝するべきでした。
しかし、彼女が気づいていない何か、まだ実現していない何かに、どうして感謝できるでしょうか。私たちの関係が日に日に緊張を増すにつれ、暗号空間とエイダという、新たに受け入れた安全な世界に逃げ込みたいという思いは強くなっていきました。
「エイダはどんなコインを買うように勧めたんだ?」とトムは言った。
「ネオ」
「ああ、やばい。」
「イオタ」
'ごみ'
「ゴーレム」
「そんなわけないだろ。ビットコネクトも買ったなんて言わないでくれよ」
「はい、そうしました...」
「馬鹿な男だ。自滅したな。」
「ああ、ああ…でも、最初は自分がこんなに儲かっているなんて信じられなかったから、もっとひどかった。最初は1200ドルだったのに、すぐに5000ドルくらいになったんだ」
「それはあなたが目指していたものとは全く違います。」
「いえ、全く。3週間ほどで初期資金を4倍に増やしたのですが、オークションまであと3週間しかありませんでした。何か抜本的なことをしなければならないと感じたんです。そこでカルダノ兄弟にアプローチするという計画を思いついたんです。」
「彼らが誰であろうと、それは全然良い計画とは思えない」とトムは言った。
バーテンダーは、まるで唸り声をあげる犬のようで、ニヤニヤ笑いました。さらに2杯注ぎました。「これはサービスですよ。一杯いかがですか、ハハハ」と笑っていました。
「カルダーノ兄弟は」と私は続けた。「デュッセルドルフでレストランを何軒か経営しているイタリア人の兄弟です。うちの近所にもレストランがあって、ヒルダと私はいつもそこに通っていました。彼女はカルダーノ兄弟が絵画を何点か購入するのを手伝ったので、彼らと知り合いになったんです。」
兄のロベルトは、彼のレストランで食事をするたびに、いつも温かく迎えてくれ、テーブルまで自ら案内してくれました。ある晩、他の客が全員帰った後まで滞在していた時のことです。ロベルトは私たちと同じテーブルに座り、私が今まで飲んだ中で最高のワインをご馳走してくれました。ある時、彼はこう言いました。「絵画の制作を手伝ってくれたあなた方は、常連客です。何か必要なことがあれば、本当に何でも、遠慮なくおっしゃってください。」
その瞬間、私はただ抽象的にその発言を認めただけだった。一体なぜ彼に何かを頼む必要があるんだろう?それから数ヶ月が経ち、突然、彼の提案こそが私が探し求めていた解決策のように思えてきた。
「まあ、少なくともあの状況から無事に抜け出せたね。君が話してくれたこの話は、刻一刻と不穏になってきたよ」とトムは言った。
「ええ、わかっています」私はため息をつきました。「私はロベルトのところへ行き、投資するものはすべて金に変わると確信して、2万ドルの融資を頼んだのです。」
「それで彼はあなたにそれを渡したのですか?!たったそれだけで?!」
「ええ…ええと、彼のお金を一生懸命投資していると説明しなければならなかったのですが、素晴らしいヴェネツィア絵画を買うという話になると、彼はすっかり納得してしまいました。彼はそのコンセプト全体に夢中になっていたんです。彼が即座に2万ドルの現金を渡してきた時、状況を改めて考えて、静かに引き下がっておくべきだったと思います。」
「それで、いつ、どうやって事態は悪化したんだ?」とトムは尋ねた。
「うーん…もう一口飲んでみようかな…」
「お前はお前のやるべきことをやれ、毒を飲め」
「ヒルダが私がオンラインで誰かと執拗に話していることに気づき始めた時、事態は悪化し始めました。理由はもうよく分かりませんが、ある時、インドの女の子から仮想通貨取引の指示を受けていると彼女に話したんです。彼女の名前まで口にしました。」
「彼女はそれが気に入らなかった。」
「いや、もちろん彼女はそれが気に入らなかった。でも、どうすることもできなかった。ヒルダがいない間、私はエイダと何時間も話していた。彼女のことを空想し始めたんだ」
「彼女とウェブカメラでセックスしたの?」
「いや、いや…私たちはイチャイチャはしたけど、それはまだ純真な感じだった。でもある日、エイダにすごく興奮しちゃって、電話が終わった後、彼女に似たインド人の女の子をポルノサイトで探し始めたの。彼女のような裸の体、あのコーヒー色の肌の無修正版が見たくてたまらなかったの」
「この変な奴!」
「ああ…そう、本当にひどかった。でも、一番ひどかったのは、エイダに似た女の子が出てくるポルノビデオを実際に見つけた時、ズボンからチンコを出して自慰を始めたこと。そしたら、まさにその瞬間、ヒルダが仕事から2時間も早く帰ってきた。現場で見つかったんだ」
「それは恥ずかしいことだ」
「ええ、あーん…ええ…ヒルダはびっくりしたわ。」
'当然'

「ええ、でももっとひどかったのは、デスクトップの画面で自慰行為をしている女の子をエイダだと思って、家から出て行って数日間行かなかったことなんです」
「それであなたたちの関係は終わったの?」
「いや、実は数日後、彼女が泊まっていたホテルのバーで会ったんです。」
「彼女はホテルに行ったのに、あなたは彼女の家に泊まったの?!」
「まあ、それは彼女の選択だった。もちろん、彼女に頼まれていたら出て行っただろう。でも、彼女は私をそこに置き去りにして、逃げ出したんだ」
「彼女はとても動揺していたに違いない」
「もちろんです...でもなんとか彼女に状況を説明することができました。」
「そんなことをどう説明するんだ?」とトムは言った。
「あの男を見ろ」とバーテンダーが口を挟んだ。「ハンサムだ。あの恵まれた身なりの野郎を見てみろ。あの美少年みたいな顔でやってきて、芸術について語り、安っぽい言葉遣いで、しかも自分はデトロイトの鉄鋼労働者だって言い張ってるんだからな」
「鉄骨構造のメカニック…」
「ここから出て行け」
「出て行ってほしいの?」
「いや、私が言いたかったのは、いわゆる『ここから出て行け』ってこと。さあ、そのくそったれな話を最後までやれ。」
「ええ、実際、短期的には奇跡的に許されていると思っていました。自分の主張を証明するために、インド人女性が自慰行為をしているポルノビデオをヒルダに見せたんです。すごくセクシーなビデオで、あのビデオに出てくる女性はすごくセクシーだったんです。するとヒルダの怒りは興奮に変わり始めました。
みんな、怒りと欲望の組み合わせが爆発的な何かを生み出すって知ってるよね。お互いの服を引き裂き、かつてないほど激しく突き合った。まさに炎のようだった。二人とも、この関係が破綻する運命にあることは分かっていたと思う。それが、あの時の激しい野蛮さをさらに増していたんだ」
つづく
著者:
ジョン・コンドル