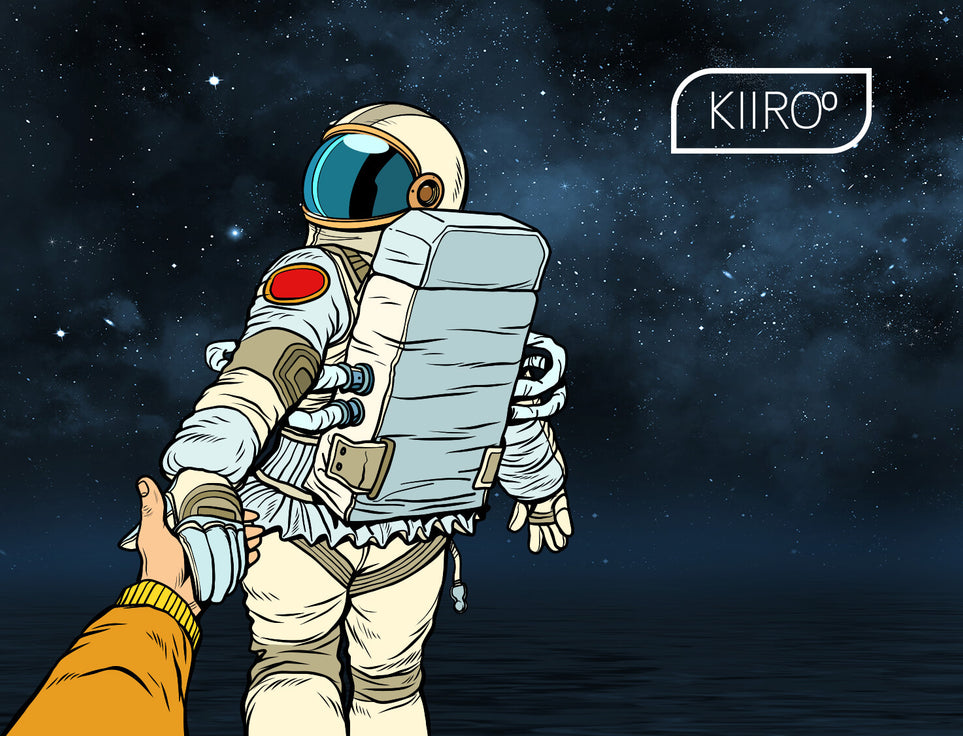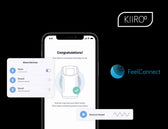パート4
「今日はすごく元気そうね」と、ヒルダが仕事に出かけてから数時間後、ビデオチャットでエイダが言った。「利益をしっかり稼がないと」と私は言った。「決意は固いし、強気な気分よ」
「あなたの頭の中にはただ一つの目的があるのですね。ただ金持ちになるためにトレードをしているわけではない。何か欲しいものがあるのでしょう。それが何なのか、教えていただけますか?」と彼女は言った。
ヒルダとの素晴らしい夜を過ごした後、突然、あの絵を手に入れるという使命に完全に集中できるようになった。エイダとのあの戯れは、ただ私を脇道に逸らしていただけだった。エイダに気持ちを伝えたいなんて、もうどうでもよかった。だから、全部話しても構わないと思った。「よかったわ」と、私が話し終えた後、彼女は言った。「気高くて、独創的で、予想外だったわ…ええ、あなたの目的に共感します」
それから私はエイダに目標があるかどうか尋ねました。
「もちろんよ」と彼女は言った。「笑わないと約束するわ。」
"私はかもしれない。"
「やめてください」
「でも、すごく馬鹿げたことだったら、どうしようもないよ。」
「恥ずかしい思いをさせてしまうよ。」
「そうしないようにします。」
彼女は喉を掻きながらこう言いました。「月に行きたいです。」
「ハハハ、当然笑っただろ!」トムは突然そう言って、左手で私の肩を叩いた。
「ええ、もちろん、馬鹿げた発言でした。でも、エイダは腹を立てました。だって、本当にそう思っていたんですから。学校でインド宇宙研究機関が打ち上げたロヒニ衛星について学んで以来、インドはいつか宇宙飛行士を月に送ると信じていたと彼女は説明したんです。」
彼女は彼らの一人になろうと決意していました。高校生の頃から、アスリートのように体を鍛え始めました。そして、数学が得意であることに気づき、喜びに胸を躍らせました。そして、数学をさらに伸ばすために昼夜を問わず勉強しました。高校卒業後は、名門バンガロール大学に入学し、数学を学び始めました。
「今まさにそうしているんです」と彼女は言った。「でも問題は、両親がもう高額な学費を払えなくなってしまったことです。それに、パーソナルフィットネスコーチの給料も払わないといけないんです」
「それで彼女は暗号通貨に頼るようになったんだ」とトムはため息をついた。
私はうなずき、バーの反対側の暗闇を見つめた。
「まったくひどい状況だ」とトムは付け加えた。
「ああ」と私は言った。「何が待ち受けているのか、全く知らなかった。エイダと私は、自分たちの利益と、お互いの成功に、とても興奮していた。借りた2万ドルのほとんどをビットコネクトに投資したんだ。そのプロジェクトが最大の利益を生みそうだと思ったからね」
「バカね。」
「ええ…2017年12月末の時点で、私のポートフォリオの価値は約8万ドルでした。絶対に成功すると確信していました。2018年1月1日、ヒルダはミュンヘンの両親を訪ねました。彼女は両親と深刻な話をしなければならないので、一人で行きたいと言いました。ドイツ語で話すのは私には退屈でしょうから。
彼女が私を連れて行きたくなかったのは、実は彼女の家族の高い基準に私が達していないからだと分かっていました。それでデュッセルドルフで何日か一人で過ごさなければなりませんでした。私は軽んじられたと感じました…彼女は私が彼女のために何をしようとしているのか理解していませんでした。確かに私はエイダと浮気をしていましたが、二流の人間のように扱われるに値しないと感じていました。
その晩、エイダからビデオ電話がかかってきた。彼女は喜びにあふれ、キラキラと輝いていた。「今日はどうしてそんなに不機嫌なの!? 大きな利益を祝わなきゃ! きっと成功するわよ、坊や! あなたはドージコインを買って、私は月に行くわ!」と彼女は叫んだ。
私は彼女に自分がなぜ不機嫌なのかを話した。
「あなたのひどい彼女は、あなたに対して全く敬意を欠いているわ!そんな仕打ちを受けるべきじゃないわ」と彼女は言った。最後の言葉の間、彼女の声は突然かすれていた。彼女は大きな栗色の目で私をまっすぐに見つめ、悪意に満ちた笑みを浮かべた。背筋と胃に、ゾクゾクするような感覚が走った。
「私には意地悪な彼女がいる価値はないわ!」私は眉を上げて言いました。
「いいえ、いいえ、あなたにはあなたに優しくしてくれる人がふさわしいのよ」と彼女は言った。
「そう?」
「はい、そうですよ。」
「優しい人…?」
「ええ、可愛いわ」彼女は唇をすぼめながらゆっくりと言った。彼女の唇がこんなに美しいピンクブラウン色をしていることに、今まで一度も気づいたことがなかった。少なくとも、それほど意識したことはなかった。「可愛い子、踊ってあげるわ」と彼女は言った。
それから彼女は立ち上がり、椅子を脇に寄せてゆっくりと踊り始めた。首を回し、目を誘惑するように動かした。「私のドレス、気に入ってくれた?」と彼女は尋ねた。私はそのドレスにすっかり魅了された。それは金色の模様が刺繍された、幾重にも重ねられた赤いドレスだった。
「手織りのバナラシ・サリーよ」と彼女は言った。カメラを床に向け、部屋の中央に敷かれたペルシャ絨毯の上にうつ伏せになった。両腕を前に伸ばし、漆黒の長い髪を床にカールさせた。彼女は顔を上げて、カメラをまっすぐ見つめ始めた。「この踊りは『捧げ物』と呼ばれているの」と彼女はささやいた。

口の中がカラカラになった。「すごくセクシーね」と、私はかろうじて言った。
「セクシーだと思う?」
「耐えられないほど…」
彼女は微笑んで続けた。地面を転がり、腕を振り回し、脚でピルエットを作った。そうこうしているうちに、手織りのサリーが少しずつ剥がれ始めた。やがて両腕全体が露わになり、次にお腹、そして脚が露わになった。サテンの下着が見えてしまった。思わず唇を舐めた。彼女も微笑んで、同じようにした。
「あなたは今私の胸を見たいのでしょうね、あなたの目を見ればそれがわかります...」
"良い..."
'良い..?"
"はい、そうします"
「あはは、全然優しくないね。嘘つきだね!」
「えーっと…」
彼女の笑顔はますます神秘的で魅惑的になった。彼女は再び手足を振り回し始め、そして突然の一撃でブラジャーを引き裂いた。
「ああ、なんてことだ」私はどもりながら言った。
「あなたの神についてはどうですか?」
「あなたの胸を作ったとき、彼は本当にインスピレーションを受けたんです…」
「悪い子だ。」
「ここで自分をさらけ出しているのね…」
「あなたも遠慮なく自分をさらけ出してください。」
"しかし..."
「でも何?」
「私が自分の正体を明かせば、この事態は、私たちが今立っている場所よりもずっと遠くまで進むことになるでしょう。」
「それは承知しております。」
「気にしないの?」
彼女は首を横に振った。「本当に大丈夫よ」と囁いた。「私が説得させて。」彼女は腰を下ろし、太ももを開いて下着を露わにした。そして右手の人差し指と中指で下着を愛撫し始めた。それから下着を少し持ち上げ、唇の外側のピンク色を覗かせた。
それ以上説得する必要はなかった。私は服を引き裂き、リビングルームに無造作に放り投げた。私たちが一緒に自慰行為をしている間、彼女は最高に甘い声をあげていた。
それから私はヒルダのラップトップに射精しました。
つづく
著者:
ジョン・コンドル