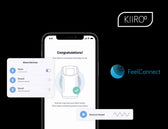「私と一緒にいてください。そして、きっと楽しんでいただけるでしょう。きっと気に入っていただけるでしょう。きっとわかるでしょう。」
興味がないと断言して会話を終えたにもかかわらず、私はそこへ行きました。そして数日後、私は何百人もの取り憑かれた変人たちの真っ只中にいました。人々は叫び声を上げ、中には激しく渇望する商品から自分たちを隔てている鉄のシャッターを叩く者もいました。
「もう一度ジョン:なぜ?」
「だって」彼はいたずらっぽく笑った。「ああ、まあ、ちょっと待って。見てろよ」
「バカね。自分がここにいるなんて信じられない。」
私は何か言いたかったのですが、太った女性が叫んで私を遮りました。
「ここでの私たちの活動が気に入らないなら、ここから出て行けばいいじゃないか!」
私が返事をする前に、ジョンは両手を挙げて私たちに冷静になるよう懇願しました。
「奥さん」と彼は言った。「落ち込む必要はありません。私たちはただ楽しい時間を過ごしたいだけなんです。さあ、キンキンに冷えたビールを一杯出して元気を出してもらいましょう」
ジョンが巨大なスポーツバッグを開けると、中は缶や冷却器具でいっぱいだったため、その女性も私と同じくらい驚いたようでした。
「そのバッグは買い物に持ってきたのかと思ってたんだけど、もういっぱい詰まってるとは思わなかったよ」と私は言った。
「店に入る前にはほとんど空いているだろう」とジョンは言った。
その間、ジョンは女性に缶ビールを手渡した。女性はすっかり困惑しているようだったが、ビールを断ることはなかった。ジョンは他の通行人とも交流を始め、すぐに10人ほどがビールを飲んでいた。
缶を開けると、蓋に小さな穴が開いていて、ごく小さなテープで塞がれていることに気づきました。ビールを2杯飲んだだけで、10杯飲んだような気分になりました。周りの人たちは騒々しくなり、陽気になりました。
ジョンがちょっと頭がおかしいのは、ずっと前から分かっていた。彼が電話をかけてきて、近所の家電量販店のブラックフライデーのセールに誘ってくれた時、彼が何かを企んでいると気付くべきだったのかもしれない。
「一体なぜそこに行く必要があるのですか?」と私は彼に尋ねました。
「そうだな」彼はニヤリと笑った。「だって楽しいだろうから」
「いや、そんなことはない。すごく迷惑になるよ。」
「信じてください。すごく面白い作品になるはずです。きっと見たくなるはずです。」
「何を見るっていうの? ショッピングモールの店を襲撃するイカれたバカの集団… なぜ? 一体どうしたの?」
その時、私たちだけではないことに気づいた。人混みの奥まで見渡す限り、飲んでいる人たちがいた。スポーツバッグを持った人たちが缶ビールを配っているのも見えた。そして、シャッターが開いた。
騒々しい買い物客たちは、まるで数千ものピクセルが一つの点に収束しようとしているかのようだった。何百人もの買い物客が店内に押し寄せ、セキュリティゲートは粉々に破壊された。どこを見渡しても、手足がねじ曲がり、顔が歪んでいるのが見えた。
突然、叫び声と泣き声はシンセサイザーとベースが織りなす音波にかき消された。エニグマの「Sadness」という曲だと分かった。それは、私が性的成長の過程で欠かせない存在だった「アンドリュー・ブレイク」のポルノ映画を思い出させた。
この曲のせいで、この乱闘に巻き込まれためちゃくちゃセクシーな女性たちが不釣り合いなほど多かったことに気づいたのだろうか?彼女たちは、まるでナイトクラブに通っているかのような格好で、あちこちにいた。
ほとんど服を着ていない人もいた…そして、服を脱いでいる人が多かった。最初は、これは揉み合いのせいだろうと思っていたが、今はもうそうではない。この豊満な女性たちにもっと近づきたいという抑えきれない衝動に駆られた。自分がすでに店の中にいることに、半ば気づいていた。
そのとき、私は完全に理解しました。なぜなら、一瞬の明晰な瞬間に、これがまったく普通のセールではないことに気づいたからです。この店で通常提供される商品は一切ありませんでした。フラットスクリーンも、ラップトップも、カメラもありませんでした。あるのは性に関する商品だけでした。
それは、私が(あるいはおそらく私たちの誰もが)今まで見た中で、最も印象的な性関連の物品の展示だった。多種多様な性具のほか、ロボットやポルノビデオのホログラム投影もあった。
それから一瞬、意識が朦朧とした。ぼんやりとした人影の中にいるようで、自分がどこにいるのか、何が起こっているのか、自分が誰なのかさえ分からなくなっていた。女の子にキスをしたのか、それとも彼女が私にキスをしたのか?私たちはもうキスをしていたのだろうか?彼女は同意を求めてきたのだろうか?
まあ、それが何であれ、私たちは確かにキスをしていたし、それは全く悪くなかった。彼女の舌はちょうど良い湿り具合で、唇は豊かで、しっかりとしているけれど柔らかい。この唇が誰のものなのか知りたくて、私は頭を後ろに引いた。
私はまったく不快感を覚えなかった。まるでアンドリュー・ブレイクの世界の女性の一人が突然スクリーンから飛び出してきて、まさにその場に現れたかのようだった。
彼女はゴージャスで背の高いブルネットの女性で、長い巻き毛と濃い黒のマスカラが、どこか東洋的な目を際立たせていた。ハイヒールを履き、黒のストッキングとベルベットの黒いランジェリーだけを身につけていた。
そして、彼女だけがその類の人ではなかった。私も同じだった。周りの男も女も服を脱ぎ始め、中には既に全裸の者もいた。群衆の殺到は乱交へと変貌していた。
かなり大きめの胸の下からジョンの頭が現れた。
「気に入るって言ったでしょ!」と彼は叫んだ。「これはただのブラックフライデーじゃない。大人バージョンだよ。ハハハ!」
それから彼はまた姿を消した。振り返ると、また聞き覚えのある声が聞こえた。
「私のウィッグ気に入ってくれましたか?本物っぽいですか?」
トリクシーだったことに、本当に驚いたのだろうか?今にして思えば、なんとも言えない。彼女は私がキスしていた女性と同じような服を着ていたが、背は10インチほど低かった。
「あの目はどうやって描いたんですか?」と私は尋ねました。
「とても未来的なメイクね!」と彼女は笑い、「今すぐ私とセックスした方がいいと思う」と付け加えた。
これまで決して些細なことは許されない日だったし、結局何も起こらなかった。まるで、大規模で容赦のない、下品な乱交パーティーのようだった。人々はおもちゃの箱を開けていた。いや、それはあまりに文明的な表現かもしれない。箱は引き裂かれ、おもちゃは群衆の中に投げ飛ばされていた。
ああ、そしてあの可哀想なロボットたち... 彼らは、ウエストワールドのプロデューサーでも顔を赤らめるような方法で暴徒に襲撃されました。
しばらくして、私は『クライムズ・オブ・パッション』のチャイナ・ブルーに似たブロンドの女を膝まづいてバックスタイルで愛撫していた。私たちの3メートルほど離れたところでは、トリクシーと背の高いそっくりさんが回転ステージでソワサント・ヌフを踊っていた。
彼らのかつらの長い茶色のカールが蛇のように彼らの周りに巻き付いており、彼ら自身も自分の尾を噛む丸まった蛇、ウロボロスのようでした。
後になってジョンは、これは全て自分が仕組んだことだと教えてくれた。彼は自分の幅広い友人や知人のネットワークを駆使して、この乱交パーティーを企画したのだ。大勢の参加者がその冗談に同調していた。女優、モデル、そしてプロのセックスワーカーもいた。
人々が缶ビールを配っていたのですが…そこには合成ではないビーガンハーブが「混入」されていました。しばらくの間、事前の知識もなく薬を盛られたことに憤慨していました。でも、この「フレッシュ・モブ」を心から楽しんだので、彼を許す気持ちが湧いてきました。
私はまだ彼がセックスイベントを宣伝する会社に雇われていたに違いないと思っているが、ジョンは賭けに負けたためにブラックフライデーの乱交パーティーを企画したと主張している。
執筆者
バジリオ・ヴァレンティーノ