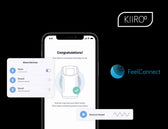バジリオ・ヴァレンティーノ
ドアベルが鳴り、ドアを開けると、玄関先に七面鳥が立っていました。いや、正確には七面鳥の着ぐるみを着た若い女性でした。彼女は私を見て微笑み、それから軽く回転しながら、背中に「お腹いっぱいにして」と書かれた小さなサインボードがピンで留められていることに気づきました。
「最近、訪問販売が本当にひどくなってきているわね。」私がため息をつき、ドアを閉めてアパートに戻ろうとしたとき、七面鳥の女性が、彼女の言うことを聞いてくれと私に促した。
「私はあなたの感謝祭のプレゼントです」と彼女は言った。
'理解できない...'
「何も理解する必要はありません。私はあなたと一緒に祝うためにここにいるのです。」
「何を祝うんですか?」
「感謝祭」
「それは馬鹿げている...」
「一緒にお祝いしてくれないの?」彼女は失望に満ちた声で言った。私はすぐに、相手が行商人ではないことに気づいた。しかし、相手が何なのかは全く分からなかった。
「わかりました」私はためらいながら言った。「入ってください」
彼女の顔には満面の笑みが浮かび、彼女は飛び上がって羽根の生えた腕で私を抱きしめました。
後ろ向きに廊下に転び込んでしまったのですが、私が足を滑らせて地面に倒れ込むと、彼女は私の上に倒れ込んできました。「あら、ごめんなさい!そんなつもりじゃなかったのに…」と彼女は泣き叫びました。
「あなたは一体誰ですか?なぜ私を困らせるのですか?」私はうめきました。
「怪我はしましたか?」と彼女は尋ねた。
「いいえ、大丈夫です。ただイライラしているだけです。」
「あら、大丈夫!私はあなたを傷つけるためにここにいるわけじゃないわ…いいえ、全く逆よ。」そう言うとすぐに、彼女は私に軽くキスをしました。
彼女を少し押し上げて、予期せぬ襲撃者をよく見ようとした。私の上に乗った少女の顔立ちはジェシカ・アルバにそっくりだった…いや、見れば見るほど、私を圧倒させたのは七面鳥のコスチュームを着たジェシカ・アルバだと確信した。
しかし、それはあまりにも突飛な考えだったので、私は突然、頭を地面に強く打ち付けて精神的に無力になってしまったのではないかと心配になりました。
「体調があまりよくないんです…」私はぶつぶつ言いました。
「まあ」と少女は言った。「ソファーへ座らせましょう。」
彼女は私を助け起こし、一緒にソファまで歩いて座りました。七面鳥の娘はキッチンまで歩いてきて、コップ一杯の水を持って戻ってきました。私は一口飲んで、もう一度彼女を注意深く、そして不謹慎にも見つめ、こう言いました。
「キッチンにいたとき、ウイスキーのボトルを見つけましたか?」
「そうしました」
「よかった…戻ってグラスを二つ注いでくれるかな。同じ戸棚にウイスキーグラスもあるし」
「ああ、見たよ」
「素晴らしい。そうしてくれる?」
「ああ、もちろん」
私たちは二人とも黙って数口飲みました。そして私は言いました。
「もし私が正しいとしたら、あなたは誰かによってここに送られたのですか?」
「その通りです。」
「誰なのか教えていただけますか?」
「いいえ...つまり、はい、お伝えできません...」
「それは不便ですね。どうしたらいいのか分かりません。」私がそう言うと、女の子は泣き始めました。
「ねえ」私は言った。「どうしたの?」
「私、ちゃんとやってないの…あなたのプレゼントになりたかったのに…全部間違ってる。私って、本当にダメなの」
「お願い、泣かないで!あなたは素晴らしい人よ。そんなこと言わないで。泣かないで!」
'しかし...'
「わからないよ…君は…うーん…君は…したいんだろう…」
彼女は涙を浮かべながら私を見て言いました。「お腹いっぱいになりたい。」
「ああ、やばい...」私はため息をついた。
「あなたはそれを望んでいません...私は失敗者です。」
「いやいや!そうよ!あなたは美しいし…私もあなたと同じくらい混乱しているだけよ。」
彼女の目が突然涙を浮かべて輝き始めたのが、少し不気味だった。『キル・ビル』に出てくる日本の暗殺者の少女を思い出した。確かに、本当に不気味だった。でも、同時にとても興奮もした。「まだ私を欲しがってるの?」と彼女は囁いた。
「えーっと…そうだね、私」 – この時、私はもう何をすればいいのか、何を言えばいいのか分からなかった – 「私は…私はそうすべきだと思う…」
「詰めるの?」
'うん...'
彼女はすぐに七面鳥の衣装を引き裂き始めた。数秒後、とても可愛くて張りのある胸が露わになった。彼女はそれを私の顔に押し当て、乳首を舐めさせた。私はまだ混乱していたが、性器が思考を支配し始めていた。そう、ペニスで考え始めると、すべてがずっと明確になっていった。
俺は彼女を地獄の底まで突き詰めた。そして二人とも何度も激しく絶頂を迎えた。彼女は午前6時頃、俺のもとを去った。
翌日は9時に起きなければならなかったので、あまり眠れませんでした。ニューヨーク・エキスポセンターで10時にジョンと会う予定だったからです。当時、私たちは20歳くらいの若者でした。
人生、自分自身について、どうすればいいのか全く分からなかった。全く分からなかった… 奇妙な仕事から、あの仕事へと移り変わり、その日はエキスポセンターの大規模な家電見本市にいた。大手テクノロジー企業のブラックフライデーの仕事をしていたのだ。
私は10時にセンターでジョンと会うことができた。かなり二日酔いだったが、生き生きとして、生きる喜びと団結心に満ちていた。
「いい夜を過ごしたから、そういうことになるんだ」と、ジョンは私が奇妙な冒険を話すと笑いながら言った。その日は二人とも共通の知り合いであるジミーと仕事をすることになっていた。彼を友人と呼ぶのは大げさすぎる。
なぜ私たちがジミーと付き合っているのか、全く理解できませんでした。彼はかなりうっとうしい人で、それどころかジョンは、ジミーがジョンの元カノ二人と親しげな関係以上の関係になろうとしているのではないかと強く疑っていると言っていました。だから、ジョンがなぜジミーを友達だと思っているのか、そもそも、そんな疑念を抱いているにもかかわらず、私には全く理解できませんでした。
いずれにせよ、私たち3人は頼まれていた通り、大手コンピュータメーカーのブースに集まりました。彼らは、非常に魅力的な新型コンピュータを発売したばかりでした。私たちの任務は、特別に設計されたカートに載せて、この新製品をフェアで宣伝することだと告げられました。
カートに展示されたデバイスに、できるだけ多くの人に手を触れてもらうことが私たちの狙いでした。できるだけ長くコンピューターに手を触れ続けた人が勝ちです。
その間、私たちはカートに乗ってコンベンションセンター内を走り回り、できる限りの騒ぎを巻き起こさなければなりませんでした。成功率を高めるため、私たちは派手で未来的なシルバーのスーツを着て、私たちの一人がメガホンを使わなければなりませんでした。ジョンはメガホンを見つけるとすぐにそれを手に取りました。
すると、銀色のスーツは2つしかないことに気付きました。
「私たちは3人いるんです」と、任務を説明してくれた男に言った。「必要なのは2人だけだ」と彼は無関心そうに言った。
「ああ、わかった。でも、具体的には3人分の仕事があるって言ってたよ」「いや、それは違う。たった2人だ」と男は言った。
'しかし...'
ジミーが口を挟んだ。「大丈夫だよ。気にしない。君たちはこの仕事をできる。大丈夫だ」「本当に大丈夫か?」
「はい、どうぞ。」
私たちは二人とも肩をすくめ、未来的なスーツに着替えてカートを動かし始めた。するとジミーが現れ、コンピューターの画面に手を置いた。
「ジミー、一体何をしてるんだ?」ジョンは叫んだ。「これ、家に持って帰るよ。」
「それは馬鹿げているよ、ジミー」と私は言った。
「それについては、あまり確信が持てないね、ジミー」とジョンは付け加えた。
「ジョン、君には僕を止めることはできないよ」ジミーはいたずらっぽくニヤニヤしながら言った。
「ああ、まさか?」ジョンはデ・ニーロ風のニヤニヤ笑いで答えた。「このクソコンピューター、君が当たらない方に100ドル賭けてもいいよ。」
「わかった、簡単だ」とジミーは笑った。「そのコンピューターと100ドルを買ってやる。ジョン、君はバカだ!」
「大丈夫だよ、ジミー。お前が最低な奴だってことは分かってる。待ってろよ」ジョンは叫んだ。「お前は負け犬になって家に帰ることになる。間違いない」
エキスポ会場を数時間歩き回っているうちに、6人が集まってきて、コンピューターに手を触れながらカートにくっついてきました。ジミーは、私たちがスタートした瞬間からそこにいたので、まだ自分が勝つと確信していました。
なかなかの見物でした。ジョンがメガホン越しに叫ぶ荒々しい声が、その場全体を盛り上げていました。彼はメガホンを手に、まさに本領を発揮していました。
彼は止められなかった。叫び、歌い、韻を踏んで…本当にクレイジーだった。あれら全部どこから湧いてくるのか全く分からなかったけど、とにかくかっこよくて、説得力があった。それでも、あの賭けには負けるだろうと思った。
それでもジョンは驚くべき手腕で任務を全うしていた。私は彼のパフォーマンスに満足し、誇りに思っていた。本当にそうだった。彼が叫ぶまでは。
「これを見て!今日は特別なものを持ってきたんだ。みんな、絶対聞いて!みんな、よく聞いて!ここにいるのがジミー、私のすぐ隣にいる男の人。ジミーは知らないんだけど、彼の妹 ― 彼がとても可愛がっている妹のことを、彼はいつも私に話してくれるの ― が、今日、彼女のとても、そう、とても、とても個人的な日記を、みんなに、いや、本当にみんなに読んでほしいって頼んできたの!さあ、始めよう。
日記帳よ、ついに来た!ついに18歳になる日!人生がここから始まるんだ、ははは。ワクワクする!ウィリアムには待ってほしいって言ったけど、彼は待った。かわいそうなビリー!彼にとっては本当に不運なことに、今日たまたまヴァレリーに会いに行ってたんだ。ふと気になってたんだけど… だって私、本当に悪い子だから。めちゃくちゃ意地悪なの、笑。
時計が12時を告げると、彼女は言いました。「ああ、ベイビーガール、ベイビーガール、もうベイビーガールじゃないわよ!」私たちは二人で飛び跳ね、踊り、叫び、抱き合いました。彼女を長く強く抱きしめすぎたので、「恥ずかしくないの?」と言いました。
「どういう意味?」と彼女は尋ねようとした。確かに尋ねたが、それはただの遊びだったか、無意味だったか、とにかく何だった。彼女は完全に私のものだった!私はあの張りのあるおっぱいをずっと見ていた。だから私は彼女にこう言った。「あの張りのあるおっぱいをずっと見ていたのよ!」
「何だって?おかしい子!男の子が好きなのに!どうしてそんな変なことするの?」と彼女は叫んだ。ええ、ええ、私は男の子が好きでした。彼女の言う通りでした。本当に好きでした。ベッドの中で、何晩も彼らのことを考えていたんです。
ずっと、彼女たちのことが頭に浮かんでいた。そしてもうすぐ、彼女たちは私の近くに来る…とても近くに…とても近くに…近い以上の存在になる。私は下唇を噛んだ。ヴァレリーはとても優しくて、可愛い女の子だった。本当に可愛い、うーん…以前から気づいていたんだけど、彼女のような女の子、コロンビアやベネズエラみたいな場所から来た女の子は、いつもすごく可愛い。
天使のような顔立ち。男の子たちが彼女たちに何を見ているのか、よく分かった。なぜ彼女たちの引き締まった曲線美に欲情するのか。もちろん、私もいい体してるわ。彼女たちの目にはそれが見えるけど、自分のお尻なんて見ないでしょ? いやいやいや。彼女のガムドロップ型の乳首が気になっただけよ。
「もういい!」ジミーは叫んだ。「こんなくだらない話は聞きたくない!」
ジョンはいたずらっぽく笑った。「でも、ジミー、簡単なんだ。出て行けばいいんだよ。この話、このとても魅力的な物語を聞きたくないなら、出て行けばいいんだよ。」
「こんな風に負けるわけにはいかない。一瞬たりとも考えないで…」
ジョンが日記を読み始めると、ジミーの声はメガホンにかき消された。
「『ずっと誰かに言いたかったことがあるんだけど』ってヴァレリーに聞いたの。『あなたって、ちょっとビッチね! ええ、ハハハ、ずっと言いたかったの…実際、そうだと思うわ!』
ヴァレリー…かわいそうなヴァレリー、緊張して混乱していたんだと思う。まさかこんなことになるなんて思ってもみなかった!私があんな風に彼女に言い寄るなんて…笑っちゃう!これを書きながら笑っちゃう。
「ジョン、こんなの馬鹿げてる。君の賭けなんかどうでもいい。ジミーだけじゃなく、私たち全員を恥じ入らせているんだ!誰も止めないなんて信じられない!」
確かにとても奇妙なことでした。会議に出席していた多くの人が私たちの話を聞いていたに違いありません。しかし、彼の突飛な行動は、気まずい視線やくすくす笑いを誘う程度で、誰も介入しませんでした。そして彼は続けました。
「ヴァレリーの抵抗はただの演技だったと思う。戸惑いもそうだった。彼女の大げさな演技が面白かった…実際、すごくセクシーだった。ワイルドで自由な気分だった。彼女の静かな頬は、触れると燃えるように熱くなった。すごく熱い!」
以前にも男の子とキスしたことがあって、大抵は楽しかった。中にはちょっとぎこちない子もいたけど、概ねよかった…でも、今回は全然違いました!ヴァレリーの顔は優しそうでした!本当に優しそうでした!あぁ、でも乳首が硬かった!
それはまさにガムドロップ型の乳首だった。本当にそうだった。想像していたよりもずっと良かった。もっと濡れていた。あのしょっぱくて、甘くて、酸っぱくて、しょっぱくて、あの匂い…彼女の脚の間を滑らせた後、私の指についた匂い。どうして私はこんなにいやらしいんだろう?どうしてこんなに汚いんだろう?わからない。でも、大好きなんだ。
彼女のあらゆるところに触れるのが大好きだった。服を脱がせるのも、さりげなく彼女のパンティーを引っ張るのも…自分のパンティーを。彼女がまだ恥ずかしがっているのも、彼女の顔を私のクリトリスに押し付けるのも、彼女の口を私の唇でこすりつけるのも、大好きだった。
その瞬間、ジミーは逃げ出した。私はかなり驚いた。少なくともジョンに襲いかかると思っていたからだ。だが、ジミーは臆病者のようにただ逃げ出した。私たちを取り囲んでいた他の人たち、まだパソコンに手を突っ込んでいた人たちは、当惑して辺りを見回した。ジョンは右手を上げて言った。
「賭けに勝てて嬉しいよ。ジミーは最低な奴だ、信じてくれ。でも、日記の最後の一節だけ付け加えたいんだ。バジリオ、君にとってその部分はすごく興味深いだろうから。さあ、よく聞いてくれ。
「どうしてジョンにこんなに従順な気持ちになるのか、自分でもよく分からない…彼は彼氏でも何でもないのに。なぜ私は彼に許し、なぜ私は…したいんだろう?彼に何かをしてもらいたい…私に何かをさせてもらいたい。彼に服を脱がされた。ニューヨークのど真ん中にあるホテルの窓の前で…私は服を脱がされた。全裸に。そして私はそうしました。
みんなに見られちゃった!興奮したわ!なんてこった!なんてこった!なんてこった、ジョン。しかも今度は、雇われた売春婦のように振る舞えって言うなんて!なんて恥知らずなの!もう二度と彼とは話さない方がいいわ。なんて想像力豊かなの!笑 クレイジー、クレイジー、クレイジー、ジョン。
わかったよ、ジョン。わかったよ、君のためにやるよ。君の変態的な想像力のおかげで、七面鳥みたいな格好をした君の友達に会いに行くんだ。オーマイゴッド!すごく興奮してる!ジョンに感謝!
執筆者
バジリオ・ヴァレンティーノ