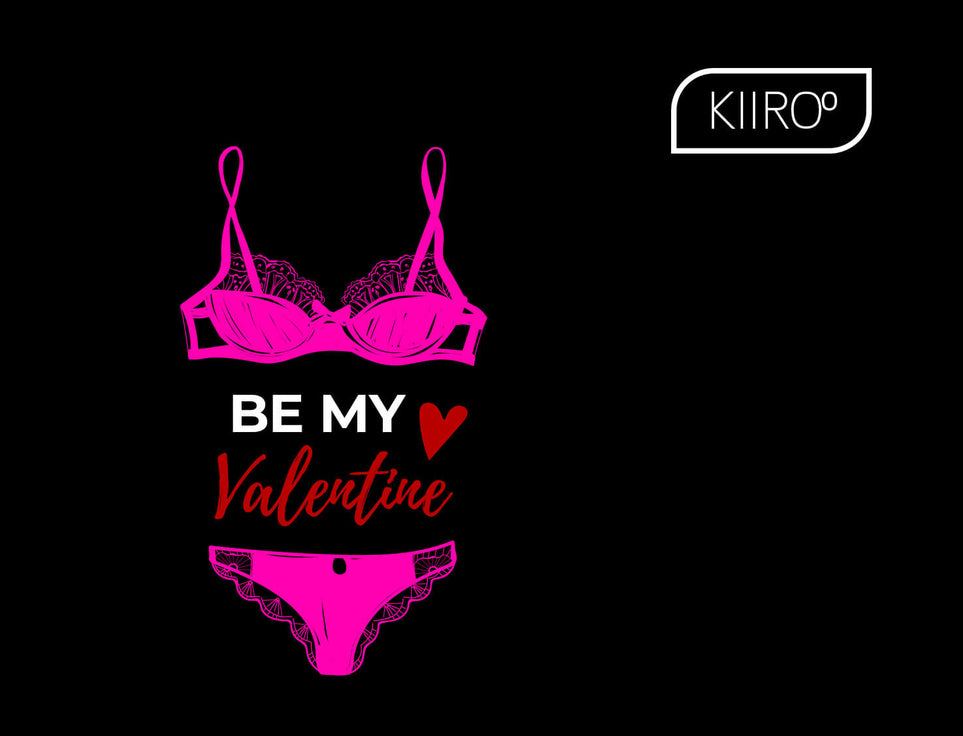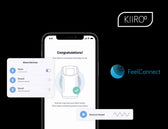去年のバレンタインデーから、あの人と2年間付き合うことになった。そうそう、エリックのこと覚えてる?まるで神様から遣わされたみたいに彫りの深いピザ配達人。もちろん覚えてるよ。
コロナが流行り始めてから、エリックは以前よりずっとピザを届けてくれるようになったし、家でもオーガズムを味わえるようになった。最初は何も期待していなかったけど、それがいつの間にか… 当たり前のことになってしまった。どうしてそうなったのかは聞かないでほしいけど、もう終わったこと。
毎日セックスしてピザを届けてくれるイケメンのピザ配達員?うーん、ちょっと話がうますぎる。それで、また独身…になった。そういえば、今日は何の日だと思う?バレンタインデー。
でも、新しく始めることにした。新しいピザ屋を見つけた。今日からエリックも、彼のペニスも、彼のディープディッシュピザも過去のもの。さあ、宇宙が定めたバレンタインデーの伝統に戻る時だ。
受話器を取り、新しいピザ屋「ジョンズ・ピザ」に電話する。ハムとパイナップルのディープディッシュピザを頼む。満足げに受話器を置く。ハムとパイナップル、今日はちょっと冒険しすぎじゃない?最近カラオケ機器を買ったんだけど、今日まで試してみたかったの。カラオケとピザ、これぞバレンタインデーの過ごし方。
ソファに丸まってNetflixで「Too Hot To Handle」を見ながら、辛抱強く待つ。エリックはこの番組に出るべきだった。そんな考えに陥る前に――誰もが危険な道だと分かっているが――ドアベルが鳴った。ピザが届いた。ガリガリのティーンエイジャーか離婚歴のある女性――よくある配達員が来るだろうと思いながら、ドアに駆け寄る。
「エリック?」私は驚いて彼を見た。「え、ピザの配達をしてるの?」
そう問いかけたけれど、答えを聞く気にはなれなかった。私とエリックがどれだけうまくいかないとしても、彼は今まで以上に魅力的に見えた。彼の筋肉がシャツの袖を締め付けているのが目に浮かび、彼の口が私のアソコを舐め、お尻を掴むたびに濡れていく記憶が蘇ってきた。
「そうだな、最後の学期を終えるまでアルバイトが必要なんだ」と彼は私のアパートをそっと覗き込みながら言った。「バレンタインデーを一人で祝うのかい?」
「あー、そう。ピザを買ってテレビでも見ようと思って。ほら、ただ一緒にいようと思って。」私たちは黙って見つめ合った。
「それはおかしい」と彼は言い、私の方へ一歩近づきました。「直した方がいいと思う」彼は片腕で私の腰を掴み、もう片方の腕にピザの箱を乗せました。唇を重ね合わせたエリケは、ピザをカウンターに落とし、私のソファによろめきながら倒れ込みました。彼の広い肩が私を包み込み、私は無力に横たわりました。
キスの合間に、エリックは「思い出が蘇るのかな?」と呟く。私は答えない。二人とも真実を知っている。彼は私のパジャマのズボンを足首まで下ろし、キスをしながら体を伝う。「また君のアソコを食べる夢を見てたんだ」
触ると濡れている私のアソコを、エリックはゆっくりと舐め始める。脚が震え始める。「潮を吹かせるか試してみろ」と彼は言い、二本の指を私の中に挿入する。彼が私の中にいる記憶が脳裏に蘇り、私は小さく悲鳴を上げた。
彼は指を動かし始めた。「それがいいの?」彼の動きがどんどん速くなるにつれ、私はうめき声を上げた。「それがいいって言ったでしょ?」私はさらに大きな声でうめいた。「うん?」もう我慢できない。
「うん!うん!お願い、ファックして。お願いー!」私は懇願する。私のアソコから愛液が噴き出し、エリックの口がそれを吸い上げる。「食べて、食べて、食べてー!」彼は指で弄りながらアソコを舐め続ける。私のアソコから愛液がゆっくりと溢れ出す。彼は指を抜き、私の口に押し込む。私は指を吸い尽くす。
彼のジーンズの一番上のボタンを外そうとしたが、彼の手が私を止めた。「だめだ、今はだめだ」と彼はソファから立ち上がりながら言った。「ただ君を喜ばせたかっただけだ」私は戸惑い、少し立ち止まった。「ちょっと待って、私とセックスしたくないの?」
「ああ、そうだよ。これはただのウォーミングアップだったんだ。」
彼はソファから立ち上がり、ドアの方へ向かった。「ハッピーバレンタインデー」
パート 1 はここでお読みください。
執筆者
ナターシャ・イヴァノビッチ
ナターシャ・イヴァノヴィッチは、Kiiroo、LovePanky、Post Pravdaなどでの執筆で知られる、親密関係、デート、そして恋愛関係をテーマにしたライターです。TheLonelySerbでは短編小説を執筆・執筆しています。彼女は犯罪学で学士号を取得し、その後、調査心理学の修士号も取得しましたが、その後、真の情熱である執筆活動に専念することを決意しました。