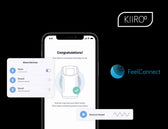汗が顔に流れ落ち、ロレインは深呼吸をした。「忘れないで」と独り言を言った。「すべては腰にあるのよ」
動きに身を任せると、太ももの間に勢いが増していくのを感じ、彼女はリズムに身を委ねた。呼吸が荒くなり、心臓が激しく鼓動するにつれ、体には湿気が溜まり続けた。彼女は頭の中で一つ一つの動きを数え、筋肉が収縮したり緩んだりする感覚に体がどう反応するかに集中した。
「23、24、25!」彼女は膝を曲げて鋳鉄製のケトルベルを地面に置きながら、心の中で息を吐いた。
トレーニング後の爽快感こそが最高だった――アドレナリンが全身を駆け巡り、解放感に包まれた。ほんの一瞬目を閉じて落ち着きを取り戻し、トレーニングへと戻った。
トレーニングを終えたロレインは寝室へ行き、背中の上部をさすった。鈍い痛みが走ってきた。もしかしたらフォームが崩れているのかもしれない。
部屋の中でこすりながら立っている間、しつこい痛みが彼女をしばらく苛んだ。しかし、すぐに彼女の注意は別のものへと逸れてしまった。
ロレインはバスルームから、パートナーが朝のルーティンをこなす、楽しそうな鼻歌を歌っているのを聞き取った。ロレインと同じくグレッグも朝型人間だったが、フィットネスにはそれほど熱心ではなかった。彼はシャワーを浴び、髭を剃り、そして即興のカラオケで一日を始めるのが好きだった。
「おはようございます!」彼はまだ鼻歌を歌いながら、陽気に言った。
「おはよう?ええ」とロレインは認めた。「いい?よくわからないけど」
その時、グレッグがバスルームのドアから顔を覗かせた。シャワーを浴びたばかりで体はピカピカで、胸はまだほんのり湿って赤らんでいた。腰には一枚のタオルがだらりと巻かれ、ヘーゼル色の瞳は心配そうに輝いていた。ロレインは何よりもその瞳に惹きつけられた。
「悪いトレーニングだったのか?」と彼は心配そうに柔らかい声で尋ねた。
「いいえ、最高でした。ただ…ちょっと痛いんです」ロレインは肩を撫でながら認めた。この関係の中で常に強い方でいようと決意しているロレインは、負けを認めるのが嫌いだった。しかし、グレッグの幼稚な心配は、いつも彼女をメロメロにさせてしまうのだった。
「そうだな」と彼は顔に半笑いを浮かべながら言った。「それについて何ができるか考えてみましょう」。
グレッグはタオル一枚のままロレインに近づき、彼女のすぐ横を通り過ぎて背を向けた。
ロレインはそっと頭を傾け、彼と目を合わせ、彼の意図を探った。愛情と心配、そして同時に渇望も感じていた。ロレインはこれから何が起こるのかを予測し、それを歓迎した。深呼吸をすると、彼の温かい体が背後に寄り添ってくるのを感じ、高まる性的な緊張を少しでも和らげようと唾を飲み込んだ。しかし、効果はなかった。
グレッグの手が彼女の肩に衝撃を与えた。指先は優しく彼女の肌に触れ、親指はしっかりと押し付けながら、心地よい円を描くように動かし始めた。彼のタッチが背骨全体に衝撃を与え、彼女は思わず背中を反らせた。まるで電撃が彼女の体を蘇らせ、運動後の朦朧とした状態を吹き飛ばしたかのようだった。
「あのね、僕はいつも君の体のラインを引き立てるライクラの素材に憧れていたんだ」グレッグは、さらに近づいていきながら告白した。
「んー、この服の下で私がどれだけ汗をかいているか気づけば、そんなにいちゃつくことはないわよ」ロレインは半分からかい、半分柔らかいうめき声で冗談を言い返した。
グレッグは身を乗り出し、ロレインは耳元で彼の息を感じながら「試してみて」とささやいた。
その言葉で彼女の次の活動が決まった。
ロレインは恐る恐る体を向け、グレッグにも同じように撫でるように誘いながら、上半身を撫で始めた。グレッグは微笑み、彼女の誘いに熱心に応え、ロレインのライクラベストのきつくて滑らかな抱擁を楽しんだ後、ゆっくりと一インチずつ肌から剥ぎ取った。
ロレインは、ほんの少し恥ずかしそうに彼を見上げ、彼が彼女のしなやかな体にしっかりと注目しているのに、彼女へのあからさまな欲望を垣間見た。傍から見れば、ロレインのような女性には到底似合わない従順な態度に思えるかもしれないが、寝室では、まさにそれが彼女の好みだった。もう強がることも、支配することもない。彼女は彼のスイートピーであり、彼は彼女の主人だった。
グレッグは上着を脱ぎ捨て、少しの間後ずさりして彼女の自然な姿をじっくりと眺めた。彼は軽く身振りでロレインに残りの服を脱ぐように合図し、彼女はゆっくりと、そして誘惑的に服を脱ぎ、肌に触れる感触を堪能した。グレッグの前で裸になると、彼の顔に微笑みが戻ってきた。今度は承認の笑みだった。彼女は自分の体が濡れていくのを感じた。
「先生、私に何をしたらいいでしょうか?」と彼女は優しく尋ねた。
「横になりなさい」と彼はきっぱりと命令した。「仰向けになって」。
ロレインは喜んで従い、見せつけるように言った。しかし、グレッグは見ていなかった。彼は一番下の引き出しに手を伸ばしていた。めったに使われず、見落としがちな引き出しだ。
「何しにそこへ行かれるんですか?」ロレインは、少し自信たっぷりに、そして好奇心旺盛に尋ねた。
「えっと…」彼は引き出しを体で覆い隠しながら話し始めた。「鋳鉄があなたの専門分野なのは承知しています。しかし、冷たく硬い鋼にも何か特別なものがあるとずっと思っていました」
グレッグはそう言うと、滑らかで威厳に満ちた様子で立ち上がり、振り返ると、手に握られた威圧的な金属製のディルドを露わにした。それはまるで完全な支配の象徴のようだった。完璧に磨き上げられた鋼鉄の輝きは朝日に輝き、ロレインは畏敬の念に息を呑むべきか、それとも今すぐ彼に抱いてほしいと懇願すべきか、迷った。彼女が迷っている間に、グレッグはシリコン潤滑剤の小瓶に近づき、それをディルドにたっぷりと塗ってからロレインに近づいた。
「後ろに下がれ」と命じられ、ロレーヌは主の意のままに身を委ねた。「さあ、目を閉じろ」
自ら闇へと身を投じたロレーヌは、すぐに金属製の差し出し物の球根状の先端が陰部に接触するのを目の当たりにした。肌に触れるだけで、快感に体が張り詰めた。刺すような冷たさと、妥協を許さない硬さ、それでいて心地よく滑らかな感触。彼女はその存在に魅了され、冷たく心地よい愛撫に身を委ねずにはいられなかった。
ロレインは、グレッグが自分の弱さを露わにしたご褒美として、ディルドの先端が陰唇とクリトリスを撫でるのを感じながら、グレッグの承認を想像するしかなかった。ディルドはクリトリスにしっかりと押し当てられ、鋼鉄のような表面が膣の筋肉を緊張させ、まるで接触を懇願するかのように感じさせた。
グレッグはまるで分かっていたかのように、すぐに従い、その重たい物体を彼女の膣へと滑り込ませた。その重さは驚くほどで、グレッグはクリトリスに当てて接触を維持していたもう片方の手とすぐに重なった。ロレインはこんなに大きなおもちゃを使ったことも、体中に震えるような冷たさを感じたこともあった。それでも、鋼鉄には少なからず利点があるというグレッグの意見には同意せざるを得なかった。
グレッグはすぐにディルドを彼女の体に押し込み始めた。最初はゆっくりと、しかし時間が経つにつれてどんどん速くなり、常にしっかりと。
金属製の器具が動くたびに、ロレインは自身の高揚感をグレッグにはっきりと伝えた。彼の親指は、背中に当てた時と同じように、巧みに彼女の体を押し付けたが、今度はクリトリスへと向けられていた。ロレインは、彼の男らしい快楽へのこだわりと、重厚な金属が彼女の体に出し入れされる滑らかな動きが織りなす感覚に、喜びに身もだえした。
グレッグの動きは容赦ない感覚の奔流へと高まり、ロレインはそれが自分を圧倒するのを感じた。その深淵の淵で揺れ動く瞬間、彼女にできること、彼女が望むこと、それは解放に身を委ねることだけだった。
ロレーヌのオーガズムはあまりにも強烈で、その壮麗さを言葉で言い表す術がなかった。その感覚は、彼女の体から溢れ出る、抑えきれない液体の奔流によってのみ伝えられ、生々しく情熱的な解放感を視覚的に示していた。息を切らしながら、彼女はぼんやりと目を開け、主を見上げた。彼の表情が、彼女に必要なすべてを物語っていた。
————————————————————–
余韻に浸りながら、グレッグは起き上がり、ロレインを見下ろした。「寝返りを打ってください」と優しく頼んだ。命令口調は、思いやりのある頼みへと変わった。ロレインは優しく微笑み、寝返りを打って応えた。
グレッグはバスルームに入り、マッサージオイルを持って戻ってくる前に、ボトルの栓を1本開けて彼女の上に体を置いた。
「それではうまくいったの?」と彼女は彼に尋ねた。
「確かにそうだ」と彼は認めた。
グレッグの手が再び彼女をマッサージしに戻ってくるのを感じ、温かいオイルが彼女の背中の中央を伝って流れ落ちた。
ロレインは一つ一つの動きを楽しみ、アフターケアが終わると彼に感謝した。しかし、一つだけ彼には言わなかった。マッサージは確かに良かったが、グレッグはすでに彼女の緊張を和らげる完璧な方法を見つけていたのだ。