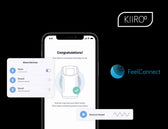それほど秘密主義ではないサンタ
重たいブーツは、人目を惹きつける靴とは言えない。まさにそこがポイントだった。スージーがかがんでツリーの下にプレゼントを置いていると、階段を下りてくる重々しい足音が聞こえてきた。娘のメアリーが、サンタクロースの衣装を完璧に着こなし、今年もクリスマスの喜びを届けてくれる彼女を見つけてくれる瞬間を待ちわびていた。
しかし、その足音は興奮しやすい7歳児の足音よりも控えめで、落ち着いているように聞こえた。それに気づいたスージーは階段の方を振り返ると、そこには恋人の姿があった。
「寝てるのよ」ローズはスージーの質問を予想しながら答えた。「テイクアウトで疲れてるのよ」
スージーは目を回し、くすくすと笑いながらローズのところへ歩み寄った。「今年はもっと軽めの食事にすべきだって言ったでしょ」
「そんなわけないでしょ!」スージーがローズの腰を抱きしめると、ローズはふざけて答えた。「知ってるでしょ?クリスマスイブはクリスマス休暇で、自分でご馳走を食べるのよ」
「うーん、テイクアウトなんて体にはあまり良くないわね」スージーは顔をしかめて、軽い調子で答えた。「あんまり食べ過ぎたら、あなたの贅沢ぶりは悪い子リストに載せなきゃいけないかもね」
「サンタさん、私が悪いことをしたって言うの?」ローズは詩的な口調で言い返した。彼女の笑顔は、喜んでそれに付き合っていることを明らかに示していた。
「ええ、本当に」スージーは喉を鳴らして言った。「サンタさんは石炭以上の罰をあなたに与えなきゃいけないわよ」
スージーはローズの背中を撫でながら、握力を強めた。
「なんでサンタさん?ちょっと変わった声ね」ローズはからかいながら少しペースを変えながら言った。「今まで聞いたサンタクロースと全然違うわ」
ローズは場面をどう設定すればいいかをよく知っていました。スージーはそれを気に入りました。
彼女は餌に食いつき、そっと近づき、人工のひげをローズさんの頬にそっと触れさせながら、耳元で何かをささやいた。
「私は今まで見たサンタとは違います」
そう言うと、スージーは一歩下がって、厚い革のベルトを外した。
彼女は自分の位置取りに非常に気を配っていた。暖炉が自分の背後にあることを確認し、自分の体を囲み、愛する人のためにこれから見せようとしているパフォーマンスを強調した。
彼女はベルトを脇に置き、バラ色の衣装の毛皮の裏地を持ち上げ、ひだを広げて、自分の体を魅惑的な贈り物にした。
「そのベルトは私じゃないの?」ローズは断言した。彼女はいつも、なかなか手に入らないふりをするのが好きだった。
「いいことが起こるのはそのうちね」スージーは彼女を安心させた。「でも今は、ヤドリギの下でサンタさんに会いに来ない?」
ローズはにやりと笑みを浮かべ、そっと近づいた。艶やかに滑らかな手でスージーのコートを撫で、ゆっくりと彼女の方へと体を寄せ、優しく献身的に乳首にキスをした。ローズの繊細な噛みつきと濃厚な吸いつきに、スージーは濡れて喜んでいたが、この状況では冷静さを保ち、主導権を握らなければならないことを彼女は知っていた。
ありがたいことに、支配と満足はしばしば同時進行する、とスージーは思った。場合によっては文字通りそうなる。
スージーはローズの片手を取り、サンタ衣装のサスペンダーをなぞらせ、ズボンと繊細なレースの下着の下に滑り込ませた。「サンタさんに、あなたがどれだけホホホホできるか見せつけてあげてもいいんじゃない?」スージーは誇らしげに笑った。
彼女の要求は、陰唇を強くつねるという形で応えられた。良い意味で。
「やりすぎ?」ローズは歯を食いしばり、高めの声で尋ねた。ヘーゼル色の瞳に甘美なサディズムを漂わせる微笑みを浮かべると、ローズは軽いタッチでスージーの襞を優しく撫で始めた。ローズがスージーのクリトリスをくるくると撫で始めると――潤滑剤も塗っていない彼女の手が、しがみつくような摩擦感を強めていた――スージーはもう我慢できなかった。
彼女はつけ髭を剥ぎ取り、サンタの帽子を脇に放り投げ、ローズに飛びかかり、熱いキスで彼女を包み込みながら、ナイトガウンをしっかりと体から引きずり下ろした。熱心に抱き合うあまり、かすかな涙の音が聞こえた。だが、気にしない。ローズへのプレゼントとして、新しいシルクのシュミーズを買っておいたのだ。
スージーは急いで服を脱ぎ、ローズを抱き上げてソファーに投げ倒しました。ローズは大喜びでくすくす笑いました。
「シーッ!」スージーは静かに言った。「メアリーを起こしちゃうよ」と念を押した。
二人ともそうではないことはわかっていたが、どちらも気にしていなかった。
「その通りよ」ローズは言った。「私は本当に悪い子だったのよ」
「そうね」スージーはそう言って、コスチュームの厚い革ベルトを取り上げてローズのおしりに当てて撫でた。
ローズがこの軽い感触を味わう時間はほんの一瞬しかなかった。スージーがベルトを次々と激しく打ち付け、ローズに襲い掛かってきた。一撃一撃が素早く鋭く正確に突き刺さるのを感じたが、ベルトの厚みが心地よく響いて、彼女の膣は興奮でびしょ濡れになった。スージーは実に頑丈なコスチュームに投資していた。その決断は報われた。
「あのサンタの手袋…」ローズは、叩く合間になんとかつぶやいた。「滑らかな素材で作られているんでしょう?」
「それを直接確かめさせてあげたらどうかしら」スージーはそう言って、ギフトバッグの一つから潤滑剤を取り出し、早めのご褒美として開けることにした。
たっぷりと潤滑剤を塗った手袋を手に、スージーはローズの濡れて熱い膣に数本の指を大胆に滑り込ませ、それから指を曲げて、挿入のリズミカルな盛り上がりを始めました。ローズの膣に指がさらに挿入されるにつれ、彼女はその激しさに息を呑み、うめき声を上げました。
手袋は滑らかでありながら、合成皮革のような質感も持ち合わせており、スージーの動きを際立たせていた。指の一つ一つが、まるで一年かけて待ち望んだ贈り物のようだった。スージーの拳がついに自分の中に突き刺さるのを感じた時、彼女はクリスマスが早く来たことを確信した。そして、彼女自身もそうありたいと願っていた。
叫び声を抑えきれず、ローズはスージーがしっかりと口を押さえつけ、拳で激しく突き続けるのを感じた。激しい突きは残忍なほど強烈だったが、同時にローズを狂わせる馴染みのある優しさも伴っていた。間もなく彼女はソファに倒れ込み、溢れ出る絶頂で濡れた水たまりができた。
ローズは満足げにハミングしていると、スージーが隣に寄り添い、優しく抱きしめてくれるのを感じた。激しいセッションの後、二人は手袋を脱ぎ、暖炉の火に温まり、安らぎを感じた。
「メアリーがサンタさんに会いに来ないのは今年が初めてよ。もう歳を取りすぎだと思う?」スージーは不安そうに恋人に打ち明けた。
「馬鹿馬鹿しい」ローズは私たちを安心させた。「メアリーはこの伝統が大好きよ。ただすごく疲れていただけ。それだけよ…それに、もしまたメアリーが寝坊してしまっても、私がここにいて、あなたたちのお祝いの飾り付けを楽しんであげるわよ」
スージーの不安は消え、表情が和らいだ。「本当に愛してるわ」
「私もあなたよ」とローズは言った。「さあ、メアリーがママがサンタクロースにキスしてるだけじゃないところを見てしまう前に、二階へ行きましょう」
スージーは、その安っぽい冗談に笑いながら、ローズを抱き上げて、クリスマスの楽しいひとときを続ける準備をしました。