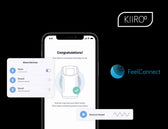選帝侯である王子が去るたびに、エリザベート王女は単なる憂鬱以上の感情に襲われました。悲しみに加え、恐怖もありました。愛する夫に二度と会えないのではないか、どうすればいいのか分からなくなるのではないかという恐怖です。もちろん、特に最初の頃は、彼と離れ離れになることが最大の悲しみの源でした。彼女は王子を深く愛し、彼と一緒にいることを切望していました。
しかし、より現実的な別の懸念が、彼女の頭に重くのしかかり始めた。当時は危険な時代であり、王子は非常に物議を醸す人物だった。実際、ヨーロッパの半数以上が、彼女の夫がいなくなったら世界はもっと良くなると確信していた。エリザベスの父は、彼女がロンドンに戻ることを許さなかった。彼女は、父の政治ゲームで許される唯一の駒は女王の地位であることを分かっていた。王女として戻ることは決してないだろう。
そして、さらに三つ目の、そしてずっと平凡な種類の恐怖が彼女の心に現れた。時が経つにつれ、この恐怖は他の恐怖を凌駕するほどに、派手なまでに薄れていった。それは退屈への恐怖だった。王子は彼女の存在そのものを高めてくれた。二人は一緒にいると、素晴らしく刺激的な会話を交わした。城を取り囲む森では、遊戯も楽しんだ。
二人は高名な学者たちが編み出した錬金術の謎を解こうとした。迷路の中で互いを探し求めた。そしてもちろん、果てしない愛の営みもあった。エリザベスは、他の人間も生きている間にこのような神聖な高揚感を味わったことがあるのだろうかと、しばしば考えていた。
そして、王子様がいない時は、これらすべてが消え去っていた。彼女は耐えられなかった。恐怖と退屈が、酔っ払った小人のように彼女の正気を削ぎ落としていた。会話は彼女の苦悩を和らげるものの、城内にも、ハイデルベルクの他の場所にも、彼女と対等に相談できる人はほとんどいないことが、すぐに王女に明らかになった。
彼らは博学か無学かのどちらかで、王妃の従順な臣下であったため、皆恐れ、当惑し、あるいは王妃に心を開くことを拒んでいた。王妃はこうした状況に常日頃から慣れており、ドレスだけでなく装いにも備わっているこの目に見えないガラスの檻を破ろうとはしなかった。こうして時が経つにつれ、内なる葛藤に突き動かされた王女は、知人たちに温かい心を持つだけでなく、積極的に友情を築こうとするようになった。
一方、繊細で分別のある王子は、滞在中に妻の心を掴む何かを考え出すために、頭を悩ませていた。そのために、ルドルフ2世の宮廷以外では比類のない、芸術家や知識人の集団を擁することができた。これ以上のことは望めないだろう。
高名な建築家イニゴ・ジョーンズは彼女のためにミニチュアの宮殿を建て、フランシス・ベーコンは彼女のために、そして彼女と共にソネットを書き、当時最も著名な俳優たちが、シェイクスピア自身が彼女の好みに合わせて作った戯曲を上演した。しかし、彼女の憂鬱は依然として十分には癒されていなかった。
そこで王子は、王女のかつての家庭教師、サロモン・デ・コーを訪ねることにしました。彼は王女にとっておそらく最も親しい友人であっただけでなく、並外れた才能の持ち主でもありました。技術者としても発明家としても、彼は比類のない存在でした。王子、イニゴ・ジョーンズ、そしてサロモン・デ・コーは、二人きりで語り合いながら、世界で最も豪華な庭園を創ろうと考えました。王女が現実から完全に切り離された、別世界の空間を。そして彼らはそれを実現しました。ホルトゥス・パランティヌスは、後に世界八番目の不思議として知られるようになりました。
庭園の建設中、イニゴ・ジョーンズはある時点でサラモン・デ・コーが示した技術的才能について驚きを表明しました。
確かに、レオナルド・ダ・ヴィンチの業績に匹敵する人物がいるとすれば、それはあなたです、と彼は言った。
これに対してデ・コーはこう答えた。「ああ、それはすでにやったよ。」
それで、ダ・ヴィンチの伝説的な機械のライオンの新しいバージョンを作ってみないかとジョーンズ氏は語った。
数ヶ月後、ハイデルベルク城の庭園を数体の機械仕掛けのライオンが闊歩しました。ライオンたちと共に、おそらくもっと奇跡的な多くのオブジェが並んでいました。中でも最も注目すべきは、メムノンの歌の像の伝説に基づいて、太陽光線に当たるとうめき声を上げ始める像と、ギリシャのオリンピック選手4人が機械仕掛けの競走を繰り広げる全長192メートルのトラックです。
王女は当然のことながら、このすべてに大喜びしていた。彼女は庭園を愛し、サロモン・ザ・コーは彼女が切望していた友となった。技師は喜びながらも、突然王女と親密な関係になったことに戸惑いを覚えた。王女は、色気を漂わせる輝く若い女性へと成長していた。若い王子が再び家を離れると、技師は恩人への忠誠を貫くことができるのかと自問する状況が生じた。そうでなければ、彼の性分には明らかに反する。
ある日、この考えが彼を非常に悩ませたので、彼は丘を駆け下りて聖霊教会に行き、祭壇の前で正しい道から外れないと誓いました。
戻ると、庭園に王女がいた。彼女は洞窟の入り口に座り、書類に熱心に読みふけっていた。顔を上げると、王女は赤らんでいた。頬は赤く、胸は高鳴っていた。技師は、王女のドレスがひどく乱れていることにも気づいた。
「大丈夫ですか、私の愛しい王女様?」彼は驚いて叫んだ。
さて、あなたが私を見つけるというのは奇妙な瞬間です、本当に奇妙なことです…王女はため息をつきました。
「どうしたんですか?何かお手伝いしましょうか?」とサロモンは答えた。
私には何も問題はありません…あなたが助けるべきではないけれど、たぶん私はあなたにとにかくそうするように頼むでしょう、と彼女は突然、予想外に、生意気な勢いで言いました。
たぶんこれを読んでいただけますか。
彼女は持っていた書類を彼に手渡した。
技師は、イザベラ・コルテーゼがフラッチャニ城に残した写本を集めて読み上げた。数文読んだ後、サロモンは突然言葉を止めた。
これは…これはダメだ!彼は叫んだ。
なぜダメなの?お姫様は喉をゴロゴロ鳴らしました。「ここが本当に魅力的なところよ!」
面白い!これは卑猥な汚物だ!どうして私にこれを読んでもらうんだ?
さあさあ…動揺しないで。君主に忠誠を誓い続けるつもりですか?
ぜひ!
それで、この物語を読んでください。とても嬉しいです。
機関士は重い気持ちで続けた。彼女を敵に回すのは危険だと分かっていた。そして、彼の心の奥底には、彼を去らせる力がありながら、全く逆の結果をもたらす何かがあった。
彼が物語の衝撃的で不健全なクライマックスに達したとき、王女は突然彼に読むのをやめるように言いました。
ああ、ありがたいことに、彼女はようやく平静を取り戻した!サロモン・デ・コーは叫んだ。
彼は彼女の目を見たとき、これ以上ないほど的を射ていたことに気づいた。
待って…その雲が通り過ぎるまで待って、と彼女はつぶやいた。
つまり、実際、この哀れな王女は完全に正気を失ってしまったのだ、と技師は独り言を言った。
しばらくして、太陽が顔を出し始めた。その日初めてだった。そして、光が庭園を照らし始めると、メムノン像はうめき声を上げ始めた。
読み続けてください!王女は泣きました。
サロモン・デ・コーが、浴びせられた卑猥な言葉を何とか吐き出そうと奮闘する間、王女は残ったドレスを引き裂いた。そして、混乱した技師が思わず覗き込んでしまうほどの、最も親密な部分に触れた王女は、彫像のうめき声に同調し始めた。彫像が自分の声を打ち消してくれることを知りながら、王女はますます激しくうめき声を上げた。
発行者
バジリオ・ヴァレンティーノ