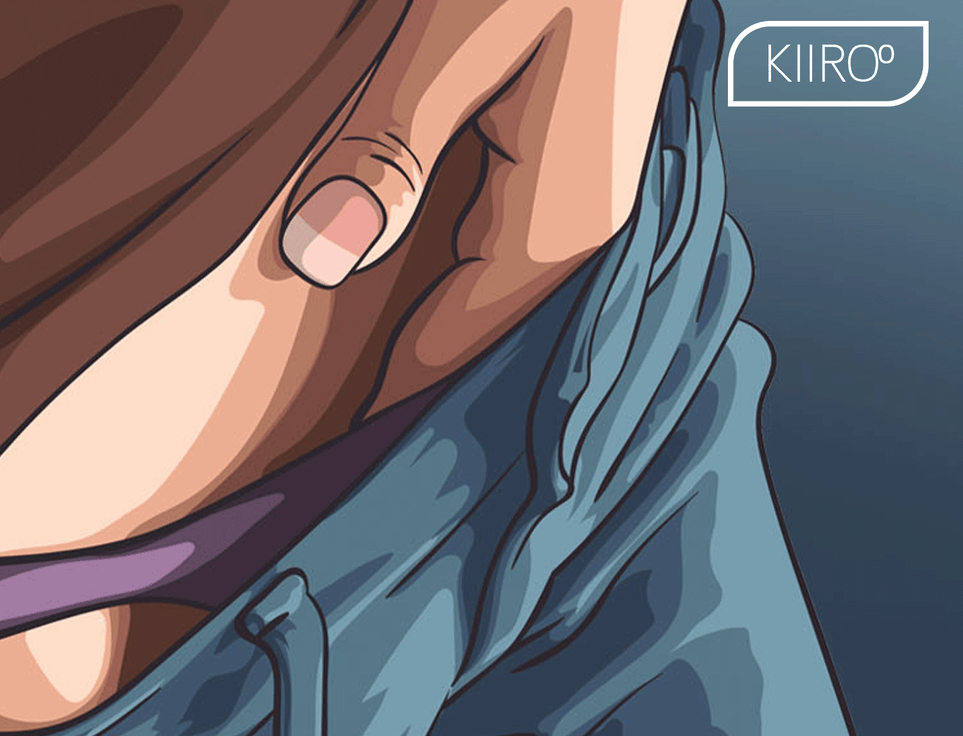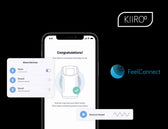バジリオ・ヴァレンティーノ
砂漠に長く留まるという決断をすぐに後悔しただけでなく、そもそもそこを離れたことさえ後悔した。サハラ砂漠を1ヶ月以上旅していたのだ。なぜそこにいたのか、そしてあの壮大な砂漠で何が起こったのかについては、また別の機会に話そうと思う。
今は、そこにいることが、私の必死の旅、つまり目的の探求の自然な到達点だったと言えば十分でしょう。私は探し求めていた強さと心の平安を見つけました。そして、再び戻る準備ができていました。
だから、変わったのは自分だけではないと知ったとき、私はひどく落胆した。いや、あの5週間で世界はすっかり変わってしまった。ほとんど見違えるほどだった。2週間で、世界は恐ろしく混乱した場所になっていた。
もっと用心深くあるべきだった。気づくことができたはずだ。実際、何かがおかしくなりそうな気配はしていた。香港からマラケシュへ飛び、そこで謎の新型ウイルスのことを耳にした。しかし、あまり注意を払っていなかった。
こういうことは以前にも起こったし、私の人生に大した影響もなかった。でも今は何もかもが変わってしまった。すべてがめちゃくちゃだ。ジャマ・エル・フナから目と鼻の先という、あんなに便利な場所にあった素敵なホテルが閉まった。街中の他のホテルも全部閉まった!
レストランもバーも喫茶店も、何もかもが閉まっていました!しかも最悪なことに、警察は人々に家に帰って屋内にとどまるように指示していました。本当はそこに居たかったのですが、仕方なくタクシーで空港まで行きました。タクシーの運転手はマスクとビニール手袋をしていて、話す気分ではありませんでした。
空港に着いても状況は全く改善しませんでした。あの忌々しい場所で丸2日間過ごし、帰国の飛行機に乗ろうとしました。努力はすべて無駄でした。同じ境遇にあるアメリカ人やカナダ人何十人もに会いました。皆それぞれ異なる情報しか持っておらず、誰も現実的な解決策を持っていませんでした。
「本当は出ていくべきなのに、なぜ閉じ込めておくんだ?」と、ある者は嘆いた。別の者は「私たちは、私たちのことを全く気にかけない国に人質として捕らわれているんだ!」と言った。
何をどう考えればいいのか分からなかった。ただ、もううんざりだ、誰とももう話したくない、あの忌々しい空港にこれ以上耐えられない、ということだけは分かっていた。街へ戻ることにした。
砂漠では、トゥアレグ族のグループと数週間旅をしていた。素晴らしいミュージシャンたち、素晴らしい仲間たち。雨に濡れた人影のないスークの路地を蛇行しながら、彼らと一緒にいればよかった、と独り言を言った。トゥアレグ族の一人、ヤクブがモロッコまで一緒に来てくれたのだ。
彼がマラケシュへ来たのは、しばらく叔父のハキムの家に滞在するためだった。別れ際に彼は、何か必要なことがあればいつでも電話するように言った。警察官に何度も嫌がらせを受けた後、誰かの助けが必要な時が間違いなく来たのだと私は思った。
ヤクブに電話して、自分の窮状を説明した。そうこうするうちに、何度も道路から離れるように言っていた警察官が私に向かって怒鳴り始めた。「ヤクブ、聞こえたか?」私は走り出しながら電話に向かって叫んだ。
「聞こえてるよ!」彼は叫び返した。「早くリヤド・スッカムへ来い!ここに居ていいぞ!」
激しい怒鳴り声を上げる数人の警官に追いかけられながら、狭い通りを駆け抜けた。ありがたいことに、私はメディナを熟知していた(読者の皆さん、その理由は後で説明します、約束します!)。ヤクブはリヤド・スッカムの外で私を待っていた。彼は両手を上げて、「ハグはダメ、抱擁はダメ!」と叫んだ。
「わかってる、わかってる…何ができる?」
「ハキムの家に行けますよ。」
「早くやってください。逮捕されてしまいます。」
友人は私を古くて大きな四角い建物に連れて行った。ちょうどいいタイミングで、外から私を追いかけていた警官たちの怒鳴り声が聞こえてきた。階段を上り、廊下を抜け、階段を下り、また廊下を抜け、中庭を横切ってさらに階段を上った。
数十枚のドアの向こうから、男、女、子供たちの声、そして時折音楽が聞こえてきた。やがて私たちは大きな部屋に辿り着き、そこでは10人ほどの男たちがトランプをしたり水タバコを吸ったりしていた。私はすぐにそのうちの一人に目を奪われた。片目しかない、ひどく醜い顔をした大男だった。
「あれは私の叔父のハキムだ」ヤクブは醜悪な巨人の方を頷きながら囁いた。友人は男たちに頭を下げ、アラビア語で話しかけた。ハキム叔父は30秒ほど話を聞いた後、激怒した牛のように怒鳴り始めた。私がいるのが彼の怒りの原因であることは明らかだった。人差し指で激しく私を指さし、ティーカップを投げつけてきたのだ。
出口に向かってゆっくりと後退すると、靴の下でガラスがいくつか砕ける音が聞こえた。「もう帰った方がいいと思う」とヤクブの耳元で囁いた。友人は踵を返し、私と一緒に部屋を出て行った。廊下に戻ると、彼は微笑んで言った。「大丈夫だよ、ここにいてもいいよ」
もう一秒でも建物の中に留まるのは賢明ではないと確信していた。ましてやそこに泊まるなんて。しかし、ヤクブはまさにそうすべきだと断言した。「他にどこへ行くんだ?」と彼は尋ねたが、私は答えられなかった。ヤクブは広大な集合住宅の端にある小さなアパートに連れて行ってくれました。「残念ながらWi-Fiはないけど、ここなら安全だよ」と友人は言いました。
あの部屋に閉じ込められた生活は、退屈であると同時に恐ろしいものだった。ヤクブは私に部屋から出ないように、誰とも交わらないようにと懇願していた。彼は一日に一度、たいてい夕方に、食べ物と、時には英字新聞や雑誌を持ってやって来た。私たちは一緒にお茶を飲み、チェスをし、ヤクブは世界的な危機に関する最新の状況を話してくれた。
数週間経ったある晩、友人は現れず、電話をかけても出ませんでした。ああ、なんてことだ、彼は病気になったんだ。入院しているかもしれない…かわいそうなヤクブ…一体どうなってしまうんだ?!翌朝も彼から連絡がなかったので、私は暗黙のルールを破ってアパートを出ることにしました。
玄関の鍵さえ持っていなかったので、鍵がかからないようにドアと枠の間にスリッパを挟みました。数分間、誰にも会うことなく廊下を歩きました。「無駄だ」と心の中で呟き、部屋に戻りました。驚いたことに、スリッパは脱がれていて、玄関のドアは閉まっていました。ドアを開けようとしましたが、中に入る方法はありませんでした。
それからヤクブにもう一度電話したが、無駄だった…脇の下と背中に冷や汗が流れ始めた。どうすればいいんだ?!しばらく、廊下をぶらぶらと歩いていた。突然、背後からくぐもった足音が聞こえた。逃げ出そうとする一方で、殴りかかろうともがきながら振り返った。もう片方の手を挙げていたが、目の前に若い女性が立っていた。
彼女は私の上げた手を取り、腰まで下ろした。彼女を見ると、私の視線はすぐに彼女の目に吸い寄せられた。瞳孔は、今まで見たことのない金茶色だった。顔の残りの部分と髪は薄緑色のスカーフで覆われていたため、その瞳の輝きはより際立っていた。
「何も言わないで」と彼女はささやいた。「私と一緒に来なさい。」
彼女は私を角へ案内し、豪華に飾られた空間のドアを開けた。黄土色の壁、深紅の長椅子、金箔の鏡、そして精巧な彫刻が施された木板に囲まれていた。ライムグリーンのカフタン(後で彼女はカフタンだと教えてくれたが、私は気づかなかっただろう)を着て、パリグリーンのスカーフを頭に巻き、エメラルドがちりばめられた金のネックレスをしていた若い女性は、その空間にすっかり溶け込んでいた。
「ここに連れて来てくれてありがとう」と私は言った。「これは本当に驚きだ。」
「ヤクブがあなたのことを話してくれたわ。誰にも会わせてはいけないの。あなたは深刻な危険にさらされているわ…ハキムはあなたをここに置きたくないの」若い女性は厳粛に言った。
「それは分かっていますが、あなたは誰ですか?なぜ私を助けてくれるのですか?」
「私はヤクブのいとこで、ハキムは私の叔父です。私の名前はスハイラです。バシリオさん、お会いできて光栄です。」
彼女は優雅にお辞儀をした。それからスカーフを外した。美しい黒髪の波が肩に流れ落ちた。
「私と一緒にいることで、すでに心地よく感じていただいて嬉しいです」と私は笑顔で話しました。
「ヤクブは、あなたは良い人だ、そして彼はあなたとの友情を大切にしていると言っていました。それは私にとってとても大きな意味があります」と彼女は言った。
突然、熱くなり、汗ばんできた。何週間も一人ぼっちで、孤立していた。スハイラは、孤立が始まってから初めて会った女性だった…そして、どんな状況であろうと、どんな男でも我を忘れさせる女性だった。突然、今にも爆発しそうな気がした。息を呑んだ。
「大丈夫ですか?」と彼女は心配そうに言った。
声を出そうとしたが、口が乾きすぎて、意味不明な言葉しか出てこなかった。すると突然、彼女の真剣な表情が、はにかんだ笑みに変わった。頬が赤く染まった。「ああ、なるほど」と彼女はささやいた。
おそらく30秒ほど、私たちはそこに立ち、見つめ合っていました。それから私は再び話せるようになりました。
「恥ずかしいです、ごめんなさい」と私はつぶやいた。
「そうですね」とスハイラさんは言いました。「分かりました…」
「何が分かりますか?」
「長い間一人でいたんだね…マフラー外さないほうがよかったかもね。」
「ええ、いや、違います!あなたはとても美しいので、信じられないくらいです…耐えられないんです…私は何を言っているのでしょう?」私はどもりながら言いました。
スハイラの金色の瞳がきらめいた。「私も長い間、独りぼっちだったの」と彼女はささやいた。
それだけで私は励まされた。彼女は歩み寄り、私の唇に自分の唇を押し付けた。柔らかく、そしてしっかりとした唇…何週間も女性の夢を見ていたのに、彼女の夢は一度も見なかった。彼女は私の心に浮かばなかっただろう。最初は舌を引っ込めていたが、すぐに私の舌、唇、そして歯を、素早く小さな動きで舐め、完璧に柔らかい舌の濡れた先端で私に触れた。
私は息を呑み、うめき声を上げた。彼女のドレスを引き裂かずにはいられなかった…あまりにも美しかった。敬意を払うしかなかった。腰のあたりまでずらし、半月型の胸を露わにした。乳白色で絹のような、小さな震えが彼女のラズベリー色の乳首を揺らした。唇を下げ、乳首に触れそうになった。舌を突き出し、触れそうになった瞬間、突然頭を上げ、彼女の腕を掴んで、予想外の動きで一気に振り返らせた。代わりに彼女の首に唇を当て、首筋、頬、耳たぶまで、とてもとても優しく舐めた。
彼女は叫び声を上げた。「そう、そう!」彼女はもはや礼儀作法を失っていた。もはや自制することも、自分を抑えることもできなかった。彼女は膝をつき、私のベルトを開いた。彼女の手は震えていた。ほとんど扱えないほどだった。しかし彼女はそれをやり遂げた。ベルトを外し、ボタンと格闘したが、それもなんとかこなした。そろそろその時だった。私は痛みに苛まれていた。私のペニスは、以前と同じように、拘束されたまま苦しんでいたのだ。
でも彼女はそれを受け止め、さらけ出し、舐めた…大切にし、吸った、プラムのように、チェリーのように、キャンディーのように、ああそう、好きだ、あなたの舐め方が好きだ、あなたが私の好きなように舐める…ああそう、ああクソッ、ああ神様!これを創ってくれてありがとう、彼女は本当に神々しく、本当に私のもの、本当に…ああ…彼女が必要なの…あなたが必要なの…あなたを手に入れるわ!
足を開いて、私はあなたに入ります、私はあなたの中にいます、私はあなたの中に入ります...そして私たちは一緒に流れ、私たちは一緒に波立ち、私たちは一緒に満ち引きします...私たちは一緒に濡れています...塩水、甘い水、甘い言葉、塩辛い唇、ねじれる腰、人生を肯定する腰...至福に満ちています...女神。
…
こうして、スハイラと私は結ばれた。欲望に屈したのだ。長い干ばつに終止符を打ち、孤独を終わらせた…そして、私たちは深刻な問題を抱えていた。そのことについては後ほど詳しくお話ししよう。
執筆者
バジリオ・ヴァレンティーノ