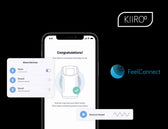忘れられない日
そのデートまでTinderを使ったことがなかったんです。別にTinderに反対していたわけじゃないんですが、スワイプしなくても結構うまくやってたんです。バーに行ったらすぐヤれるなら、わざわざ出会い系アプリを使う必要なんてないですよね?でも、同じ場所に数年も住んでいると、過去の一夜限りの関係や、忘れたい関係が頭から離れなくなるんですよね。つまり、新鮮な出会いが欲しかったんです。
でも、私はそれ以上のものを求めていた。一夜限りの関係だと、セックスがちょっと平凡になりがちだ。それも分かる。「ピチピチ」って感じじゃない限り、大抵は正常位か後背位で終わる。そろそろもっと範囲を広げて探す頃合いだ。私をあっと言わせてくれるような男性に出会いたかった。そう思って、人気の出会い系サイトTinderに登録した。
何度かスワイプした後、すぐにある男性に目が留まりました。彼の目は明るい緑色で、ダークブロンドの髪とよく似合っていました。でも、私が彼に惹かれたのはそれだけではありませんでした。私が右にスワイプした理由は、彼の「お前を食ってやる」という表情でした。「俺は女の肉の食べ方を知っている」という表情をする男性もいますが、彼はまさにその一人でした。私たちはマッチしました。それから間もなく、彼からメッセージが届きました。
"おい。"
ねえ?それだけ?私は「ねえ、どうしたの?」と答えました。
「ただ遊びに来ただけです…明日出発しますが、ぜひお会いしたいです。」
「ああ、わかった。いいね。いいよ。どこで待ち合わせする?」
「ヒルトンに泊まってるんだ。ここに素敵なラウンジがあるから、ぜひ来てね。」
「もちろん。9時にラウンジで待っててね。」
「よかった。またすぐ会おうね。」
こうして、私は初めてのTinderデートの準備を始めた。彼の好きな色や出身校を知っていただろうか?いや、いや、でも今はそんなことは関係なかった。
タイトな黒のミニドレスを着てヒルトンに到着した。ラウンジに入ると、彼が隅のテーブルにワイングラスを持って座っているのが見えた。彼は私を見上げて微笑み、席から立ち上がって挨拶した。私たちの間にはすでに性的な緊張感が漂っていた。しかも、実物はもっとハンサムだった。
息つく間もなく、彼の視線は私を貫いた。彼が私を抱きしめると、彼の手はしっかりと私の腰を掴み、柔らかな唇が頬の端に触れた。私はすでに濡れていた。私たちは再び席に戻り、彼はワインを一杯注文した。
「つまり、趣味で旅行してるってこと?それとも…」
「ええ、基本的には。友達と来たんですが、今夜はみんなクラブに行くことにしたんです。」ウェイトレスがテーブルに来て、赤ワインのグラスを私の前に置いた。
私はワインを一口飲んで、「それで、あなたは彼らと出かけたくないの?」と言いました。
「あなたの写真を見た後ではそうは思わないよ。」
なかなか滑らかな線だ。私はくすくす笑いをこらえながら、顔を赤らめた。「そうなの?」
「嘘はつかないよ」と彼はワインを一口飲みながら言った。私たちは数秒間、沈黙のうちに見つめ合った。彼の目は、私が知りたいことをすべて語っていた。そして、私の目は彼に許可を与えていた。
「お部屋を見せていただきたいです」と私は微笑んだ。「きっと素晴らしい街の景色が見えるでしょうね」
「ああ、きっと気に入るよ。」
「じゃあ、何を待っているの?」と私は悪魔のような笑みを浮かべた。
私たちは同時にテーブルから立ち上がった。彼は私のところまで歩み寄り、手を取って彼の部屋へと連れて行った。脚の間の熱が体中を駆け巡るのを感じた。彼は話し始めたが、私は聞いていなかった。下着が濡れた唇に押しつぶされ、アソコは興奮でうずいていた。
彼がホテルの部屋のドアを開けると、私もついてきて中に入った。Tinderデートって、みんなこうなるの?と、後ろでドアが閉まる瞬間に思った。でも、その考えはすぐに消えた。彼が振り返り、私の腰を掴んで引き寄せた時だ。柔らかく湿った唇が首筋の隅々までキスをし、片方の手が情熱的に私の体を抱きしめた。彼が覆わないところは1インチたりともなかった。私は、彼に見逃してほしくなかった。
彼は私をひっくり返し、壁に押し付け、ドレスを腰まで持ち上げた。背中にキスをしながら下へ下り、ゆっくりと膝をつき、お尻をこすり、掴み、叩いた。うずくような感覚が強くなり、愛液が内腿を伝って流れ落ちるのを感じた。彼の手が私の下着を足首まで下ろした。
彼は両頬を掴み、広げると、口をずっぽりと突っ込み、吸ったり、舐めたり、舌で舐めたりした。膝が震え始め、一瞬、崩れ落ちるかと思った。彼は濡れた膣に二本の指を滑り込ませ、ゆっくりと挿入していく。そこから私はもう我慢できなくなった。「なんてこった、君の味が最高だ」と彼は口いっぱいに尻を突っ込みながら言った。彼が私の奥深くへと入っていくにつれ、私は大きな声でうめき声を上げた。ああ、神様、彼は私をイカせてくれる、と私は思った。
彼は私を食べるのをやめ、片方の尻にキスをした。「シャワーを浴びろ」と、愛液が滴る口元で言った。私は急いでドレスと下着を脱ぎ、ウォークインシャワーに入った。彼はシャツを脱ぎ、筋肉質な体を露わにした。私はこれまで男性の裸を何人も見てきたが、彼の体は美味しそうなほど逞しかった。
彼がシャワーに入ってくる間、私はお湯を張った。まるで何日も何も食べていないかのように私を見つめていた。お湯は私の体を伝い、体の曲線から滴り落ちた。彼は首筋にキスをし、胸へと移った。舌で硬くなった乳首を弄り、力強い手で優しく掴んだ。「君を食べたい」と彼は呟いた。
彼はゆっくりと私の体に沿ってキスをし、唇を膣に当てた。唇を舐め、それから口で広げた。彼の舌がクリトリスに押し当てられると、私は目を閉じ、頭を後ろに傾け、愛液が体中を伝っていくのを感じた。
「オーマイゴッド」私は大声で呻き、滑りやすいシャワーの壁にしがみついた。「オーマイゴッド」私は叫び、支えを探しながら両手を振った。彼は私の手を見ずに掴み、自分の頭に置いた。彼は激しく私を舐め続け、私は喜びで体を前にかがめながら、彼の髪を掴んだ。
「私をイカせてくれるのよ」私は大声で叫んだ。
すると彼はすぐに立ち上がり、私の足を掴んで自分の上に持ち上げた。背中は冷たいシャワーのタイルに押し付けられ、うめき声を上げながら、彼の硬いペニスが私の中に滑り込むのを感じた。
「待って」と私は言おうとした。「これって安全?」
彼は笑いながら、私を激しく突き上げた。「心配しないで。ちゃんとするから」と彼はまた突き上げた。「君をしっかり扱ってあげるよ」
彼のしっかりとした腕に抱きしめられ、私は彼のペニスを楽々と上下に揺らした。彼の動きが緩み、シャワールームの床に私を下ろした。私は仰向けに寝かされ、彼は私の脚の間にひざまずいた。
「君がイクのが待ちきれないよ」と彼は言った。私は少し息を切らしながら彼を見た。「じゃあ、私が潮を吹くのも気に入ってくれるといいな」彼は大きな目でニヤリと笑った。二本の指が私のアソコに滑り込み、「待ちきれないよ」と彼は言った。
彼の指はゆっくりと前後に、そして上下に動き始めた。スピードが上がり、頭を後ろに傾けると、膣がきつく締まるのを感じた。「うん、うん、うん!」私は叫んだ。彼の指はどんどん速く動いていた。
「そうっ!」私のアソコは何度も潮を吹き始めた。「止めないで」と私は懇願した。彼はそのまま続け、腕の血管が浮き出て、私のアソコ汁はシャワーの床に流れ落ち続けた。彼はうめき声をあげ、指を抜いて口に突っ込み、私のアソコ汁を吸い上げた。
体が収縮するにつれ、私は頭を前に突き出した。「イっちゃう」と囁き、我慢しようとした。でも、もう無駄だった。彼はもうイキそうだった。次の瞬間、私は彼の頭を掴み、長いうめき声を漏らし、体がピクピクと震えた。彼が顔を上げて、微笑んでいるのが見えた。私も安堵して微笑み返した。「さあ、その美しいペニスを私の中に入れなさい。今夜、イクのは私だけじゃないはずよ」
彼は私の体を自分の方へ引き寄せ、両足を肩に乗せた。ペニスを私の中に滑り込ませながら、彼は目を閉じて言った。「マジかよ、こんなに濡れてるんだ」。少し驚いたように、彼は目を開けて私を見つめた。もう長くは続かないだろうと分かり、顎が落ち、目を細め始めた。
ああ、彼はイっちゃう、と私は思った。数回突き上げると、彼の体が緊張し、私の中で彼のペニスが収縮するのを感じた。彼はゆっくりと私の上に倒れ込み、私の首に激しく息を吹きかけた。「ああ」と彼は息を切らしながら言った。「これは今までのTinderデートの中で一番いいかもね」
著者
ナターシャ・イヴァノビッチ
ナターシャ・イヴァノヴィッチは、Kiiroo、LovePanky、Post Pravdaなどでの執筆で知られる、親密関係、デート、そして恋愛関係をテーマにしたライターです。TheLonelySerbでは短編小説を執筆・執筆しています。彼女は犯罪学で学士号を取得し、その後、調査心理学の修士号も取得しましたが、その後、真の情熱である執筆活動に専念することを決意しました。