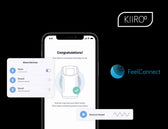2回目のデート
前回のデートがどうしても忘れられない。彼に会ってから何ヶ月も経っているのに、まるで昨夜のことのように感じてしまう。つまらない人生を送っていたのかもしれない。考古学を学ぶ学生として、私はただ岩や土を拾い集め、いつか掘り出す価値のあるものを見つける日を待っているだけなのに。
まだ実現していませんが、彼のおかげで大当たりしたような気がします。考古学的発見の宝庫に出会ったような気がします。
でも、旅先で出会う人たちの問題は、結局は旅立たなくてはならないということ。翌日、彼はロンドン行きの飛行機に乗ってしまい、私には思い出だけが残ってしまいました。彼にメッセージを送ることもできたけれど、一体何の意味があったのでしょう?
ええ、あの夜は最高だったし、最初から最後まで一緒にやったこと全部覚えてる。でも彼はあそこにいて、私はこっちにいる。いい思い出として残して、前に進むのが一番だよね?
金曜日はチームと山で考古学の発掘調査をしていました。雨が降っていて、土を掘り返しながら泥だらけになっていました。家に帰ったらNetflixをつけて、寝る前にホットチョコレートを一杯作ろうと決めていました。
でも、人生って面白いものね。一瞬で状況が変わることもある。ポケットの中でスマホが振動するのを感じた。あまり気にしていなかったけど、その後も何度か振動した。
うーん…何かあったのかな?お母さんに何もないといいけど。手袋を外してポケットを探り、スマホを取り出した。彼だった。
最後に会ってからずっと、君のことを考えずにはいられない。おかしいと思うかもしれないけど、チケットを買って、空港で君のところに向かっているんだ。君に会いたい。君の味を味わいたい。午後7時にヒルトンで会おう。
「マジかよ!」と声に出して叫んだ。体が熱くなり、背中に汗がにじみ出ているのを感じた。泥だらけの自分の姿を見下ろした。彼に返信した。「行くよ」
上司に体調が悪いと伝え、車に飛び乗って家へ向かった。泥と土の臭いを落とすのにたった数時間しかなく、それは容易なことではなかった。苦労してようやく定番の黒のカクテルドレスに着替え、7時を回った頃にはヒルトンホテルのラウンジにいた。
ラウンジは薄暗く、点いている照明はほんの数個だけだった。彼は部屋の隅の二人掛けソファに座っていた。彼は顔を上げて、私たちの視線を釘付けにした。彼の姿は、さらにセクシーに見えた。
新しい髪型?そんなことはどうでもいい、前よりずっとセクシーになったわ。私が彼の方へ歩いていくと、彼は立ち上がって手を差し出した。私はその手を掴み、彼に引き寄せられた。
「君を見てるだけで勃起しちゃうよ」と彼は私の耳元でささやいた。
私は少し身を引いて彼の目を見つめながら言いました。「私の中に入るまで待って。」
私たちは並んでソファに座り、沈黙の中で見つめ合った。彼の手が私の太ももに触れていたので、彼の目が何を語っているのか、はっきりとわかった。
「久しぶりだな」と彼は言い、ゆっくりと私の太ももを撫で、私のアソコに少しずつ近づけていった。
「もう長いことご無沙汰だったわ」と答えた。彼はさらに近づき、唇を私の唇に重ね、手でパンティの裏地を撫でた。パンティは徐々に私の愛液で濡れてきていた。
息がどんどん荒くなってきたので、私は「二階へ行きましょう」と提案した。
「そんなに待てないよ」彼の指がパンティの中に滑り込んだ。ふと周りを見回すと、ラウンジには数人が散らばって葉巻を吸いながら政治談義をしていた。誰も気づかない…よね?
考え事をしていると、彼の指が私の中に突っ込んできた。私はうめき声を抑えるために、急いで肘掛けを掴んだ。「このソファで潮を吹かせてやる」と彼は耳元で囁いた。
彼の指が私の中に入り込む感覚に、私は震え、ソファに釘付けになった。彼が体を内側に傾けると、私は少し足を開き、もう片方の手が私の後頭部を掴み、髪を引っ張った。
「私たち…」私はうめいた。「大変なことに…なる…わ」彼は私の中に指をもっと強く押し込み、「いいよ」と囁いた。
私が頭を後ろに倒すと、彼はどんどん激しく指を動かし、Gスポットを刺激しました。筋肉が収縮するのを感じ、気を紛らわせようとしましたが、もう遅すぎました。私はもう手を離してしまっていたのです。
パンティがびしょ濡れになり、私のアソコから愛液が噴き出しました。彼は指で愛液をなめ続け、愛液は内ももを伝い、お尻の下に溜まりました。私は彼の後頭部を掴み、ソファに愛液をぶちまけながら彼を抱き寄せました。
「あ、ソファー!」と思わず言ってみたけど、無駄だった。びしょ濡れだった。彼は急に立ち止まり、私の脚の間から濡れた手を抜き、指を一つ一つ丁寧に舐めた。
「さあ」彼は真剣すぎる顔で言った。「部屋に連れて行って、ビュッフェみたいに食べちゃうぞ。わかったか?」
飲み物は手つかずだったのに、酔った気分で座っていた。「はい、承知いたしました」
彼は私を助け起こし、私たちは二人ともソファの上の大きな濡れた部分を見下ろした。
「しまった」と私はくすくす笑った。
「お前は悪い子だったな」と彼は悪魔のように言った。「お前が散らかした様子を見てみろ。俺は2階でもっとひどい散らかし方をしなくちゃいけない」
彼は私の手を取り、ラウンジからエレベーターへと歩いた。中に入ると、彼は優しく私の唇にキスをし、両手でしっかりと頭とお尻を掴んでマッサージしてくれた。
「君に会いに来たのは、僕が今までにした最高の決断だったよ」と彼はささやいた。
私が返事をする前に、エレベーターのドアが開き、私たちは外に出て部屋のドアに向かいました。
彼は鍵を鍵穴に差し込み、ドアを開ける前に私を見た。「ところで、ビュッフェに行ったことはありますか?」
パート1を読む
執筆者
ナターシャ・イヴァノビッチ
ナターシャ・イヴァノヴィッチは、Kiiroo、LovePanky、Post Pravdaなどでの執筆で知られる、親密関係、デート、そして恋愛関係をテーマにしたライターです。TheLonelySerbでは短編小説を執筆・執筆しています。彼女は犯罪学で学士号を取得し、その後、調査心理学の修士号も取得しましたが、その後、真の情熱である執筆活動に専念することを決意しました。