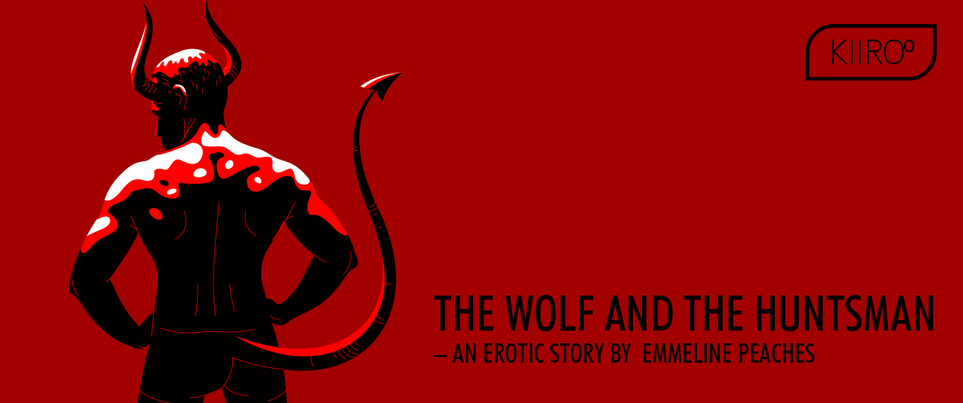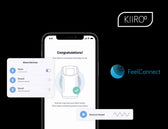「それで、今夜はシャンパンが出ると思いますか?」
「請求額を考えればそう願うしかない!」
「安心してください、皆さん。事前に確認しました。すべて含まれていて無料です」
「こんなにお得に買えたなんて信じられない!」
"私もです。"
「リンゴ投げコンテスト、絶対優勝するよ!」
ハンナは、更衣室のドア越しに友達が大笑いしているのを聞き、思わず顔を赤らめてしまった。どうしていつもあんなに強欲なんだろう?あんなにワイルドな自分は想像もできなかった。
「あの、皆さん、この更衣室には十代の若者もいるかもしれませんよ」と彼女は恐る恐る注意した。
「ああ、ハンナ、そんな堅物なこと言わないで!」メリッサは叱った。
「私は潔癖症じゃないの」ハンナは断言したが、彼女自身もそれを信じていなかった。彼女の赤みは増した。「ただ、何事にも時と場所があるって思うだけ」
「あぁ、赤面してる」ハンナは上の階から声が聞こえた。はっと見上げると、隣のブースから友達のターニャが覗いているのが見えた。他の友達もクスクス笑った。
「大丈夫かい、子羊ちゃん?」ターニャは申し訳なさそうに尋ねた。落ち着いた声は、ふさふさの黒い巻き毛に縁取られた柔らかな顔立ちとよく合っていた。
「うん」ハンナは嘘をつきながらぶつぶつ言った。
買い物を終えて、一行は仮装店から出発しました。
「いいかい…」メリッサはハンナの方を向いて、いたずらっぽい笑みを浮かべた。「あなたは、適切な場所では生意気な振る舞いができるって言うわよね。証明して。今夜、舞踏会に行くとき、下着を着けずにやってみろって言うのよ」
「え、何!?」ハンナは言葉に詰まった。友達たちの熱意あふれる顔を見て、自分の顔が再び赤く染まっていくのを感じた。メリッサはニヤリと笑った。自分には無理だと思った。ハンナにはそれがわかった。
ハンナは買い物袋の紐の持ち手を握りしめ、拳を少し強く握りしめながら、この挑戦に勇気が湧いてきたのを感じた。「わかった。いいわ!」と彼女は思わず言った。
メリッサの笑顔は消え、ショックを受けたような表情に変わっていた。他の友人たちは歓声を上げたが、ハンナはターニャの顔にかすかな不安の色が浮かんでいるのを感じ取ったと断言した。
ハンナも同じ気持ちだった。「どうしてあの衣装を買わなければならなかったの?」と嘆いた。
ハンナは片方の手で、驚くほど短いスカートの裾を引っ張り、もう片方の手で木べらを掴んだ。青いチェック柄の布地の下で、フリルのフリルが素肌に擦れ、陰部が風に吹かれて露わになっているのを感じた。
「あなたが私にこんなことをさせたなんて信じられない」ハンナはメリッサをたしなめた。
「無理やり? あら、いいえ、あなた。同意したんでしょう? それに、羊飼いだって、羊の群れを見せびらかすくらいなら、どうだっていいじゃない」メリッサはウィンクした。
「今夜はターニャは来ないの?」ハンナは話題を変えようと急いでそう口走った。
「いいえ、体調があまり良くないと言っていました」とキンバリーは答えた。「残念ですね」とメリッサは言った。
ハンナは安堵のため息をついた。今のところ、彼女はもう注目の的ではなかった。
会場に入ると、ハンナはすぐに、たくさんの体で満たされた部屋の暖かさに感謝した。下着なしで過ごすことがこんなにも楽だとは、今まで考えたこともなかった。露出した陰唇は脈打ち、クリトリスは痛んだ。
少し落ち着きを取り戻したハンナは、深呼吸をして周囲を見回し、畏敬の念に打たれた。メリッサが「舞踏会よ」と言ったのは、本気だった。巨大な天井画が天井を覆い、優しい頬をした天使や曲線美の天使の絵が飾られていた。金色のシャンデリアが部屋を照らし、鏡が周囲を囲んでいた。上から見ると、古い劇場のようなバルコニーが見え、奥の部分は赤いカーテンで隠されていた。ハンナは思わず「わあ」と声を漏らした。
彼女が振り返って友人たちを見てみると、彼らはすでにいなくなっていた。人混みの中に散り散りになり、恋に落ちた仮面の男たちに心を奪われていた。よくあることだ。
ハンナは群衆の中に見覚えのある顔がないかちらりと見たが、まず別の人物と視線を交わした。男だ。背が高く、がっしりとした体格で、紛れもなくハンサムだった。狼の形をした、本物の毛皮で作られたようなマスク越しでも、彼の鋭い視線は伝わってきた。瞳は氷のように青く、唇はまるで飽くなき食欲を物語るかのように、血色に満ちていた。
どれくらい見つめ合っていたのだろう?ハンナは思った。見つめ合うべき時間よりもずっと。一瞬、ハンナは自分の陰部が温かくなっているのをはっきりと意識した。湿っているのを感じた。彼女は視線を逸らし、メインのダンスエリアを横切った。
階段を上りながら、ハンナは廊下を振り返り、バスルームを探そうとしました。
「やりすぎよ」彼女は近くの壁に寄りかかりながら、うっかり外陰部を露出させながら、大きく息を吐いた。
「僕も人混みは苦手なんだ」廊下の端から男っぽい声が聞こえた。ハンナは不快な既視感に襲われ、飛び上がった。
それは彼でした。
「あ、えっと、そういうことじゃなくて。私…私…」
「下着も着けていない。気づいたよ」男は冷淡な様子で言った。「どうやら、かなり楽しい夜の予定を立てていたようだな」とニヤリと笑った。
「失礼ながら、いいえ」ハンナはきっぱりと言った。「だって、あなたが誰なのかも知らないんですから」
「もちろんだよ」彼は、まるで彼女の言葉をゲームのように笑い返した。「俺は大きな悪い狼で、羊飼いの女に目がないんだ」
「もう十分だ」と角の向こうから声が聞こえた。ハンナはすぐにそれが誰なのか分かった。ターニャが二人の前に姿を現したのだ。デニムのジーンズに赤いボタンダウンシャツ、そして偽物の斧を振り回す彼女は、まさに完璧なハンターのようだった。
「赤ずきんちゃんを助けに行くべきじゃないのか?」と狼は嘲りました。
「冗談は終わり。この斧は偽物かもしれないけど、それでも思いっきり振り回せると思う。さあ、友達から離れて。」ハンナの心臓が一拍飛び上がったが、どれほど激しく動いているかは彼女には分からなかった。
「ふん、いいよ」狼はハンナの方を向き、頭を下げた。「また今度ね」そう言うと、ターニャを睨みつけながら立ち去った。
彼が去ってからようやく、ハンナは胸が解放され、再び呼吸が楽になったのを感じた。体中がアドレナリンで満たされ、全身が静電気で満たされた。それは彼女が今まで感じたことのない、最も強烈な感覚だった。
ターニャは狼が去ったことを確認してから、ハンナの元へ駆け寄った。「ねえ」と息を吐き、安心させるように顔の横を撫でた。「大丈夫?」
ハンナは友人のダークブラウンの瞳を見つめ、頷いた。ターニャはいつものように優しく慰めてくれるように見えたが、ハンナは頬に当てられた彼女の手が震えているのを感じた。ターニャもハンナと同じ気持ちだと、ハンナは確信した。
「大丈夫よ」彼女はもごもごと言った。「ただ…信じられないくらい、男の人たちの神経が」
ターニャは頷き、安堵のため息を吐いてからくすくす笑った。「あなたのような可愛い子羊が、そんな狼どもとどうしてるの?」と冗談めかして言った。
しかし、ハンナが友人の言葉を聞いてなぜ欲望が湧き上がったのかは、よくわかっていなかった。
状況の緊迫感に駆られたハンナは、とろけるように身を乗り出し、ターニャのふっくらとした褐色の唇にキスをした。ハンナは大きな安堵を感じ、すぐにターニャの唇が自分の唇に優しく触れるのを感じた。陰唇に激しい快感がこみ上げてきた。
ターニャはハンナを情熱的な抱擁でキスへと引き寄せた。まるで長い間満たされずにいた欲求を満たすかのように。素早く力強い動きでハンナを持ち上げ、壁に押し付け、力強く素早く彼女の唇を探った。ハンナは喜びに息を呑み、一瞬体を後ろに反らせた。女性に対して、ましてや親友に対して、こんな気持ちになったことはなかった。これは一体何を意味するのだろうか?
ハンナが全てを理解する前に、ターニャが彼女をくるりと回して近くの暖炉の棚に支えた時、彼女は再び体が持ち上げられたように感じた。ハンナは幸福感と安堵感でくすくす笑った。何もかもが興奮を誘い、未知なる感覚の興奮に身を任せていた。
ターニャはハンナの脚を広げ、太ももにキスをした。柔らかな唇がハンナの肌を優しく撫でた。時折、程よいタイミングで軽く噛まれる。ハンナはくすくす笑いをこらえるために唇を噛んだ。
「この子羊でいいの?」ターニャは、ハンナの陰部に優しく触れながら、優しく見上げながら言った。ハンナはためらうことなく、熱心に頷いた。ターニャのニヤッとした返事に、彼女のクリトリスは切望で疼いた。
「それなら、シリコン斧を買っておいてよかった。」
ターニャはそう言うとハンナの陰部に近づき、繊細なキスを交わしてから、クリトリスを鼻で優しく撫で、少し圧力を加え始めた。ハンナは友人の触れ方に震え、その瞬間に身を委ねるように目を細めた。ターニャが温かい舌でハンナの陰唇をなぞり始めると、ハンナはハンナの豊かでウェーブのかかった髪が太ももを撫でるのを感じた。二つの感覚が完璧に溶け合い、ハンナはこの瞬間を終わらせたくなかった。
ハンナは友人に向かって腰を反らせ、ターニャのくすくす笑いが聞こえた。そして、シリコン製のハンドルの硬い縁が膣口をなぞるのを感じた。先端が彼女の愛液でしっかりと覆われると、ハンナはターニャがそれを差し込むのを感じ、力を入れながら押し込んだ。そのペニスは満ち足りていたが、今まで感じたことのない太さだった。ターニャがクリトリスを強く吸い始めると、ハンナは頭に血が上るのを感じた。圧倒された彼女は、ターニャの逞しい腕を掴み、赤いフランネルシャツを引っ張った。
斧に熱心に腰を突き入れると、ハンナは全身に圧力がこみ上げてくるのを感じ、そして激しい膣収縮が一気に始まった。これほど大きなものを体内に受け入れてオーガズムに達したことはなかった。彼女の陰部はターニャの温かい唾液でびしょ濡れになっていた。
ハンナはバルコニーから舞踏室を見下ろしながら、ターニャの胸に頭を預けた。「確かに、ここはくつろぐには最高の場所ね」とターニャは言った。「さあ、狼が忍び寄ってくるのを見てみようか」と、ニヤリと笑って軽快に冗談を言った。
「ええ…それについて…」ハンナは切り出した。「あの男のことは、パーティーの主催者に内緒で知らせた方がいいと思う。だって、もし他の誰かと何か企んでいたら大変だから。」
「いい考えね」ターニャは頷いた。「そういう人たちは、自分の行動が許されないものだと学ぶ必要があるわ。」
「…それと、あの、助けてくれてありがとう」ハンナは、今度は優しく顔を赤らめた。
「いつでもね」ターニャは小さく笑った。「ところで、メリッサの挑戦に成功したわね。よかったね。きっとメリッサはそれを見てびっくりしたでしょうね!」ターニャは気楽そうに言った。
「驚いた?ええ。『見る』ということについては……それは、あなたがそれでいいなら、あなたのために取っておこうと思うの」ハンナは不安そうに尋ねた。
驚いたことに、今度はターニャの頬が赤くなり、愛らしい笑みが顔に浮かんだ。「それ、欲しいわ、子羊ちゃん。すごく欲しいわ。」