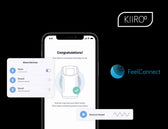クリスマスのデザート
クリスマスディナーにデートの相手がいなかった。男性を家に連れてきて両親に紹介したのは何年も前のことだった。別に大した問題ではないのだが、もうすぐ35歳になるし、母が言うには「もう若くない」のである。
今年のクリスマスは、みんなが実家に来ます。みんなって、本当にみんなです。叔父さん、叔母さん、祖父母、いとこたち、みんな泊まりに来ます。
それで、どうする?叔父や叔母に、私の情けない恋愛について愚痴を言われるのも、祖母に税金の計算をしてくれる会計士を紹介されるのも、聞きたくなかった。そこで、クリスマスデートの相手を雇うことにした。
ええ、何を考えているかは分かりますが、誰にとってもwin-winな関係でした。デートの相手が夕食に来て、おばあちゃんの隣で暖炉の前でエッグノッグを飲みながら笑い合い、そして楽しく帰って行く。何が問題になるっていうの?
グーグルで調べてみたら、俳優のポジションで男性を募集している会社を見つけました。かなり切羽詰まっていたのですが、その会社からケビンという俳優を推薦されました。2分後には、ケビンの写真と連絡先がメールで送られてきました。
ああ、彼って可愛い。本当に可愛い。ケビンは青い目にダークブロンド、そしてマジック・マイクがパンツを脱ぐような体つき。ちょっと私には釣り合わないかもしれないけど、彼のような男に振られるなんて、両親に数ヶ月黙っていたことの言い訳になる。彼にメッセージを送ってデートの約束をした。もう約束は決まっていた。
クリスマスディナーの時間が来て、みんなが私のデートの相手が来るのを待ちわびていました。
「彼の名前は何だったっけ?」と母が興味深そうに尋ねました。
「ケビンだよ、ママ。ケビンっていうの」七面鳥をつつきながら、私は答えた。「お母さんに会えてすごく興奮してるよ」
「ええ」と母はクスクス笑った。「彼に会えるのが楽しみよ! 男性が来るなんてずいぶん前だったわね。もしかしたら…あの…相手チームのバッティングをしているんじゃないかって、ちょっと思ってたのに。」
「そんなに簡単だったらいいのに」と呆れて言った。芽キャベツを掴んで夕食のテーブルに運んだその時、誰かがドアベルを鳴らした。まさに時間通りだった。
父に先に到着してしまうのではないかと怖くて、ドアまで走った。ドアを開けると、白いボタンダウンシャツとカーキ色のズボンを履いたケビンが立っていた。すごく美味しそうだけど、忘れないで。彼は雇われているんだから。何も起こらない。
私はすぐに我に返り、「こんにちは、ケビン。サラです」とどもりながら言いました。「えーと、皆さんは今ダイニングルームにいらっしゃいますので、お話をお願いします」
彼は私にウインクして言いました。「心配しないで、僕が大丈夫だよ。」
ケビンがダイニングルームに入ってくると、皆が静まり返った。「あれがケビン?」と叔母が驚いたように言った。何人かの笑い声が聞こえたが、私は冷静さを保とうとした。「ええ、はい、こちらがケビンです。ケビン、こちらが全員です」
家族が自己紹介をし、ケビンが全ての質問に答えてくれたおかげで、夕食はスムーズに進んだ。でも時折、ケビンの脚が私の脚に触れたり、肩越しに腕を回し頬にキスをしたりした。全部演技なんだから、真に受けないで。彼はあなたとセックスするんじゃない。あなたが彼に金を払ったんだから。
触れられるたびに、パンティはどんどん濡れてきた。この男、知らない人なのよ。サラ、落ち着いて。夕食の席で興奮しちゃダメよ。 「そう言ってあげたいんだけど」とケビンは腕で私の内腿を撫でながら言った。「ここに来てくれてありがとう。夕食は最高だったよ。やっとみんなに会えて本当に嬉しいよ」
ああ、もう、彼があと1分でもここにいたら、私、イっちゃう。夕食後、母は私たちをリビングに連れて行き、みんな七面鳥とグレービーソースで半分酔い気味に座らせた。
「誰かキッチンで何か欲しい人はいる?」ソファから立ち上がりながら尋ねた。皆、ろれつが回らない返事をしたので、私は「ない」と受け取った。「一緒に行くよ」とケビンが言い、私についてキッチンに入ってきた。
「えーっと、本当によくやってくれてありがとう」と、彼が私の方へ一歩近づいてきたので、私はそう言った。「すごく楽しいよ」と彼は答えた。顔は私のすぐそばで、息が肌に触れた。私は緊張してクスクス笑ってしまった。「夕食の間、私が君に触れるたびに、君が席で身をよじっているのが気になって仕方がなかったんだ」と彼は真剣な顔で言った。
彼の手がゆっくりと私の脈打つアソコを愛撫し、「大丈夫だった?」と尋ねました。驚きとショックで、私は彼の手を掴み、アソコに強く押し当てました。「ちょっと濡れすぎていたわ。」
彼は私をつかみ、キッチンカウンターの上に持ち上げた。「僕が手伝うよ」彼は私のパンティーを足首まで下ろし、濡れた染みを露わにした。そして私のドレスを持ち上げ、腰を下ろした。
彼の指が私の中に滑り込むにつれ、彼の口が少しずつ私の膣に近づいていくのが感じられた。うめき声を我慢しようと、私は素早くカウンターにつかまり、体を支えた。彼の舌が優しく私の唇を舐め、クリトリスへと向かってきた。「ああ、なんてこと」と私は囁いた。
リラックスしようとしたけれど、聞こえてくる音一つ一つに恐怖で体が震えた。ああ、誰かに見つかってしまわないといいのに。彼は立ち止まり、頭を上げて言った。「誰にも見つからないよ。リラックスして。」彼は私の脚の間に頭を沈め、唇にキスをし、クリトリスを吸い上げ始めた。
「私をイカせてあげるのよ」息を切らしながら、なんとかそう言おうとした。彼が私のアソコをどんどん激しく舐め、クリトリスが快感で膨らんでいくのを感じた。片手で彼の髪を掴み、彼の頭をアソコの奥深くまで押し込んだ。もっと激しく舐めて。そう、もっと、もっと、もっと激しく。
「イってる」と囁きながら、カウンターに手を叩きつけた。彼は私のアソコを舐め続け、愛液を飲み干した。少し間を置いて、彼は動きを緩め、優しくアソコを舐めた。そしてドレスから顔を出した。私は至福のあまり仰向けになり、「見て」と天井を指差した。「ヤドリギ!」
彼は口を拭きながら顔を上げて言った。「メリークリスマス」。私たちは一緒にくすくす笑い、彼は情熱的に私の唇にキスをした。私は彼の顔全体に自分の味を感じた。
リビングから母の声が聞こえた。「二人とも大丈夫?」
私はドレスを下ろして体を振り払い、「うん、ママ、私たちは大丈夫よ」と言いました。
執筆者
ナターシャ・イヴァノビッチ
ナターシャ・イヴァノヴィッチは、Kiiroo、LovePanky、Post Pravdaなどでの執筆で知られる、親密関係、デート、そして恋愛関係をテーマにしたライターです。TheLonelySerbでは短編小説を執筆・執筆しています。彼女は犯罪学で学士号を取得し、その後、調査心理学の修士号も取得しましたが、その後、真の情熱である執筆活動に専念することを決意しました。
ナターシャの作品をもっと見る
関連記事: