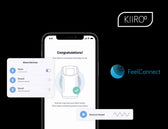遠距離恋愛の物語
彼は彼女の笑い声のしわがれた温かさが大好きだった。
時々、彼は瞬きをしながら、ほんの少しだけ長く目を閉じて、彼女の声の軽快さに浸りながら、すべてを吸収した。
「ああ、そんなに面白くなかったよ!」と彼は笑い返した。
「ねえ、『勃起』じゃなくて『選挙』って言ったでしょ、本当に面白いわ」と彼女は目から涙を拭いながら言った。
彼女の頬の輝きが、露わになった胸に映っていた。小さく張りのある胸の始まりの直前、ふっくらとした温かさが感じられた。彼のカメラは、 Kiirooプラットフォームの親密なフィルターを通して、そのすべてを完璧に捉えた。
彼らのような遠距離恋愛では、良好なインターネット接続と安全な通信手段は必須でした。ジョンはPearl2とOnyxを購入する際にこれらすべてを考慮していましたが、それがどれほど大きな違いをもたらすかは想像もしていませんでした。
人生は良かった。
彼は気にせず口を尖らせた。
「あら、かわいそうに」アビゲイルは偽りの同情の口調で言った。「もう全部忘れたいだけなの?」
彼は哀れそうに、ふざけて頷き、悲しみを大げさに表現しながらも、まだふくれっ面をしていた。それは彼のペニスと同じくらい…いや、完全にはそうではないが、しっかりとした演技だった。
「わかったわ」と彼女は認めた。「でも今回は話さないで。あなたはすぐに口ごもってしまうから。ただ…感じて」
彼はうなずき、期待しながら唾を飲み込んだ。
彼女の乳首は膨らんでいて、彼女もそれを楽しみにしていて、彼を迎える準備ができていることを彼は知っていた。
にっこり笑うアビゲイルは、 Kiiroo Pearl2 を自分の中に挿入し、ジョンが Onyx を自分のシャフトに差し込むのを待ちました。
それはとてもかさばる。アビゲイルは最初、最新作のビデオゲームみたいだと冗談を言った。二人とも気にしていなかった。
ジョンは、一緒に選んだオニキスのふかふかとした感触と濡れた感触を感じながら、オニキスに欠点を一つも見つけられなかった。
アビゲイルは「準備はいい?」と軽く微笑んだ。ジョンも同じように頷いた。彼女はゆっくりと、そして愛情を込めて、パール2を動かし始めた。
オニキスも同じように動き、アビゲイルの動きに合わせてジョンのペニスを刺激した。何かに興奮すると、彼は決してその熱意を抑えられないタイプだった。そしてすぐに、深いうめき声と共に喉の奥が震えるのを感じた。そのうめき声は冠状隆起への擦れとよく調和し、速度が増す様子から、アビゲイルが喜んでいることがわかった。
ジョンは気づかぬうちに目を閉じていた。アビゲイルもそうだった。二人は時宜を得た瞬間に見つめ合うのが大好きだったが、それはほとんど必要ではなかった。二人の喜びの根底にさえなかった。むしろ、二人を結びつけていたのは、他のあらゆるものだった。
ジョンはアビゲイルの女らしい歓喜の呻き声と、息がゆっくりと浅くなるのが聞こえた。周囲から軋む音やキーキーという音が聞こえ、それが椅子の継ぎ目の音だとジョンは分かった。彼女が腰を前後に反らせ、 パール2に熱心に突き上げ始めていることを意味しているのだ。
ますます温かくなる喜びとともに、彼は自分のペニスを誘うのを感じた。オニキスの感触は二人にとって重要だった。二人がそれを選んだのは、まるで自分のもののように感じられるからだった。彼女の膣の締まり具合と、彼女の体を実際に触れるたびに彼がいつも感じる感覚の過負荷を、まるで真に反映しているかのようだった。それは完璧で、ジョンはいつもアビゲイルにそれを伝えることができた。
このとき、彼は片手で椅子を掴んだ。革のような表面が独特の深い音を立て、アビゲイルがふざけてくすくす笑うのが聞こえた。彼女はそれが何を意味するのか分かっていた。
ジョンは深呼吸をしながら、突き上げる動きが強くなるにつれて二人のうめき声がより一層調和していくのを感じ取った。
ジョンのペニスは十分な突きを受けていたにもかかわらず、反撃せずにはいられない時もあった。まるでアビゲイルの腰を掴むかのようにオニキスの脇を掴み、彼女が何度も求めていた力と深さで彼女を犯した。
ジョンの心の中では、まさにこれが起こっている。アビゲイルも同じことを経験しているだろうと想像した。彼にとってはそれで十分だった。アビゲイルのうめき声は、至上の喜びの甲高い叫び声へと変わり始め、ジョンは固く締まったペニスに溢れ出る、脈打つような高揚感の波を必死に抑えようとした。
彼女が絶頂に達した時(彼はそれをよく知っていた)、彼もまた、汗ばんだ絶頂の喜びを、深く、動物的なうなり声とともに受け入れた。二人の絶頂のハーモニーは、初めて一緒になった時にはジョンが予想していなかったものだったが、今では二人だけの特別な求愛ダンスのように感じられる。必ずしも必要というわけではないが、それでもそれが起こった時は嬉しく感じられた。
ジョンはオニキスを柔らかくなったペニスから抜き、先端から優しく精液を垂らした。アビゲイルは愛おしそうに微笑んだ。彼女はその光景をとても気に入っており、ジョンもそれを知っていた。
「それで、気分は良くなったの、私のふくれっ面の小娘?」アビゲイルはからかった。
「あら、静かにして」彼は愛情たっぷりの笑みで言い返した。その時、二人の笑顔がどんなに暗い日も明るくしてくれるような気がした。
「そうですね、あなたの声を聞くのは大好きですが、勉強しなければならないこともあります」とアビゲイルは言いました。
「わかった、わかった、頑張れよマスターズ君」と彼は責め立てた。
「まだ言わないで!不吉なことが起きるよ!」
「ああ、そうだった。ごめん。忘れてた。頑張ってね、バターカップ」
「さようなら、私のダンディな紳士」。
そう言って彼らはログアウトし、ジョンは最後にもう一度目を閉じて、アビゲイルの笑い声を思い出した。
著者: