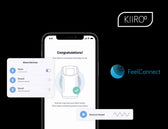テスを失ったことは辛かった。でも、それ以上に辛かった。耐えられなかった。あんなに優しくて、元気いっぱいだったのに…何も残っていなかった。彼女は心の底から打ちのめされ、私は自分が悪いと感じていた。あんな…あの…あえて女性と呼ぶべきだろうか?何か別の言葉で呼ぶべきだろうか?私たちを引き裂いたあの悪魔のような存在に、決して手を出すべきではなかった。
ジャスティーヌ、ジュリエット…彼女が何と名乗っていたにせよ、彼女があんなことをしたのは、私の弱さ、私の欲望、そして私の卑劣な性格のなさのせいだった。私はそのことを深く掘り下げて考えた時――私は何度もそうしていた――この忌々しい大惨事の全ては私のせいだと悟った。
テスと人生をやり直そうとしたが、無駄だった。テスはもうテスではなくなっていた。おまけに、彼女はもう私を必要としていなかった。テスの人生は崩壊し、私の人生も同様に崩壊し始めた。まあ、テスのように精神が崩壊したわけではないが、そうなっていたとしても驚きはしなかっただろう。
出版社との契約が破談になった…もう出版に値する作品は何も書けなかった。そして、あの悪魔のような女は姿を消し、私の物語に関わった全ての仕事も忘れ去られた。
私はニューヨークの街を昼夜問わずさまよい始めた。目的もなく、希望もなく。昼間は最悪だった。少なくとも夜には魅力があった。音楽、出かける人々、夜のエネルギー。私はますます、その夜のエネルギーを体験するために生きるようになっていった。
ぐいぐい飲んだ。ごまかす意味なんてない…ボトルが私を虜にした…そしてその虜は、お互い様だった。私も虜になり、私も虜になった。意識を失うほど飲むことで、なんとか正気を保っていた。
そしてある日、2月14日のことでした…空気は愛に満ち溢れていて、私はそれが本当に嫌でした。ブロードウェイを歩きながら、地球が自転を止めて70年代後半に放り出されればいいのにと願っていました。ああ、あの卑猥な行為が全盛だった時代にそこにいられたら、どんなに素晴らしいことだっただろう。
失恋した男なら、街角のどこにでも救いの手はあったはずだ。私は自分の歪んだノスタルジアに笑ってしまった。私はそこに行ったことはなく、ただ全くロマンチックではないことをロマンチックに思い描いていただけなのだ。この日をうまく乗り越えられなかったせいで、さらに笑ってしまった。あの甘ったるいバレンタインの戯言に対する皮肉な解毒剤のようなものが、私の中に生まれていたのだろうか?
そして、このジョークを極限まで推し進める最良の方法は、バードランドに行くことだと気づいた。きっと「マイ・ファニー・ヴァレンタインは演奏されるだろう」と確信していた。まさに究極のアンチ・バレンタイン・ソングじゃないか? 少なくとも、チェット・ベイカーのヘロインまみれの演奏を考えると…そう、まさにバードランドに行くべき時だった!
それですぐにバーに座ってラフロイグを飲んでいた。確かにカップルが多かった。ちょっとうんざりしたけど、世の中ってうんざりするほど気持ち悪いものじゃない?
「ファッキュー、人生」と私はつぶやき、一口飲んで、一口飲んで、注文して、一口飲んで、注文した...そしてチェット・ベイカー本人がステージに上がるのを見たので、私は本当に気が狂ってしまったに違いないと気づいた。
「何だって?!」スコッチを喉に詰まらせそうになり、咳き込んだ。どうやらすぐ後ろに立っていたらしいウォールストリートのいかがわしい奴が、笑いながら耳元で叫んだ。「おい、あれはチェットじゃない、違う。死んでるぞ」
「あいつが死んでるのはわかってるよ、一体何を耳元で叫んでるんだ?」と私は言った。
「君の姿を見たよ...彼が登場したとき、君がウイスキーを飲み込んで窒息しそうになったのを見たよ、ハハハ!」と彼は答えた。
「そうか...そうだったんだ。」
「ああ、まあ、問題はそこなんだよ。あそこにいるのはイーサン・ホークだよ。役になりきってるんだ。」
「彼は役になりきっている」って、一体どういう意味ですか?
「彼はチェットの伝記映画を撮ってるんだ。今夜は、自分の役にどれだけ熱中しているかを見せつけるためにパフォーマンスするんだ。」
「よし、それはかなりクールだ」
「はい、確かに彼に似ていますね。」
「ああ、まあ、彼はあまりにも美しすぎるし...無傷すぎるし...明らかにイーサン・ホークだと分かったよ。」
「そうだな、そうだな...なあ、セリフを言ってみないか?」
「何、ここ?」
「いや、もちろん男装だよ、このバカ。」
'いいね'
私たちが同じ個室にいたとき、私はその新しい知り合いにこう言いました。「いいかい、僕は女を連れてこなければここから出られないよ。」
彼は瞳孔を広げ、白い鼻を浮かべて私を見上げた。まるでマニーが妹と寝た後のトニーみたいだった。私は笑いをこらえきれずに済ませようと必死だった。
「あなたって本当にバカみたいよ」私は泣きながら笑いながら言った。
「馬鹿げたことを言うなよ」と彼は答え、笑い始めた。
笑いが止んだ後、私は言いました。「女性と一緒に出発すると言ったからといって、私が馬鹿げていると思われるでしょうか?」
「そうだよ」と彼は言った。「バレンタインデーには俺たちみたいな男に勝ち目はないんだよ」
「自分のことばかり話してたら、私のことなんて知らないでしょ」私は咳払いした。
顔を洗ってバーに戻った。戻ると、ちょうどバンドが「マイ・ファニー・ヴァレンタインの」を演奏し始めたところだった。美しい演奏にすっかり魅了されていた(チェットもきっと誇りに思うだろう!)と、真っ白なドレスを着た長い黒髪の女性を見つけた。どうやら彼女は一人で、ステージに近いバーのスツールに座っていた。私は新しい知り合いに向かって頷き、「さあ、私の番だ、ジャンキー」と言った。
彼は皮肉っぽく笑い、まるで空想上のハエを捕まえるかのように手を振った。
私はその女性の方を向いて言いました。「ねえ、チャーリー・パーカーは気に入ってる?」
「チェット・ベイカーのことよ!」と彼女は叫んだ。
「ああ、すみません、混乱してしまいました。」
「きっとそうだろうね。でもね、みんなそうじゃない?」
私は彼女の暗い茶色の目をじっと見つめ、見たものに満足しました。
「君が好きだよ、君はかっこいいよ」と私は言った。
「あなたもそうだと思うわ。ちょっとハイになってるだけでしょ?」
「それがどうしたの?」
「何でもない…私はアナスタシアです。」
「私はバジリオです。」
「わかりました、バジリオさん。この会話を個人的に続けたいなら、200ドルかかりますよ。」
私は笑った。皮肉でも何でもなかった。昔の悪徳をロマンチックに描いて、神々を愚弄してしまったことを自覚していた。タイムズスクエア近辺で売春婦に憧れていたのなら、ここにいる。これが本物だ。35歳なのに、一度も金を払ってセックスをしたことがないことに気づいた。もし初めての時があるとしたら、今がまさにその時だ。
「よし、アナスタシア、行くぞ」とウインクして言った。左腕を彼女の右腕に通し、そっと外に出した。通りすがりに、ウォール街で知り合ったばかりのアナスタシアの肩を軽く叩き、「そう言ったでしょ」と耳元で囁いた。
「私はあなたに祝福を与えます」と彼は言った。
タクシーでグリニッチ・ビレッジへ行きました。彼女のアパートがあったんです。途中、角の店でビールを何杯か買いました。「彼女と同棲しているの。二人きりで過ごしたいなら、彼女はサウナに行ってもいいわよ」
「わかりました、大丈夫ですよ。」
「ああ、でもその分は彼女の分を払わないといけないよ。」
「何だって?ここで俺を徹底的に脅迫するつもりか?」
「まあ、この方が便利だからね」と彼女は紛れもないロシア訛りで話した。
「わかりました。彼女を移動させましょう。」
アナスタシアは友達に電話をかけ、ロシア語で活発な会話を交わした。
「大丈夫ですよ」と彼女は言った。「運転手さん、着きましたよ」
アパートに着いて車を停めると、怒ったような表情をした若い金髪の女性が出て行くのが見えた。アナスタシアは私を簡素ながらもなかなか魅力的なアパートへと案内してくれた。一晩中飲み続けた酒のせいですっかり麻痺していたにもかかわらず、私はかなり緊張していた。アナスタシアには、威圧的なまでに高慢で、まるで王族のような雰囲気があった。
彼女は、私が最初に思っていた以上に美しいことにも気づいた。私たちは彼女のリビングルームにある大きな白いソファに座った。彼女に色々と聞きたかった…この女性について本当に興味があったが、それはすべきではないと悟った…遠回しに話すだけだし、彼女はそんなことを尊重するはずがない。だから、私は彼女の瞳を深く見つめ、キスをした。私たちは何分もキスを続けた…舌先を彼女の舌に絡ませるのが大好きだった。
「よかったわ」と彼女は言った。「あなたが本当に男なのか気になっていただけよ」
「もちろんだよ」
「そう願っています。この国では何が起こるか分かりませんから。」
私は笑いながら、さらに情熱的に彼女にキスをした。キスが終わると、私は尋ねた。
'どこの出身ですか?'
「ロシアから」
「それは分かりました、でも、どの都市ですか?」
「イルクーツク」
「シベリアの真ん中。すごい。地球上で最もエキゾチックな場所の一つだね。」
「それはただの都市です。」
「え、本当?孤立してたんじゃないの?あそこで育つのは変だったでしょうね。」
「そうだと思う。もう一度キスして。」
「その通りだ…」私は再び彼女にキスをし、ドレスを脱がせ始めた。ブラジャーをいじり続ける間もなく、彼女はすぐにソファの私の隣に来て、下着だけを露わにしていた。彼女は私の服を脱がせ、私は彼女の脚からパンティーを引き下ろした。
数ヶ月ぶりに再び女性と交われたからというだけでなく、アナスタシアという、このスリリングでエキゾチックで、最高にエロティックな存在と交われたからこそ、私は途方もなく興奮した。コンドームを装着し、彼女の中に挿入した。まるで何度も経験してきたかのように、まるで互いのために生まれてきたかのように、とても自然な感覚だった… ワイルドな行為だった。何の束縛も感じず、絶頂を迎えた後もすぐにまたコンドームを装着し、彼女の中に挿入した。
「あなたは素晴らしい、本当に感動的だ」私は彼女の隣に横たわり、息を切らしながら言った。
「私の中に戻ってきて」と彼女は言った。「もう一度あなたに会いたいの。」
私が別のコンドームをいじり始めたとき、彼女は言いました。「やめて。私はコンドームなしのほうが好きなの。」
かなり衝撃的な言葉だとは分かっていたが、もう気にしなかった。だから従った。無防備に彼女の中に入って…そして、それは衝撃的な感覚だった。彼女の尻を掴んで持ち上げ、部屋の中を歩きながら彼女を犯した。まるで踊っているかのように、彼女は私に密着していた…とても親密なダンスを踊っていた。私たちは再び絶頂を迎えた…同時に、私が絶頂を迎えると同時に、彼女が震えるのを感じた。私たちは隣り合って横になり、息を整えた。それからビールを飲んだ。
「あなたのセックスの仕方が好きなの」と彼女は言った。
私は笑って答えました。「お褒めの言葉しか返せません。」
「できるかもしれないよ」
「たぶんそうすべきだろう...」
私は彼女の上に飛び乗って、またセックスをしました。それは激しく、そして救いのようでした。彼女の陰唇が私のペニスを飲み込むのを見ていると、まるで私の中で深く壊れた何かが修復されるようでした。私はそれを取り出し、彼女の腹中に噴射しました。彼女はさらに激しく喘ぎ、そしてまた私に飛びかかりました。
5回目が終わった後、私たちはキッチンに移動しました。キッチンのテーブルに座って、またビールを飲みました。
「あなたが好きよ。あなたは男らしくセックスするわ」と彼女は言った。
「本物の女性とやってくれたら、たまらないよ」と私は言った。
「この国では自分が望むものを手に入れるのが難しいと感じることが多い」と彼女はため息をついた。
「それではなぜここにいるのですか?」
「お金のためです。」
「それで、これも、このすべても、これもまたお金だけなのですか?」と私は言いました。
「最初はそうでした。でも今は特別なんです」と彼女は答えた。
私は彼女を見つめ、彼女の驚異的な体に見惚れていた。彼女は私をじっと見つめていた…私たちは気まずい沈黙に陥りそうになったが、彼女がそれを阻止してくれたことには本当に感激した。彼女は私の右腕を取り、膝をつくように促し、同時に私の前で膝をつき、お尻を私のペニスに押し付けたのだ。気まずい沈黙を阻止する、これ以上の方法は見たことがなかった。私が絶頂を迎えた時、赤い星、黄色い月、そして緑のクローバーが見えた。息を整えて、私は言った。「セックスでオリンピックの金メダルをもらうのは私たちだわ、ベイビー」
「いいえ」と彼女は答えた。
'なぜだめですか?'
「君は、その栄誉に値する。一生懸命頑張ったんだから。」
私は笑ってため息をついた。「今日はまさにヴァレンティノの日だ…ありがとう、アナスタシア。本当に感謝しているわ。あなたは私の命を救ってくれたのよ。」
最高に最高なバレンタインデーだった。彼女には二度と会わなかったけど、奇妙に聞こえるかもしれないけど、そのせいでバレンタインデーはより美しくなった。
著者
バジリオ・ヴァレンティーノ