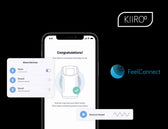ポリアナ著
数週間前…
私は満足感を感じながら、満足そうに微笑んでいます。
「認めてもいいだろう、このラウンドは100%勝った」
「分かってるよ、私のプレゼントはつまらないものなんだ」
「私のリストに載っているもののうち、一つでもダメなものはないでしょう」
「何のリストですか?」
「うーん…」
あの会話の後、ふと思った。服や宝石は気にしない。彼は物のサイズなんて気にしないタイプだ。残るのはオタク、テクノロジー…そしてセックス。おもちゃの趣味は抜群で、これまでの努力が…素敵な思い出を生んでいる。
アナルプレイは私にとって決して好ましいものではなかったため、普段は避けていました。彼は私の考えを変えてくれると約束してくれたものの、私は控えめに言っても懐疑的でした。誕生日の前夜(いつだったか覚えていませんが)、玄関で彼が私にキスをしようと身を乗り出してきた時、彼の匂いを嗅いだのを覚えています。
それはいつも同じだった。新鮮でありながら深く、威圧的でありながら安心感を与えてくれる。彼は安全と保護の香りを漂わせ、いつも私を安心させながら、どこか奥底で興奮を掻き立てる。
最後の箱を開ける私を見守る彼の視線が、肌を焼き尽くすのを感じたのを覚えています。頬に赤みがさし、さらに熱を帯びました。ああ、あの箱はキラキラと輝いていて、とても綺麗だったけれど、もっともっと大きなものを期待させてくれた。
二人で一緒にシャワーを浴びた時のことを思い出す。ゆっくりと交互に体を拭い合う親密な時間。その後のマッサージ。彼は私の体の隅々まで潤いを与え、オイルを筋肉に浸透させてくれた。まるで瞑想のような静けさが私の中に生まれた。
彼が優しく、たっぷりと、必要な箇所に潤滑剤を塗ってくれたのを覚えています。彼のキス、抱擁、そして愛撫は、私が自分でも感じることができるとは思っていなかった欲望を掻き立てました。
'大丈夫ですか?'
「以上です、ありがとうございます」
その一時停止の間、私の呼吸は速くて息苦しい音を立てていた。
'準備はできたか?'
「はい。はい、そうだと思います。」
そこに少し圧迫感を感じ、小さな欲求の呻き声が唇から漏れた。彼の呼吸が少し速くなり、かすかな興奮の表情が耳元でささやき、身震いがした。私は彼のために少しだけ開いた。
彼はゆっくりと、ミリ単位ずつ、細心の注意と忍耐をもって、私がこれまで逃していたものをほんの少しだけ味わわせてくれた。それから間もなく、私はすっかり虜になってしまった。
あれを包むのはきっと大変だっただろう。形は明らかだったが、それでも剥がされた瞬間に息を呑んだ。それに、彼に足首を縛り付けさせれば、動きが本当に制限される。
切実に喘ぎ、まるで懇願するように、私は彼に見つめられながら裸で横たわっていた。開いた窓から差し込む月と星の光に肌は輝き、乳首がそれに気づくほどだった。そう、私はあの時、彼の温もり、彼の体、彼の長く太いペニスを懇願したのだ。覆い、満たし、そして完成させることが欲しかった。いや、必要だった。
'お願いします?'
彼は私たちの距離を縮め、バーを掴んで軽く引っ張った。脚の緊張が高まり、背中が反り返り、寒さとは無縁の心地よい震えが全身を駆け巡った。彼の空いている手が伸びてきて、乳首の周りを円を描くように撫でた。彼の肌は私の肌と比べてとても温かく、触れた感触は胸に焼けるような跡を残した。
彼は私の真上に体を構えた。手首を頭の後ろで縛っていた。彼が甘く熱い唇を下げて指を置いた瞬間、彼の頭に手を滑らせたいという衝動に腕の筋肉が張り詰めた。
彼はいつも私の体と反応をじっと観察していた。胸への愛撫から少し離れると、彼は私の様子を読み取った。私たちの視線が合った。私の体に何を見ても、彼は気に入った。私がまさに彼の望む場所にいることに満足したのだ。自分の仕事ぶりに満足した彼は、ついに私の懇願に応えてくれた。
その後に続いた甘美な忘却の詳細はぼんやりとしているが、衝撃的なセックスが文字通り私の心を完全にクリアにしてくれた…
今夜…クリスマスイブ
彼が鍵をドアに差し込む音が聞こえ、鳥肌が立った。鍵を落とす音と、何かがもつれるような音、そして呟くような悪態が聞こえた。彼の足音が止まる。もしかしたら…
「何かお手伝いしましょうか?あら、すごい!」
'ねえ、あなた。'
彼は首を横に伸ばし、腕の中の巨大な箱の隙間から床を見ようとしていた。私は鍵を取りに行き、彼に道が開けていることを保証した後、軽くキスをしようと中に入った。彼が通れるように脇に寄ってから、ドアを閉めて鍵をかけた。箱の中には一体何が入っているのだろうと、頭の中はぐるぐると回っていた。
マットな黒の包装紙に、幅広で光沢のある紫のリボンが添えられていて、クリスマスの飾り付けにぴったりマッチしています。彼はそれをリビングの床の真ん中に置いてくれました。あまりにも大きいので、通り過ぎるには振り返らなければなりません。彼が得意げに立っている横に立ち止まり、私は感激で胸がいっぱいになりました。
「それで?開けて。」
私は、彼の言葉の命令に抗いながら、自分自身を思い出し、箱の前で小さく見えてしまった、丁寧に包まれた彼の贈り物の入った大きなギフトバッグを提示した。
「あなたが先です」
ぶつぶつ言った。急に、人目を気にして、少し不安になった。
「気に入っていただけると嬉しいです。」
「そうするつもりです。でも、どうしても言い張らないといけないんです。」
「ああ、わかりました」
頬が赤く染まっている。リラックスさせながらも、同時に緊張感を保って、まるで活き活きとした感覚にさせる彼の才能には、いつも驚かされる。リボンは何か滑りやすい素材でできているので、少し苦労する。ギフトラッピング用の素材を袋に詰めて保存してあるので、これを使うとさらにいいだろう。
紙はうまくいきませんでした。あまりにもしっかりと固定されているので、将来使うために取っておくことはすぐに諦めました。紙の下には、白い蓋付きの簡素な箱がありました。私は不思議そうに彼を見上げ、彼は頷きました。「続きを」。
蓋を外すと、床一面に千切れた紙が散らばっているので、彼がそれを受け取りました。ソファに折りたたんで置いてあったリボンも彼が取り出したのに気づきました。私がラッピングが好きなのを覚えていてくれたんですね、可愛い。
箱の中には、ほんのりと香りのするティッシュペーパーの山に包まれ、個包装された小さな小包が4つ入っています。それぞれラベルと番号が付けられています。
- 口のマーク - キルシュに浸したチェリーの瓶と本物のトルコ菓子、うーん
- 耳にマークが付いたスマートスピーカーとプレイリストのバーコード、なんて思いやりなんだ
- 目が刻まれた、柔らかいサテンの紫色の目隠し、興味深い
- 鼻に印がついた、私が長い間欲しがっていた香水の瓶。官能的でスモーキーなバラの香りが溢れている
きっとここにあるはずの最後の贈り物を探し回ったが、何もなかった。困惑して顔を上げる。
「ありがとう。これは素晴らしい。快楽主義者の夢であり、とてもよく考えられている。でも、5つ目もあるべきではないでしょうか?」
「そう思うでしょう…」
今、またリボンに気づいた。いつの間にか彼はリボンを再び手に取っていた。リボンの上のギフトタグには女性の体の輪郭が描かれている。以前は何も考えていなかった。
'おお…'
彼は指を曲げて私を招き寄せる。感謝の気持ちを込めてキスをすると、彼は私の服を脱がせ始める。私は彼にそうさせて、これが欲しい。彼はゆっくりと、慎重に服を脱ぎ、紫のリボンで私を縛り上げる。彼が目隠しに手を伸ばすのが見える。
静かに頷くと、辺りは暗転し、私の体は彼の気遣いに反応した。彼は優しく私を抱き上げ、部屋へ連れて行き、ベッドに寝かせた。
一瞬の沈黙。感覚が研ぎ澄まされ、私は彼を探す。すると音楽が始まる。ベッドの上で、彼の重みが私と共に感じられる。彼の口の中でチェリーの味がし、次に粉のような甘美な香りが舌の上へと広がる。バラの香りが漂い、私の心は真っ白になる。五感と彼への欲望だけが、ただ一つだけ。
'私はあなたが欲しいです。'
'知っている。'
著者
40歳。現在、パンセクシュアル、サピオセクシュアル、デミセクシュアル、そして少し変態でポリアモリーを自認するPolyAna Saysのアナは、人生の喜びを謳歌する、ハッピーなヒッピー快楽主義者です。セックスポジティブと自己愛が彼女のこだわりです!普段はフリーランスとして働き、シングルマザーとしても活躍しています。Instagramで@anaeidherselfをフォローしてください。