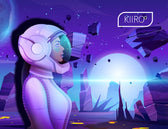パート5
「もう、卑劣なことはたくさんだ!」トムは叫んだ。
「そうだな」とバーテンダーは付け加えた。「あんなことを続けたら、トムがショットグラスを一気に開けるより早くここから出て行かれるぞ」
「みんな」と私は言った。「これは物語の一部なんだ。全体にとって極めて重要なんだ。詳細を全て知らずに、一体何が起こったのか理解できるわけがない。性的な詳細は特に重要だ」
「よし」とバーテンダーは言った。「これが最後のチャンスだ。お前は本当にイカれた野郎だ。話は十分面白いが、この店をポルノみたいな懺悔室にするのは勘弁してくれ」
私は深くため息をついて言った。「クソったれ、俺はただこのクソみたいなことを伝えようとしているだけなんだ。ティッパー・ゴアの再来みたいに俺を検閲するなよ。ジャック・ドーシーみたいなクソ野郎」
「わかった、もう終わりだ!」バーテンダーは叫んだ。「ここから出て行け、お前の態度にはもううんざりだ!」
「私ももううんざりよ、この堅苦しくて気難しい野郎!」と私は叫び返した。20ドル札を2枚バーに投げ捨てて店を出た。驚いたことに、トムが立ち上がって私についてきた。
私が自転車の鍵を開けようとしていたとき、彼は私に近づいてきて「やあ、ジョン」と言った。
'何?!'
「ジョン、バーテンダーのハンクに振り回されるなよ。彼はそういう奴なんだから」
「じゃあ、彼とファックしてよ」
「ああ、ああ…おいおい、お前が色々と酷い目に遭ってきたのは分かってる。話したいんだろう…分かるよ。ゲッコーで一杯おごってやろうぜ」
ゲッコーは、たまたま角を曲がったところにあったバーで、聞いたこともなかった。広々とした、金属的な雰囲気で…まるで石油タンカーの中みたいだった。アルコホイン蒸留所とは対照的に、ここはかなり混んでいた。少なくとも50人から60人はいただろう。ラムシュタインの実験的な時代の、よりエレクトロニックな曲が流れていた。
トムはバーで飲み物を2杯注文し、私たちは電気メッキされた金属製の背の高いバースツール2脚に座りました。
「あなたの左目は私を不安にさせる。なぜ右目のように私を見てくれないの?」私の新しい知り合いは大音量の音楽にかき消されて叫んだ。
「実は、まさにその話をしようと思っていたんです」と私は答えた。「その理由は、物語の一部なんです。ご存知の通り、私の資金は個人投資史上最悪の詐欺の一つに巻き込まれていたんです。2018年1月の最初の2週間、私のポートフォリオの価値は急落し始めました。それでもユーチューバーたちは、健全な下落に過ぎないと断言して視聴者を安心させ続けました。「安値で買え!」と彼らは言い続けました。もちろん、私は彼らを信じようと必死でした…Bitconnectはポンジスキームだという噂はますます広まりました。そして運命の日、1月16日が訪れました。Bitconnectはアメリカ当局によって閉鎖されたのです。」
「君は本当にひどい目に遭ったね。」
「ええ、ええ…そうでした。私のポートフォリオは壊滅状態でした。下落は奈落の底と化していました。」
「それで、カルダノの人たちはどうですか?」
「ロベルト・カルダーノのところへ何も持たずに帰って、何が起こったのかを話すしかなかった。彼は多くを語らなかった。もっと語ってほしかった。彼の顔、いや、全身から滲み出る冷たい怒りは、今でも悪夢にうなされるほどだ。」
「彼は君の顔をひどく殴って、左目を壊したのか?」とトムは言った。
「いや、全然。彼は私に触れてない。でも、彼のしたことは、彼の手下にボコボコにされたのと大差ない。レストランにいた従兄弟二人に、一緒に来るように命じた。『君のあの恋人を訪ねるんだ』とロベルトは言った。『この問題を解決するのを手伝ってくれるよう、丁寧にお願いするんだ』」
「でも、でも」私はどもりながら言いました。「彼女はそんなこと何も知らないんです!」
「もちろんそうじゃない。でも今はそうしなくちゃいけないんだ。」
胸が張り裂けそうなほど重く、私は立ち上がり、外に停めてあった大きな黒いメルセデスに案内されました。ヒルダのアパートへと向かいました…」
「もう、畜生だ」とトムは言った。
「ひどい状況でした…怒鳴り声や罵声、泣き声がひっきりなしに聞こえました。ヒルダに全てを説明しようとしましたが、どうしたらいいのでしょう?彼女は激怒していました。結局、その日のうちにロベルトに2万ドルを支払ってしまいました。その後、彼女は私を追い出しました。二度と口をきくことはありませんでした。」
「思ったよりはましだったな」とトムはうめいた。「でも、目はどうしたんだ?」
アメリカに帰ってからもエイダとは連絡を取り合っていました。もちろん、彼女も経済的に破綻していました。この苦難を分かち合えたことで、ある種の満足感がありました。ウェブカメラでのセックスも続けました。それでもまだ楽しかったのですが、日々の心境は絶望に満ちていました。罪悪感と羞恥心が渦巻く、毒のような気分でした。事態がさらに悪化しようとしていたとは、知る由もありませんでした。とてつもなく、ひどく悪化する…
エイダは宇宙飛行士になるという夢を諦めざるを得ませんでした。勉強も諦めざるを得ず、家族は彼女がお金を浪費したことをひどく非難しました。すべてがめちゃくちゃになっていました…私は彼女を助けたい、そして彼女に会いたいと思いました。」
「君は彼女とセックスしたかったんだね。」
「それもね。それで、ある日、思い切って彼女をアメリカに招待したの」
「デトロイトへ?」
「いや、もし彼女が宇宙飛行士になれなかったとしても、少なくとも宇宙旅行を垣間見ることはできると思ったんです。それで、フロリダでしばらく一緒に過ごして、ケープカナベラルを訪れようと提案したんです。」
「それはそんなに悪い考えじゃなかったよね?」
「当時は完璧なアイデアだと思ったんです。エイダも気に入ってくれて、驚いたことに手頃な航空券を見つけて来てくれたんです。マイアミで会ったんです。いやぁ、二人ともすごく緊張しました。いわゆる生で会うなんて、本当に不思議な感覚でしたよ」
「汚い野郎」
「ハハハ、そうよ。彼女は魅力的だったわ、本当に魅力的だった。そして数時間後には、実際に会ったのよ」

「みすぼらしくて安っぽいモーテルの部屋で?」
「いや、いとこのジミーのビーチサイドのコンドミニアムに泊まればいいんだ。スピードボートも貸してくれたんだ。だからお金はなかったけど、それでも贅沢な暮らしはできた。数日間は本当に最高だったよ」
「それからどうしたの?」
「ああ、クソッ、クソッ… ドン・ジョンソンみたいなノリノリだったんだ、分かるだろ? ジミーのスピードボートで波間をクルージングして、エイダが隣にいて。バイクでレースして、彼女に腕を回されて。俺は飛んでるみたいだった。そして、俺はしくじったんだ、本当にしくじったんだ。」
'あなたは何をしましたか?'
「ついにケープカナベラルを訪れるという、まさにその大事な日、私は夢中になってしまい、まるで自分が神様になったような気分でした。エイダを背中にしっかりと抱きしめ、大きなホンダで悪魔のように猛スピードで走っていたんです。オイル漏れの現場を通り抜け、マシンのコントロールを失いました。時速約100マイル(約160キロ)で低いコンクリートの壁に激突したんです。」
「なんてこった、最悪!明らかにお前は成功したのに…彼女も?」
「最初は、あの血まみれの手足、引き裂かれた服、バイクの部品の山の中に、生き物がいるはずがないと思いました。私が彼女の顔に覆いかぶさると、彼女は突然目を開けました。そして、私を見た瞬間、彼女の表情に真の恐怖が忍び寄りました。「あなたの目よ!」と彼女は叫びました。」
つづく
著者:
ジョン・コンドル