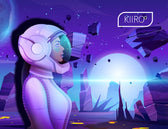パート6
最後の文章を叫んでいた間、私はすっかり夢中になっていたか、酔っていたか、あるいはその両方で、バーの音楽が止まったことに気づきませんでした。近くにいた何人かの人々が、困惑した表情から同情的な表情まで、私を見ていました。その中には、大胆な赤いドレスを着た、背が高く、髪が長いブロンドの女性がいました。
「ああ、かわいそうに!」彼女は叫んだ。「あなたの話から私が感じたのは、本当に胸が張り裂ける思いでした。私と友人があなたたちにビールを一杯ご馳走しましょう。それから、結末を聞かせてください。」
彼女が言っていた友人は、彼女の隣に立っていた。30代、褐色の肌をした東アジア系の女性で、身長約160センチ、黒髪が長く、とても人懐っこい顔をしていた。彼女はうなずいて同意を示し、二人は一緒にバーへと向かった。
「女の人がビールをおごってくれるなんて? すごいね!」トムは笑った。「さて」と彼は続けた。「君は左目を失ったって言うつもりかい? それで、僕を見つめていないほうは義眼だって。」
私は首を横に振った。「目は確かにあるんです」と私は言った。「ただ機能していないだけ。いや、まだ1%くらいは機能しているんです」
「君は1パーセントの人間だよ!」トムは笑った。
「ひどい!」と、髪の長い女の子が叫んだ。彼女はビールを4本手に持ち、私たちに近づいてきた。「あの子に何が起こったのか知りたいわ」と言いながら、ビールを私たちのテーブルに置いた。
「エイダは本当に最悪だったよ」と私は言った。
「彼女は成功したのか?」
「はい、彼女はそうしたが、そうしなかったのと同じかもしれない。」
「なぜそんなことを言うんですか?」
「ええ、彼女の全身は完全に壊れていました。数日間、人工的に昏睡状態に置かなければなりませんでした。右腕と右脚の負傷はひどいものでした…最終的に医師は左前腕と右足を切断せざるを得ませんでした。」
髪の長い少女は悲鳴をあげ、アジア人少女は口に手を当てた。
「それは本当にひどい!」金髪の女性は叫んだ。
「確かにそうだ」私はため息をついた。
「ちょっと冷たく聞こえるかもしれないし、専門的すぎるかもしれないけど」とトムは言った。「でも、二人の経済状況を考えずにはいられない。医療費はとんでもない額だったに違いない。どうやってやりくりしたんだい?」
「いい質問ですね」と私は言いました。「私たちはそうしませんでした。」
「できなかったの?」
「いや、無理だったんです。お金がなかったんです。エイダは手術後、奇跡的に早く回復しました。でも、退院の日が近づくにつれ、私たちは経済的な状況にパニックになり始めました。どこかでローンを組もうかとも言ったのですが、エイダは拒否しました。
誰がこんなことを思いついたのかは知らないが、いつの間にかエイダを一銭も払わずに国外へ密輸する話が持ち上がった。その夜、私はエイダを車椅子に乗せて駐車場まで連れて行った。そこには従兄弟のジミーがビュイック・ヴェラーノで待っていた。ジミーは私たちの突飛な計画に協力してくれることになったのだ。
「どれだ?」トムはうなずきながら尋ねた。
「彼女をキューバに連れて行くためです。」
「どうして?そんなわけないだろ…」
「ああ、そうだな。ジミーのヨットクラブに直行して、エイダをスピードボートに乗せてやった。夜も更けようとしていた頃、外で待っていると、夜明けの光が海を照らし始めたんだ」
「つまり、あの女と、あなたとあなたのいとこのこと?」
「いや、ジミーはもう十分やった。残っていたのはエイダと私だけだった。なんとかキューバにたどり着き、エイダの帰国便も手配した。言うまでもなく、別れは辛く、緊張した。もう何を話せばいいのか分からなかった。喉にゴルフボールほどの塊が詰まったような感覚で、スチュワーデスがエイダを車椅子でゲートまで連れて行き、私の人生から去っていくのを見守った。」
「あら、大変!」と、髪の長い少女は言った。大きな茶色の目に涙が浮かんだ。にじんだマスカラを拭いながら、彼女は言った。「ごめんなさい。まるで女の子みたいにヨダレを垂らして、すすり泣いて、自己紹介もしてないのに。」
「大丈夫ですよ」と私は言った。「では、自己紹介をしてください。」
「私はメアリーです」と彼女は言いました。「そしてこちらは私の友達のアリスです。」
私たちは名前を告げ、全員で握手をしました。トムは言いました。「数年前、握手が禁止されていたのを覚えてる?」
「ばかばかしい!」私は叫んで、みんなで笑いました。
その時、DJが古典的なデトロイトテクノを演奏し始めました。
「MDMA でみんなを元気づけられるかもしれないわ」とメアリーは言った。
「いいか、ジョン」とトムが言った。「今がその時だ。まさに今がその時だ。お前は人生に二流の娼婦のように翻弄されてきたが、責任はここで終わる。メアリーのマンディを食べて、思いっきり楽しもう!」
マンディがテーブルの下で私たちの手の甲に砕いたMDMAの粉末を振りかけ、私たちは皆、何気なくその結晶で唇を拭った。ダンスフロアには小さな人だかりができていた。女の子たちもそれに加わることにした。数分後、トムと私は彼らの後を追った。
アリスはベージュのドレスを着て、とてもセクシーに見えた。ここ数年、一人で過ごす時間が長すぎて、女性に対して少し恥ずかしさを感じていたのだが、突然、目に見えない力が私を掴み、彼女へと押し寄せるのを感じた。その力は弱まることはなく、数秒後にはアリスの顔がすぐそばまで迫ってきた。私は彼女の目をまっすぐに見つめ、腰に腕を回した。

「今すぐ彼女にキスしなきゃ!」頭の中で力が爆発した。この提案は明らかに議論の余地がない。だから私は言われた通りにした。
彼女は最初頭を後ろに倒したが、それから笑い出し、キスを返した。数秒後、彼女は突然笑い出した。
「何がそんなにおかしいの?」と私は言った。
「キスして!」彼女は叫んだ。
'はい...'
「君がキスするの、すごく面白いよ... 君はまさにそんな風にキスするんだ。」
私は彼女が完全に正しかったことに気づきました。これが彼女が私に話してくれた最初の言葉であり、私は突然彼女にキスをしていたのです。
「何か問題でもあるのか?」私は恐る恐る尋ねた。
「いえ、問題ありません。ただ面白いだけなんです。」
'あなたはそれが好き?'
'はい、そうします!'
「それは嬉しいですね。」
長く激しいキスを交わし、舌先で互いの唇の奥を探り合った。一瞬、メアリーが微笑み、トムも笑いながら両手の親指を立てているのが見えた。アリスは体をくねらせ、私は彼女をぎゅっと抱きしめた…私たちは音楽に身を委ねた。
彼女の体がリズム。私の心臓がリズム。すべてがシンクロしていた。ジーンズ越しに彼女のお腹に押し付けられる、巨大な勃起を抑えきれず、一瞬恥ずかしくなった。アリスは私の不安を和らげるように、くるりと向きを変え、引き締まった丸いお尻を私のペニスに擦り付けた。
遠くから奇妙な笑い声が聞こえ、その笑い声はまるで小石の浜辺に打ち寄せる波のように私の方へと押し寄せてきた。レーザー光線の中からトムの顔が浮かび上がった。
「本当にそうなんですか?」と彼は笑った。
「はい、なぜ確信できないのですか?」
彼は一体何を言おうとしているのだろう。何を確信すればいいのだろう。一瞬、私は緊張し、混乱した。
「彼女は、あのね、この物語のハッピーエンドにはお金を払わないといけないのよ。」
他のシナリオが頭の中を駆け巡り始めていたので、この説明にホッとした。アリスは振り返って私たちの方を向いていた。「お友達の言う通りね」と彼女は言った。「ごめんなさい。気にしないで。今キスしたでしょ?すごく面白かったわ!続きもしたいんだけど、一晩一緒に過ごすには500ドルかかるわ」
私がひどく失望しそうになる前に、トムは叫んだ。「決まった!これは俺の責任だ、ジョン!今夜はお前のものだ!責任はここで終わると言っただろう。今夜を受け止めて噛み砕け!全てお前のものだ。」
つづく
著者:
ジョン・コンドル
イラストレーター:
フロリス・ピータース
フロリスはアムステルダムを拠点とするオランダのイラストレーター、ストーリーボード作家、漫画家です。
Instagramでフォローしてください @florispieterse