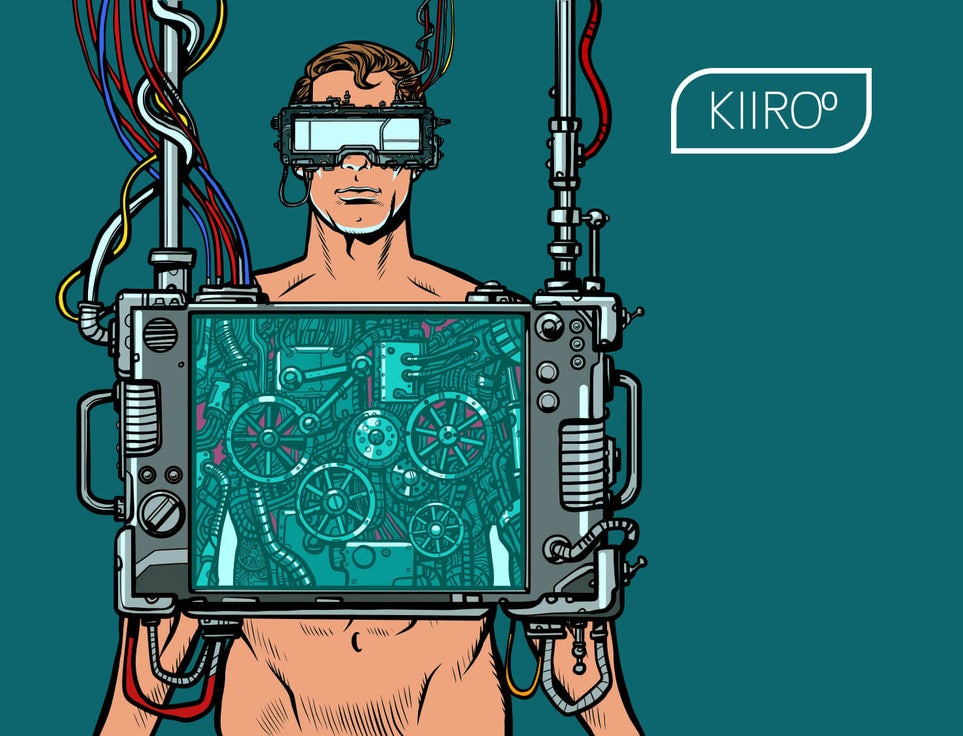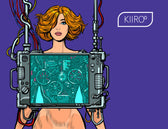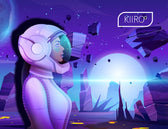サイバーマンデーのエロティックストーリー
「この村のことは聞いたことがなかった」私はバーの後ろの女性に言った。
「まさか、そんなことないわよ」彼女は目を細めてクスクス笑った。彼女は私が今まで見た中で最も風変わりな女性の一人だった。驚くほど美しかったが、同時にただただ奇妙でもあった。彼女の顔は、日本人女性によくある繊細な顔立ちでありながら、ブロンドの髪と明るい緑色の目をしていた。彼女の体型はどちらかというとラテン系で、大きな胸と膨らんだお尻だった。
彼女は、安川村に入ってから初めて、そして唯一出会った人だった。45分ほど歩き回って、バーやレストランが立ち並ぶ路地に着いたが、そのうち一つだけが開いていた。そのバーで、驚くほど美しい若い女性が温かく迎えてくれた。どうやら彼女は一人で店を切り盛りしているらしい。客は私一人だった。
「今は正午だし、この通りのバーやレストランには他に昼食を食べている人はいないよ」と私は彼女に言った。
「ここは小さな村です、皆が働いています」と女性は話した。
「でも、なぜバーやレストランがそんなに多いのですか?」と私は尋ねました。
彼女は私の質問に答える代わりに、お酒と一緒におにぎりはいかがですかと尋ね、「うちのおにぎりは県内で一番ですよ」と付け加えた。
「えーっと、わかりました…」
しばらくして、私は3つ目のおにぎりを4つ目の日本酒で一気に飲み干した。「これ、すごく美味しいですね。自分で作ったんですか?」と私は言った。
「いいえ、妹が作っています。彼女に会ってみませんか?」
「ああ、もちろん」
ドアがスライドして開き、バーの女性とほとんど同じ風貌の、もう一人美しい女性が現れた。緑色の髪と金色の瞳だった(なぜ金髪だと思ったのだろう?)。「私の名前はデスティニー。好き?」と彼女は言った。
私は「そうかもね」と笑った。なんて変な女性たちなんだろう…と思った。
「あなたとお酒を飲みたいの。いい飲みゲームを知ってるわ」とデスティニーは言った。「わかった…」
「曲はこうです。ポリスの『ロクサーヌ』を演奏します。スティングが『ロクサーヌ』を歌うたびに、どちらかが日本酒を飲み、スティングが『プット・オン・ザ・レッド・ライト』を歌うたびに、もう一人が日本酒を飲みます。あなたはどちらのパートを選びますか?」
「『プット・オン・ザ・レッド・ライト』にしよう」と私は言った。このフレーズは「ロクサーヌ」ほど頻繁に出てくるはずがない、と思っていたのだ。しかし、それは間違いだった。歌が終わると、私もまた間違っていた。「少し顔色が悪いわね」とバーの女性は言った。
「昼食時にそんな風に飲むのは慣れていないんです」と私は苦労して答えた。
「少し横になって休みませんか?」デスティニーは尋ねた。
「はい…えーと、何ですか?」
「私たちはすぐ近くに住んでいます。ソファで泊まっていってもいいですよ」この全く異例の申し出を断ろうなどとは思いもしませんでした。
「当店までご案内いたします」とバーの女性が言った。彼女は突然バーカウンターの後ろから現れ、左腕を私の右腕に絡ませた。同時に彼女の妹も右腕を私の左腕に絡ませた。
私たちは通りを進み始めた。まるで運ばれているようだった。周りの奇妙な看板がぼやけて見えなくなった。私たちはコンクリートのアパートの前に止まった。そこには「ダッチ・ワイブス・ホテル」と書かれた大きなネオンサインが飾られていた。
「変な名前だ…ここはホテル…ホテルに住んでいるの?誰がホテルに住んでいるの?何が起こっているの?」と私はつぶやいた。
「大丈夫、私たちと一緒に来てください」とデスティニーは言いました。
エレベーターで7階へ。ミニマルでハイテクなアパートメントに案内され、白いソファに丁寧に座らされた。「お茶をお入れします」とバーテンダーが言った。「とても強いお茶です。奇跡を起こすはずです、信じてください」
彼女の言う通りでした!一口飲むごとに力が戻ってくるのを感じました。「わあ、これは最高!」と私は言いました。「ありがとう…バーの女性」
「私の名前はハーモニーです。」
「ハーモニー、お会いできて光栄です。実は、あなたの優しさに少し圧倒されているんです。こんなこと、私が受けるべきことなのか、ちょっと不安です」私はそう言いながら、ソファに両脇に寄り添う女の子たちを見つめた。
「ああ、こちらこそ光栄です!」とデスティニーが言った。「とても素敵なお客様ですね」とハーモニーが付け加えた。
眠気と高揚感、そして信じられないほどの興奮を感じた。もう自分を抑えることができなかった。「お二人とも綺麗な脚ですね」と私は言った。「触ってもいいですか?」二人とも顔を赤らめた。
「さあ、行きましょう」とデスティニーは言った。
「そう言ってくれることを期待していました」とハーモニーは付け加えた。
左手をデスティニーの膝に、右手をハーモニーの膝に置いた。背筋がゾクゾクした。夢を見ているのだろうか?幻覚を見ているのだろうか?事故に遭ったのだろうか?こんなの現実じゃない。同時に、顔の両側にキスをされた。幻覚だろうとなかろうと、私は地獄に落ちてやる!と心の中で言った。「この状況を乗り越えよう」
気がつくと、二人の舌が私の舌を弄んでいた。胸が露わになり、スカートのボタンが外されてストッキングが露わになり、ジーンズが足首まで引き下げられた。そして私たちは裸になった。女の子たちは交代でフェラを始めた。
「なんてこった!」私は叫んだ。「あなたのその神聖な口には一体どんな力があるのか?絹のような唇をした掃除機が2台も付いているみたい!ああ、信じられない!我慢できない!」
「ヤバすぎる!クソ、クソ、クソ。」私がイク直前に彼らは止まった。
「まだ来ないで、もう少しお茶を飲んで。次は私たちに乗って。波のように、風のように、駆ける馬のように、私たちの体に乗って。」
そして実際、私はまさにそれを実行したのです。
「あなたのシックなソファーに射精してしまってごめんなさい」私はその後でどもりながら言いました。
「またぜひお願いします」
彼らはそれを二度言う必要はなかった。
姉妹たちが私を取り囲む中、ソファで眠り込んでしまった。日が沈み始めた頃に目が覚めた。服を着替えた後、村を散策しようと外に出た。まだ用事がある時間だった。
ダッチワイフ・ホテルから一歩外に出た途端、街灯とネオンサインが明るくなった。そしてなんと、ついに通りに人がいたのだ。なんと二人の男性が、まっすぐ私の方へ歩いてきた。一人は日本人、もう一人はヨーロッパ人風で、私の目の前で立ち止まった。
「ジョン・コンドルさんですね。お会いできて光栄です」と日本人は言い、頭を下げた。「私は蘭学教授、こちらは私の尊敬する同僚のバルトリン博士です」
もう一人の男は、ソーセージのような指をした大きな白い手を差し出した。「どうして私を知っているんですか?」私はためらいがちに握手をしながら尋ねた。
蘭学教授の唇に、はにかんだ笑みが浮かんだ。「どうやら、我々の商品のデモンストレーションは…満足のいくものだったようだな。」
'何?'
「あなたはビジネスのためにここにいらっしゃいます。そして、当社の最新の試作品はあなたを温かくお迎えしました。きっとご満足いただけたと思います。」
「なんてこった!あの子たち……ハーモニーとデスティニー、ロボットなの!?」私は叫んだ。
「でも、でも…どうしてそんなことが?汗もかいてたし、オーガニックな匂いもしたのに」私はどもりながら言った。数秒黙っていたが、すぐに正気を取り戻した。
「信じられない。なぜあなたの仕事のことを誰も知らないのですか?」と私は言いました。
「私たちは製品を発売する適切な時期を待つことにしました。今がまさにその時です。準備は万端です。ぜひ貴社とお取引させていただきたいと思います。」
デスティニーとハーモニーがアメリカに一緒に帰ってくれました。パスポートとビザが必要だったんです。本当に笑えました。職場の人たちはすっかりびっくりしていました。
「正気じゃない!」上司が叫んだ。「何週間も姿を消して、その後誰も聞いたこともない最先端のセックステクノロジー製品を持って現れるとは。一体いくらするんだ?数百万ドル?俺に何をしろと言うんだ?まだ給料を期待しているのか?」
「はい」と私は言った。「安川電機の人たちがデスティニーとハーモニーを数十台送ってくれる予定です。販売はしませんが、プロモーションに使えます。日本の人脈の力を借りれば、大人向けのテクノロジーを幅広く提供できます。サイバーマンデーではなく、『サイボーグマンデー』と名付けましょう。」
全世界が注目するでしょう...
著者
ジョン・コンドル
Kiiroo製品を他社製品と比較してみましょう。比較表をご覧ください。