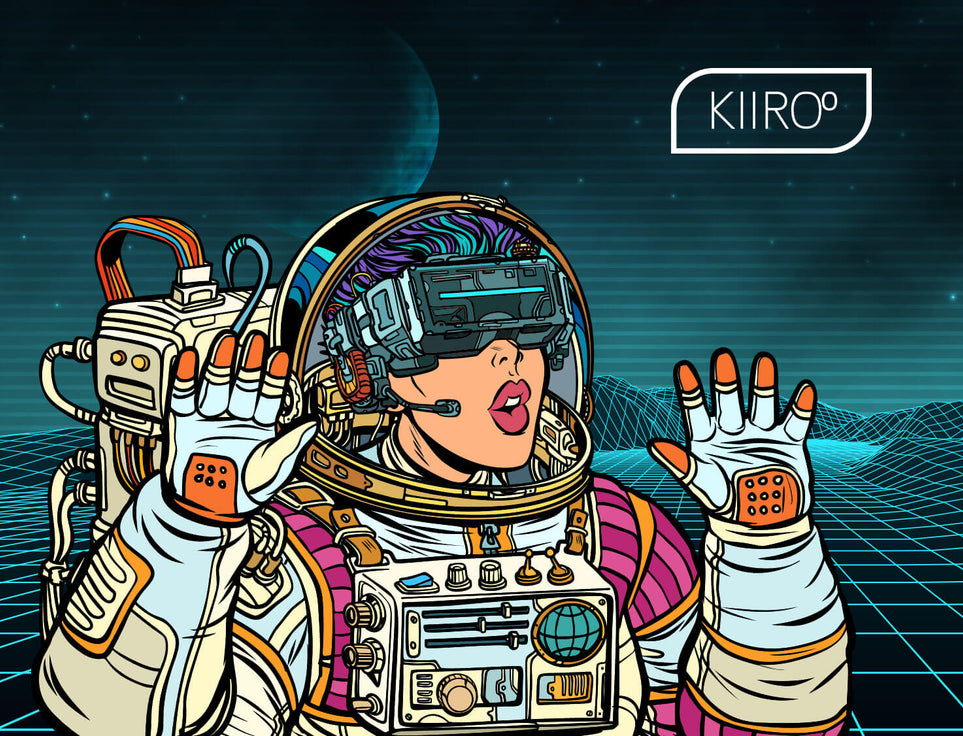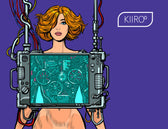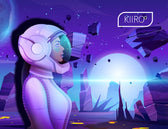パート7
クラブにいたのに、次の瞬間には真新しいブロックチェーンの自動運転タクシーに乗っていた。トムは私たち全員を彼の家に招待してくれた。街灯が点滅し、地平線の高層ビル群が大きくなっていく中、私たちはダウンタウンへと向かって疾走した。
アリスは甲殻類のように私にしがみついていた。左腕を背中に回し、左手で胸を撫でていた。右手は太ももに置いた。しなやかな指先が下腹部とベルトの上を戯れるように動いていた。
「あなたってすごくセクシーね。あの俳優のライアン・ゴズリングみたい。今夜あなたに会えて本当に嬉しいわ」と彼女は私の耳元でささやいた。
「お互いに喜び合っています。」
彼女の舌先が私の首に触れ、右手の指が私のベルトの下、下着の中に滑り込むのを感じたとき、私はため息を抑えることができませんでした。
「ああ、ああ、君は悪い、悪い女の手に落ちてしまったんだね」とトムは笑った。
彼は私たちの向かいの後ろ向きの席に座り、メアリーを膝の上に座らせていました。
その間、金属的な女性の声が「シートベルトをお締めください!シートベルトをお締めください!」と繰り返していた。
タクシーは、デトロイトのスカイラインに最近加わった、実に派手なネオアールデコ様式の高層ビルの前で止まりました。
「なんてことだ!」私は叫んだ。「ここがあなたの住んでいるところなのですか?」
「そうだな」とトムは言った。「ホドラー本人からは、それ以上のことは期待していなかったのか?」
私と女の子たちは困惑した表情を交わした。
「君は私の言うことを信じていないようだね!」とトムは言った。
「えっと、それはそうじゃないんです」私はためらいながら言った。「それは…」
「俺を最低な奴だと思ってるってことだろ。俺に何も期待してないだろ。分かってるよ、分かってるよ」とトムはニヤリと笑った。「大丈夫だよ、俺はただ自分に正直でいただけなんだ。昔はちょっと浮浪者だったけど、お前とは違って暗号通貨で大金を稼いだんだ。神様って不思議な力を持ってるんだな…でも、全ては公平だと思う。お前は見た目で、俺は金持ちだ。さあ、さっさと上へ進もうぜ」
私たちは広いロビーに入った。床も壁も、少なくとも5種類の白と黄色の大理石でできていた。エレベーターで54階まで上がった。トムのアパートは建物の正面にあった。彼は虹彩スキャナーを覗き込み、玄関のドアを開けた。
「オーマイゴッド、オーマイゴッド、オーマイゴッド!」トムのとてつもなく豪華なアパートに入ると、娘たちは悲鳴を上げた。複雑なLEDの模様で照らされた廊下を抜けると、1000平方フィートほどの広さがあるリビングルームに出た。部屋の反対側は、床から天井まで続く青みがかった窓で囲まれていた。都心部と湖を見渡すパノラマビューは、この世のものとは思えないほどだった。
「悪くないよ、トム」と私は言った。
「もっとひどいこともあるよ」と彼はニヤリと笑いながら言った。
「信じられないわ」とメアリーは言った。「一体どうやってやったの?」
トムは喉を掻きむしった。「ここのジョンと同じように、僕も暗号通貨を発見したんだ…でも、明らかに僕の場合は少し違った。誰か飲み物を飲みたい人はいるかい?」
彼はクリスタルのボトルとワイングラスを4つ持ってきてくれた。私たち4人は窓に面した巨大な白いソファに座った。
「あのね」と彼は続けた。「昔はGMでそこそこいい仕事に就いていたんだ。一生懸命働いて、給料も悪くなかった。特に何もしていなかったから――妻もいなかったし、趣味と呼べるものもなかったし――ただ銀行にお金を振り込んでいたんだ」
2016年には既に、友人のマイケルがビットコインとイーサリアムに投資させようとしていました。「銀行に現金を預けるのは無駄だよ!」と彼は言っていました。2017年から2018年にかけての仮想通貨バブルで彼が全財産を失った時は笑ってしまいました。でも、あの出来事全体を通して、こういうバブルはまた起こるだろうと改めて思いました。
それで、あの忌々しいアルトコインがすべて価値の90~99%を失ったとき、私は買い始めたんです。2018年の夏から、毎日50ドルずつ投資し始めました。しばらくして、自分の戦略がうまくいっていることに気づき、投資額を1日100ドルに増やしたんです。
安値を見ても何も売らなかった。そして、ご存知の通りバブルが再来した。そして2020年から2021年にかけての強気相場は、どんどん上昇し続けた。言うまでもなく、私に降りかかった金銭的恩恵は、まるでハリケーンのようなものだった。お前らのケツは、その成果に見舞われているんだからな。」
「なんてこった!」私はため息をつき、両手で顔を埋めた。
「ああ、うちの可愛い息子はもう我慢できないんだ。嫉妬しすぎなんだ」とトムは言った。
「かわいそうなジョン!」アリスは叫びました。
「本当にかわいそうなジョンだ」トムは皮肉っぽく笑った。「とてもかわいそうに。」
「いきなり失礼なこと言わないで。どこからそんな考えが出てきたの?」メアリーはトムを落胆したように見ながら言った。
「ああ、冗談だよ」とトムは言った。「今夜は最高に楽しいよ。友達同士のちょっとした冗談なんてどうでもいい。飲もうぜ。」
子どもみたいに嫉妬を表現してしまったことが恥ずかしくて、左手を上げて頭を下げて謝りました。「トムが私をからかうのは当然よ。私はバカなのよ」と私は言いました。
「あら、この馬鹿野郎。中にすごくタフな男がいるって分かってるわ。連れ出してあげるわ」アリスは言った。彼女は再び私のところに忍び寄り、私の唇に自分の口を当てて舐めた。右手はまた私のベルトを弄り始めた。彼女がなんとか私のズボンを開けてくれた時は、本当にホッとした。私のペニスは今にも破裂しそうだったからだ。彼女は器用に私のズボンと下着を脱がせ、性器をマッサージし始めた。
「すごくいいね!」左からトムの声が聞こえた。私は彼を無視しようとした。視界の隅で、彼が小さなガラスの小瓶を手に取っているのが見えた。彼は小さなスプーンを使って、小瓶から白い粉を鼻に吸い込み始めた。「すごくいいね!」彼はまた叫んだ。
アリスが私の前に膝をつき、フェラチオを始めたので、私の意識はすぐに下腹部で起こっていることに引き戻された。彼女の唇はサテンのように柔らかかったが、唇はしっかりとしていた。背骨を伝い、後頭部まで突き刺さる衝動が走った。アリスがさらに強く、さらに深く吸い始めると、パチパチという音が響き、目尻に星が見え始めた。
しかし、左コーナーでトムが再び私の気を逸らしたため、星空は消え去った。彼はポケットからマネークリップを取り出し、札束を取り出し、テーブルに放り投げた。「さあ、仕事は終わった。今度はお前らがやってくれ」と彼は唸り声を上げた。
「そんな風に呼ばないで」私はうめいた。
「大丈夫よ」メアリーは言った。「彼はただの、いやらしい、性欲の強い野郎なのよ。あなたはトムじゃないの?」
「そうよ、そうよ!さあ、メアリー、窓のところまで歩いて行って服を脱いで。」

彼女は言われた通りにした。背中のファスナーを開けると、赤いドレスが足元に落ちた。背中はくぼんでいて、お尻は丸く、それでいて引き締まっていて、脚は長く、体は滑らかに動いていた。鮮やかな赤、薄黄色、蛍光グリーン、琥珀色…と、強烈な色彩の閃光に包まれているようだった。もっとも、それは私の頭の中で想像しただけだった。フェロモン、エンドルフィン、ドーパミン、セロトニンの洪水が、私の知覚に及ぼした影響だった。
彼女は黒い下着を脱いだ。
「どこかの変態の覗き魔が双眼鏡で君を見つめているといいな。それは最高だ」とトムは言った。「このパーティーにおもちゃを持ってこよう」
彼はコーヒーテーブルの引き出しから長方形の黒い箱を取り出した。開けてみると、中には性具がぎっしり詰まっていた。「そうだな、ジョン。お前はセックスネタばかりで自分が変態だと思ってただろうが、本当の卑猥な王様は俺だ、ハハハ!」
つづく
著者:
ジョン・コンドル